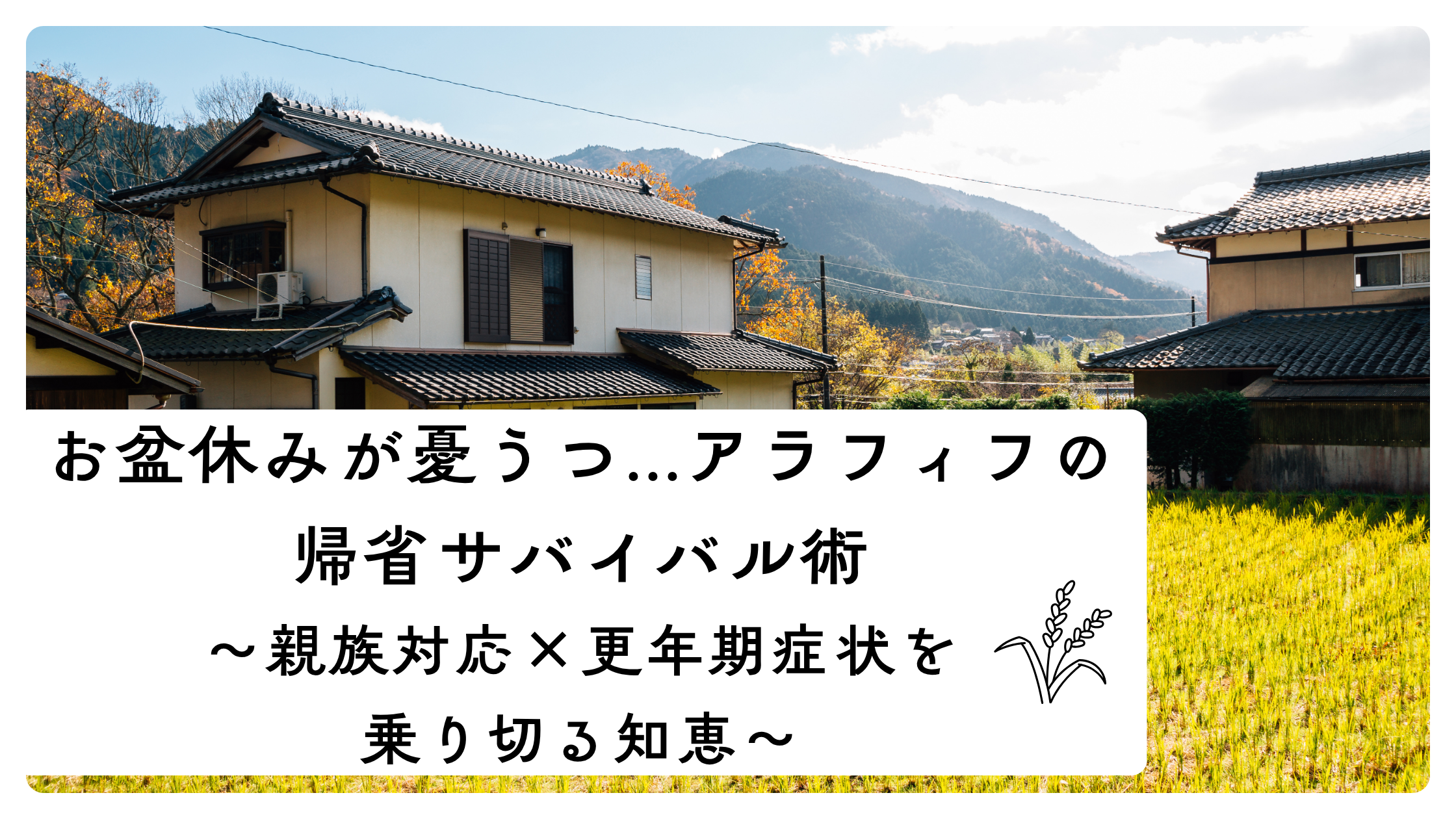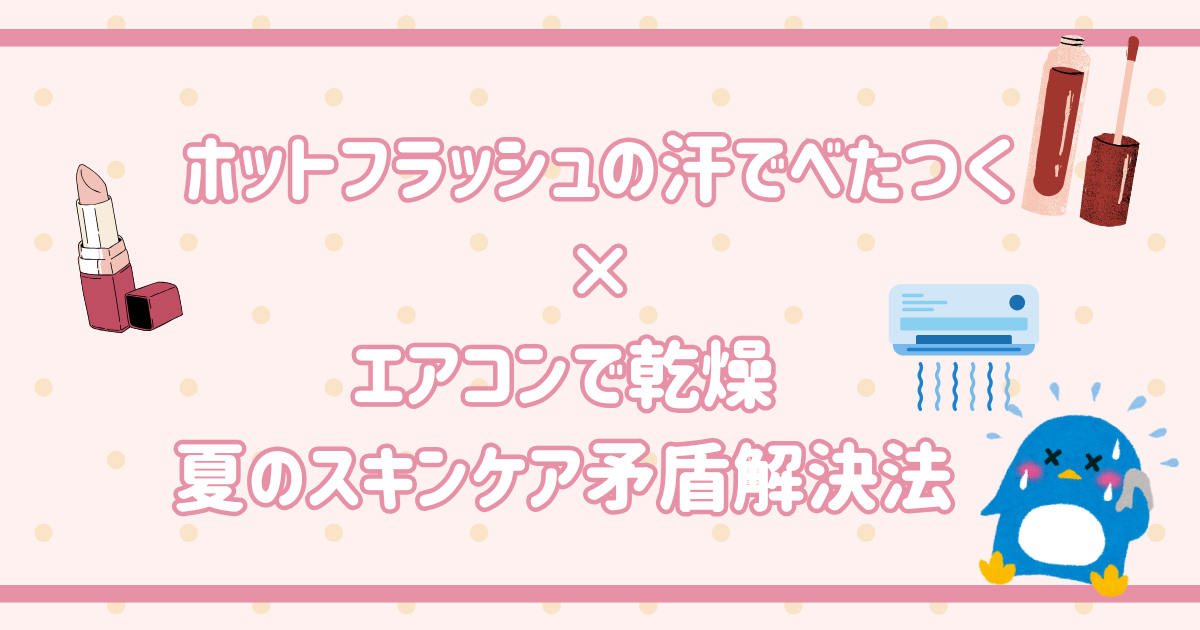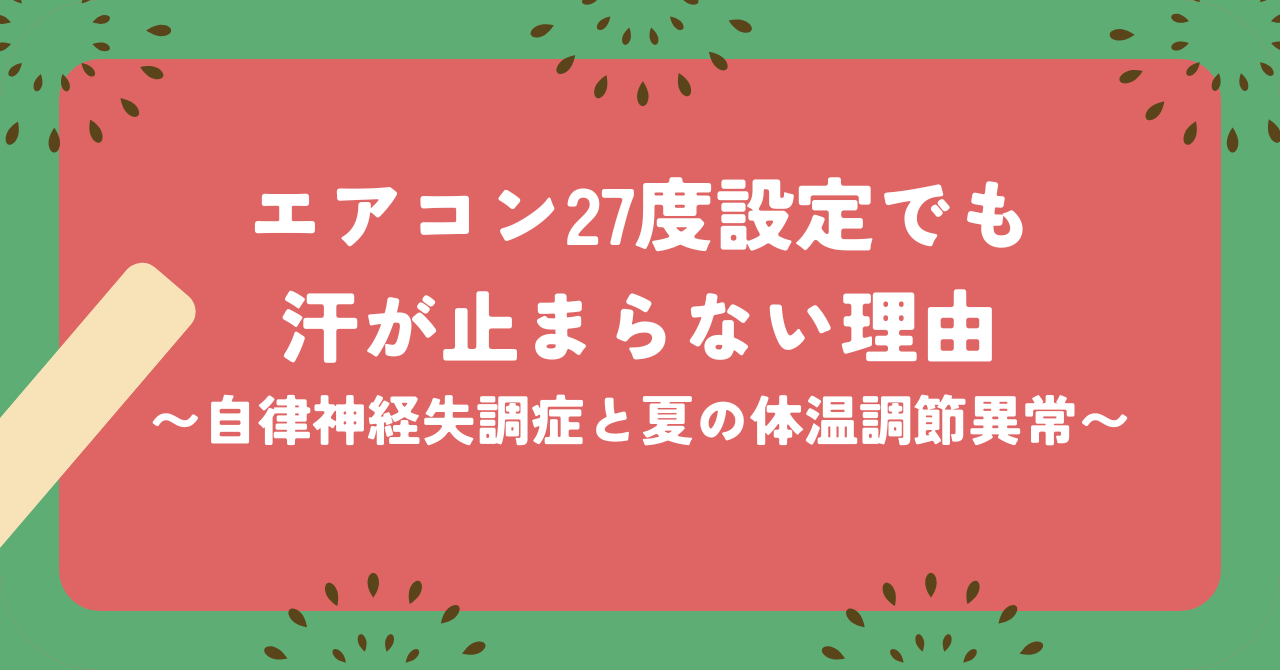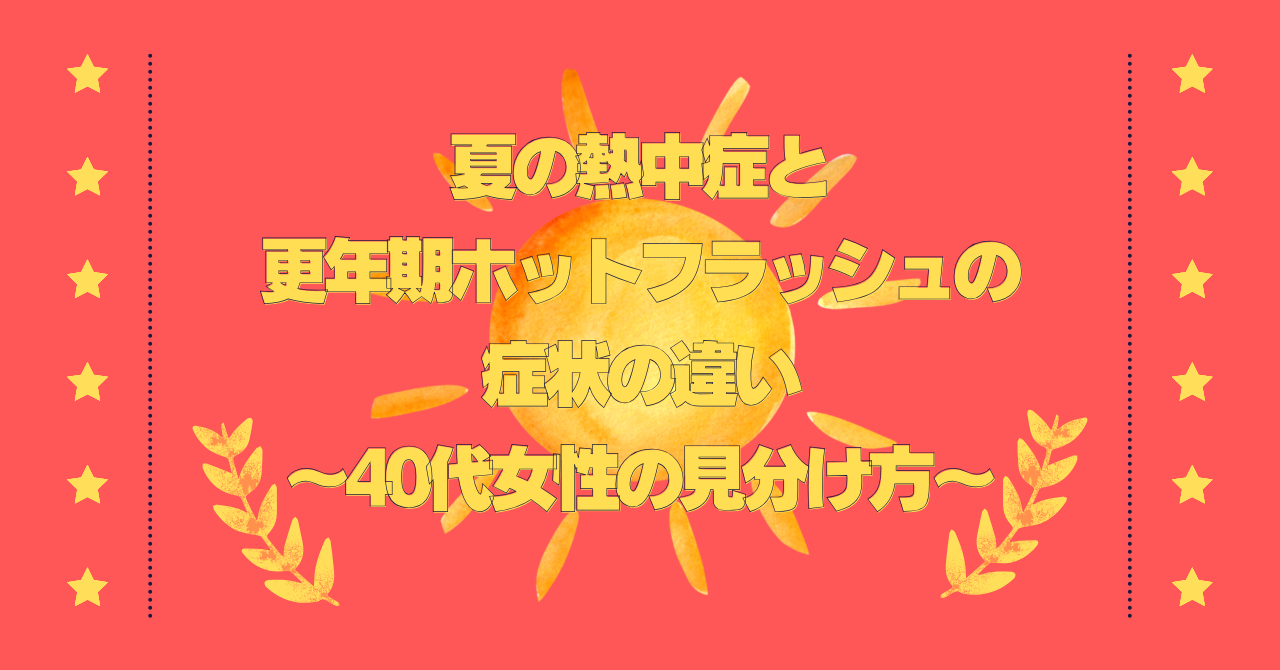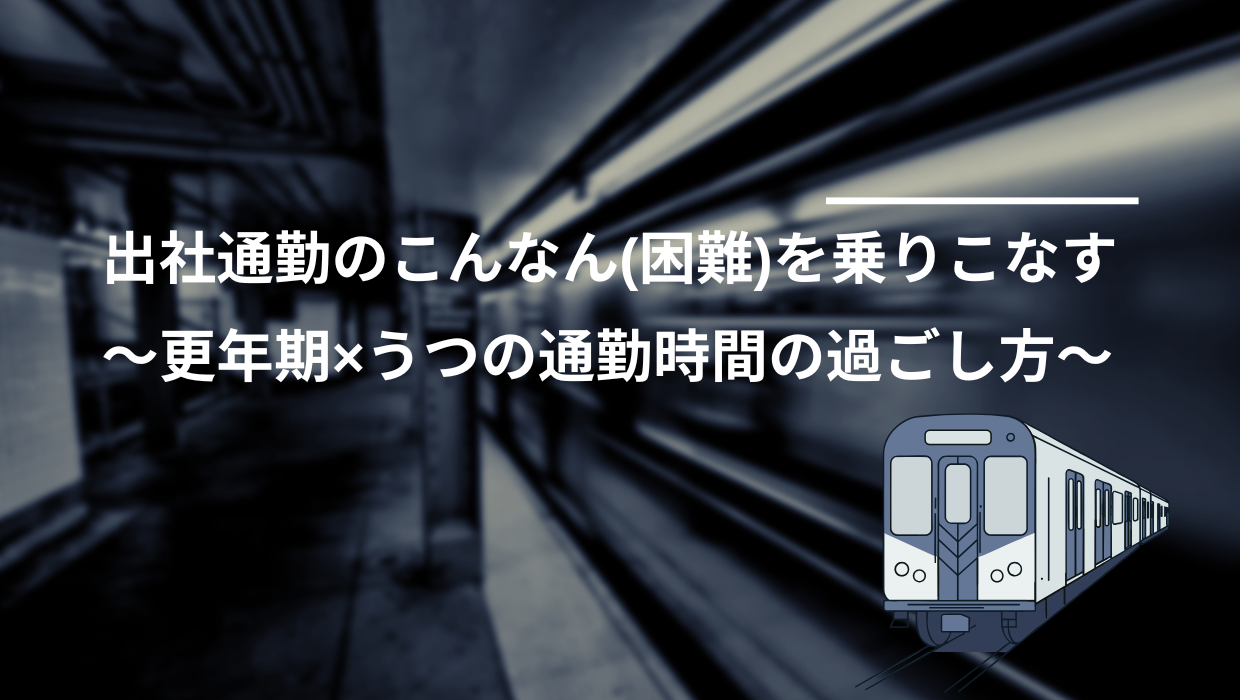仕事と健康の二本立て、長い就業人生をサバイブする

仕事と健康の二本立て、長い就業人生をサバイブする
〜知っておきたい制度とサポート〜
「困難な日も、こんなんな日も」の管理人、こんなんさんです。
「体調不良なのに休め辛い」「このまま働き続けられるか不安」「もっと柔軟な働き方ってできないの?」
40〜50代の私たちが直面するこんなん(困難)は、健康面の変化だけでなく、仕事との両立にも及びます。でも、知っておくべき制度や権利を理解していれば、少し心が軽くなるかもしれません。
今回は、更年期症状やメンタルヘルスの問題を抱えながら働き続けるために知っておきたい制度や権利について、私自身の経験も交えながらお話しします。
■ 知っててほしい、労働者の健康に関する権利
休職制度—心と体を回復する時間
46歳で急激なうつ症状が現れたわたし。最初は「休むのもなー」と思っていました。でも、主治医と産業医から「今すぐ休んでください」と言われ、会社の休職制度を利用することに。
休職制度とは、病気やケガで一定期間働けない場合に、雇用関係を維持したまま休める制度です。正式には「休業」と呼ばれ、労働基準法で定められた権利です。
休職制度のポイント:
- 多くの会社では就業規則に休職期間や条件が定められています
- 一般的に、勤続年数に応じて休職可能期間が設定されていることが多いです
- 医師の診断書が必要(診断書の書き方については医師に相談を)
- 傷病手当金(健康保険)で収入の約2/3をカバーできる場合も
「休職後の復帰が憂鬱だからこのまま我慢して働こう」と思う必要はありません。心と体の健康を回復させるための正当な権利です。主治医と相談しながら、必要なら遠慮なく利用しましょう。
知っておきたい傷病手当金
休職中の経済的な心配も大きいですよね。そんなとき頼りになるのが「傷病手当金」です。
傷病手当金とは:
- 健康保険に加入している人が、病気やケガで働けないとき、収入を補償する制度
- 支給額は、直近の給与(標準報酬日額)の約2/3
- 支給期間は最長1年6ヶ月
- 連続して3日間休んだ後(待機期間)、4日目から支給
私も休職中はこの制度に助けられました。収入は減りますが、全く無収入になるわけではないので、心理的な余裕がかなりでき、おかげでゆっくり休むことができました。
申請には医師の意見書と会社の証明が必要です。申請書類は加入している健康保険組合や全国健康保険協会に問い合わせると教えてくれます。
復職支援制度—段階的に職場に戻る
休職後、いきなりフルタイムで働き始めるのは難しいもの。
復職支援の主なプログラム:
- リハビリ出社(試し出社):本格的な復職前に、短時間の出社を試みる制度
- 時短勤務:勤務時間を短縮して働く
- 業務制限:残業禁止、出張制限など、負担の大きい業務を制限
- 段階的復職:徐々に勤務時間や業務量を増やしていく
これらの制度は会社によって異なりますが、産業医や人事部と相談しながら、自分の状態に合わせた復職プランを立てられることが多いとのことです。
■ 会社と医療をつなぐキーパーソン:産業医との連携
産業医って何者?その役割と活用法
更年期症状やうつ症状があるわたしたちにとって、産業医は強い味方になりえます。
産業医とは:
- 労働者の健康管理を専門とする医師
- 従業員50人以上の事業場には、産業医の選任が義務付けられている
- 健康診断の結果確認や職場環境の改善、健康相談などを行う
産業医との連携ポイント:
- 健康上の不安があれば、産業医面談を申し出る(会社の人事部や健康管理室に相談)
- 主治医と産業医の連携が大切(情報提供同意書の提出など)
- 無理のない働き方について相談できる
産業医は会社側と労働者側の間に立ち、健康と仕事の両立をサポートしてくれる存在です。遠慮なく活用しましょう。
会社に伝えるべきこと、伝える必要のないこと
更年期症状やうつ状態について、どこまで会社に伝えるべきか迷うところ。
伝えるべき情報:
- 業務に影響する症状(集中力の低下、疲れやすさなど)
- 必要な配慮や調整(休憩の確保、残業制限など)
- 通院の必要性や頻度
伝える必要のない情報:
- 詳細な診断名(「女性特有の体調不良」「体調管理が必要な状態」などの表現でOK)
- 治療の詳細な内容
- プライベートな症状の詳細
伝える相手としては、直属の上司だけでなく、人事担当者や産業医など、状況に応じて適切な人を選びましょう。
私の場合は、「継続的な体調不良と、それに伴うメンタル面の変化があり、定期的な通院が必要」というシンプルな説明にとどめました。詳しい症状は産業医にのみ伝え、職場での必要な配慮についてアドバイスしてもらう形を取りました。
■ 健康経営という新しい風
「健康経営」って何?最近の企業動向
「健康経営」という言葉、最近よく聞くようになりましたよね。これは、経済産業省の推進している活動で、従業員の健康管理を経営的な視点で考える取り組みのこと。
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/downloadfiles/240328kenkoukeieigaiyou.pdf
健康経営の主な特徴:
- 従業員の健康増進を企業の成長や生産性向上につなげる考え方
- 経済産業省が「健康経営優良法人認定制度」を実施
- 健康診断の充実、メンタルヘルスケア、働き方改革などを推進
大企業だけでなく、中小企業でも健康経営に取り組むところが増えています。自社の健康経営への取り組みを人事部や健康管理室に確認してみると、意外な支援制度が見つかるかもしれません。
女性の健康の取り組みもはじまっています。
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/jyoseinokenko.html
会社の健康支援制度を探してみよう
健康経営の広がりにともない、様々な企業が独自の健康支援制度を導入しています。
よくある健康支援制度:
- 健康診断の追加オプション(婦人科検診など)の費用補助
- カウンセリングサービス(EAP:従業員支援プログラム)
- フィットネスクラブの利用補助
- 健康セミナーの開催
- 治療と仕事の両立支援制度
わたしのいた会社では、EAPという外部のカウンセリングサービスが導入されていて、仕事や健康、家族のことなど、様々な悩みを無料で相談できます。これは職場の人に知られることなく利用できるので、メンタルヘルスの不調を感じたときの最初の相談先として活用されるそうです。わたしの場合、メンタルダウンが来てしまったのですぐに産業医との面談となりました。
■ 自分を守る働き方って
リモートワーク・フレックスタイム制度の活用法
コロナ禍をきっかけに広がったリモートワークやフレックスタイム制度。これらは更年期症状やメンタルヘルスの波と付き合いながら働く私たちにとって、とても強力な味方になります。
リモートワークのメリット:
- 通勤のストレスや体力消耗を避けられる
- 体調の波に合わせて休憩を取りやすい
- 温度調節や服装を自分で管理できる(ホットフラッシュ対策に便利!)
フレックスタイム制度のメリット:
- 朝の体調不良や不眠後の疲労に対応しやすい
- 通院予定も組み込みやすい
- ホルモンの波に合わせた働き方ができる
こうした制度をすでに導入している会社なら、積極的に活用しましょう。まだ導入されていなくても、主治医からの意見書や産業医との相談を通じて、個別に対応してもらえる可能性もあります。
時短勤務や配置転換など、無理をしない選択肢
体調や症状に合わせて、働き方を調整する選択肢もあります。
考えられる働き方の調整:
- 時短勤務:勤務時間を短縮する(育児・介護休業法の枠組みではなく、傷病による時短)
- 配置転換:体力的・精神的負担の少ない部署への異動を相談
- 業務内容の調整:無理な業務や残業を減らしてもらう
- 在宅勤務との組み合わせ:週の一部を在宅で勤務する
大切なのは「無理をしない」こと。パフォーマンスを100%維持しようとするより、70%の力で長く続けられる働き方を選ぶほうが、結果的には会社にとってもプラスになると思っています。
■ 治療と仕事の両立支援制度を知っておく
両立支援コーディネーターという存在
「治療と仕事の両立支援」は、厚生労働省が推進している取り組みです。その中核を担うのが「両立支援コーディネーター」という専門家。
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000213499.pdf
両立支援コーディネーターとは:
- 治療と仕事の両立を支援するための専門的な研修を受けた人材
- 医療機関、企業、支援機関などに所属
- 患者(労働者)、企業、医療機関の間を調整する役割
地域の産業保健総合支援センターでは、両立支援コーディネーターによる相談も受け付けています。病院の医療ソーシャルワーカーが両立支援コーディネーターの研修を受けていることもあるので、通院先の病院で相談してみるのもよいでしょう。
利用できる外部支援機関
会社以外にも、働く人の健康をサポートする様々な機関があります。
主な支援機関:
- 産業保健総合支援センター:各都道府県に設置されている、労働者の健康確保を支援する機関。健康相談や情報提供を無料で行っています。
- 地域障害者職業センター:うつ病などで休職した人の職場復帰を支援する「リワーク支援」などを提供。
- ハローワーク:「難病患者就職サポーター」や「精神障害者雇用トータルサポーター」などの専門家による相談が可能。
- 保健所・精神保健福祉センター:心の健康相談や情報提供を行っています。
私は休職中に地域障害者職業センターの「リワーク支援」を利用しました。生活リズムの立て直しやストレス対処法、復職に向けた準備など、実践的なプログラムが役立ちました。無料で利用できるので、主治医と相談しながら検討してみるといいかもしれません。
■ 会社との上手な交渉術
必要な配慮を伝える具体的な方法
自分の状態や必要な配慮を会社に伝えるのは勇気がいりますが、適切に伝えることで理解を得やすくなります。
効果的な伝え方:
- 事前準備:必要な配慮を具体的にリストアップしておく(「残業を控えたい」「週1日のリモートワーク」など)
- 医師からの意見書を活用:主治医に職場への意見書を書いてもらうと説得力が増します(詳細な病名ではなく「女性特有の体調管理が必要」などの表現でOK)
- 段階的に提案:いきなり多くの配慮を求めるのではなく、優先度の高いものから少しずつ相談
- 貢献意欲を示す:「長く働き続けるために」「より良いパフォーマンスを維持するために」という前向きな姿勢を伝える
理解されないとき、拒否されたときの対応
残念ながら、会社側の理解が得られないケースもあります。そんなときの対応策:
- 産業医を介して再度相談:産業医から会社側への働きかけを依頼
- 人事部や上位の管理職に相談:直属の上司の理解が得られない場合は、人事部門や上位の管理職に相談
- 外部の相談窓口を利用:各都道府県の労働局や総合労働相談コーナーで相談
- 両立支援コーディネーターの活用:医療機関と職場の橋渡し役として支援を依頼
- 最終手段として転職も選択肢に:健康と仕事の両立が難しい環境なら、転職も視野に入れる
会社との話し合いが難航するときは、ひとりで抱え込まず、専門家の助言を求めることが大切。まずはご自愛からはじめましょう。
■ 自分らしく生き続けることをあきらめない
更年期症状やメンタルヘルスの問題を抱えながら働き続けるのは、かんたんなことではありません。でも、適切な制度やサポートを知り、活用するケースが増えていることも事実です。かつての自分と比べるのではなく、今の体調や状況に合った働き方を選ぶ勇気を持ちましょう。必要な時には休息を取り、サポートを求め、自分のペースを大切にする。
これからの10年、20年を見据えたとき、今は自分の体と心を守るための調整期間と考えれば、少し気持ちが楽になるかもしれません。
「困難な日も、こんなんな日も」、自分らしく働き続けるヒントが、この記事から少しでも見つかれば嬉しいです。
みなさんは、どんな工夫をして働き続けていますか?あなたの体験やアドバイスもぜひ教えてください。
「困難な日も、こんなんな日も」
── こんなんさん
※この記事についてのご感想や、あなた自身の体験談などがありましたら、ぜひコメント欄でシェアしてください。みなさんの声が、次の記事の励みになります。
*「こんなんな日も」とは、「こんなん出た」、「こんなんいるー?」など、関西弁から取りました。ただ、管理人は関西人ではありません…。