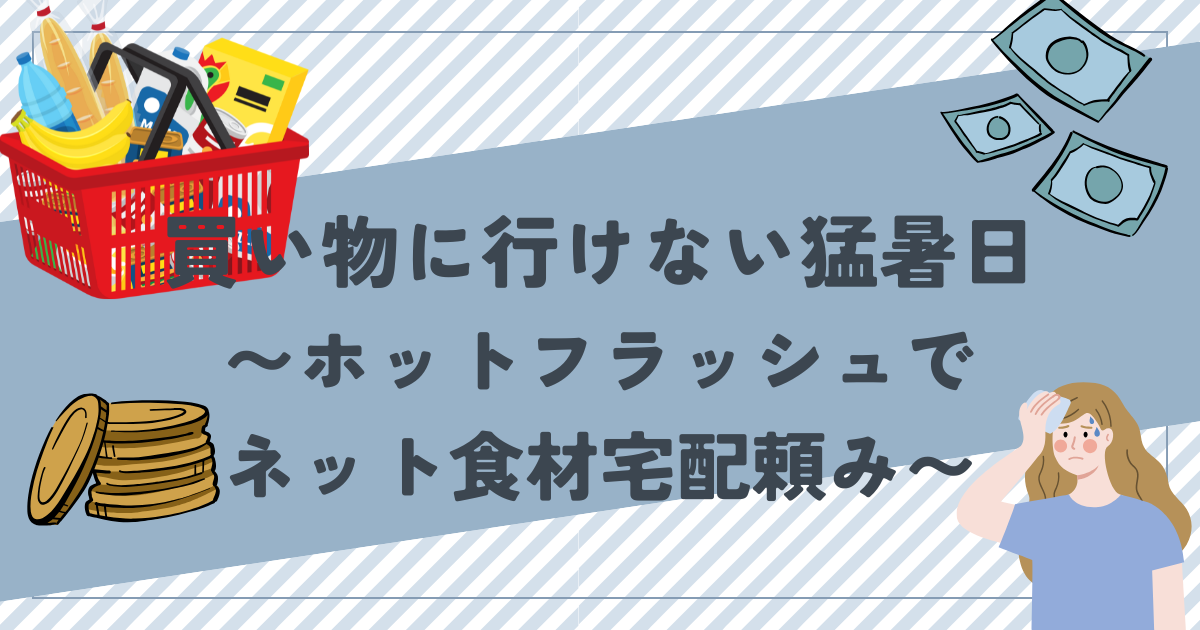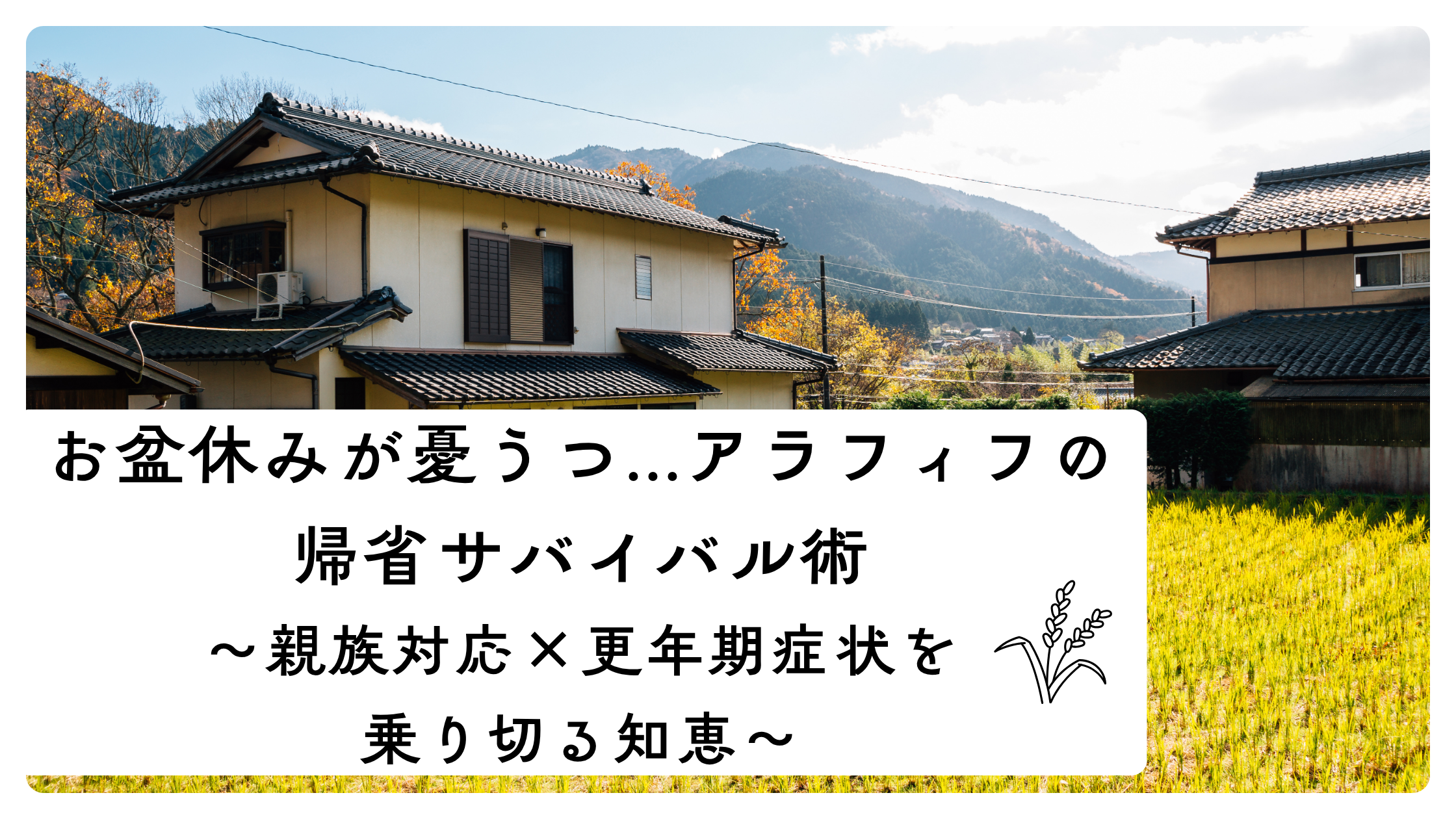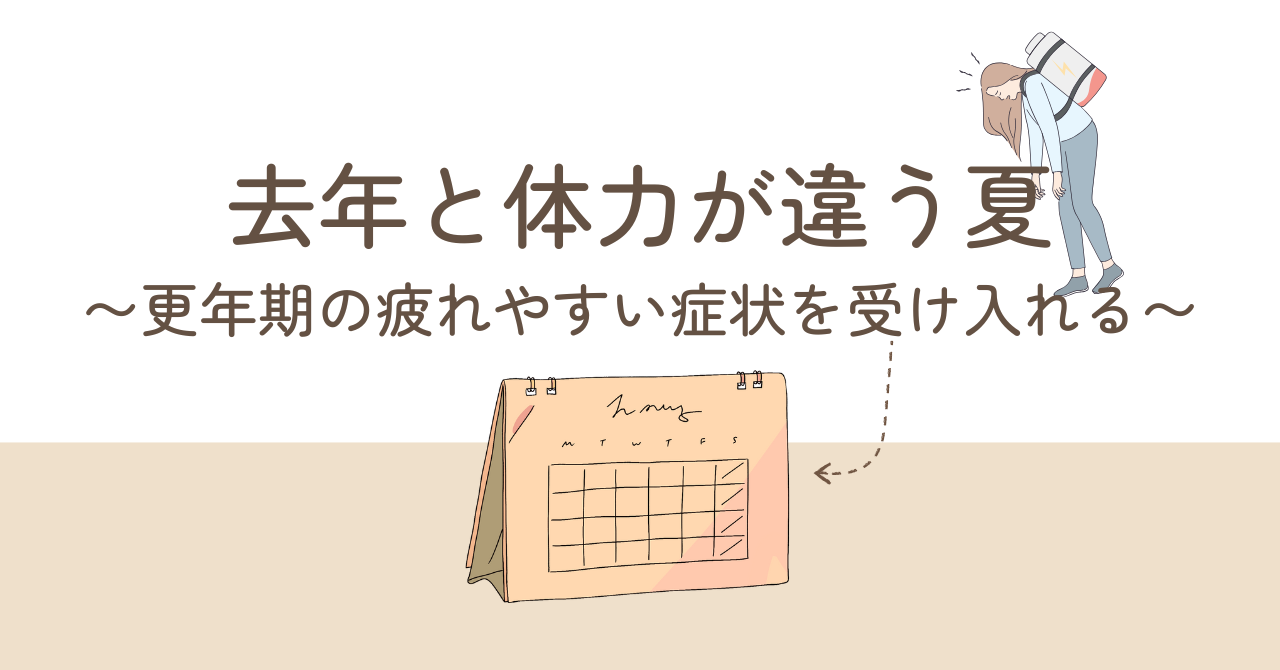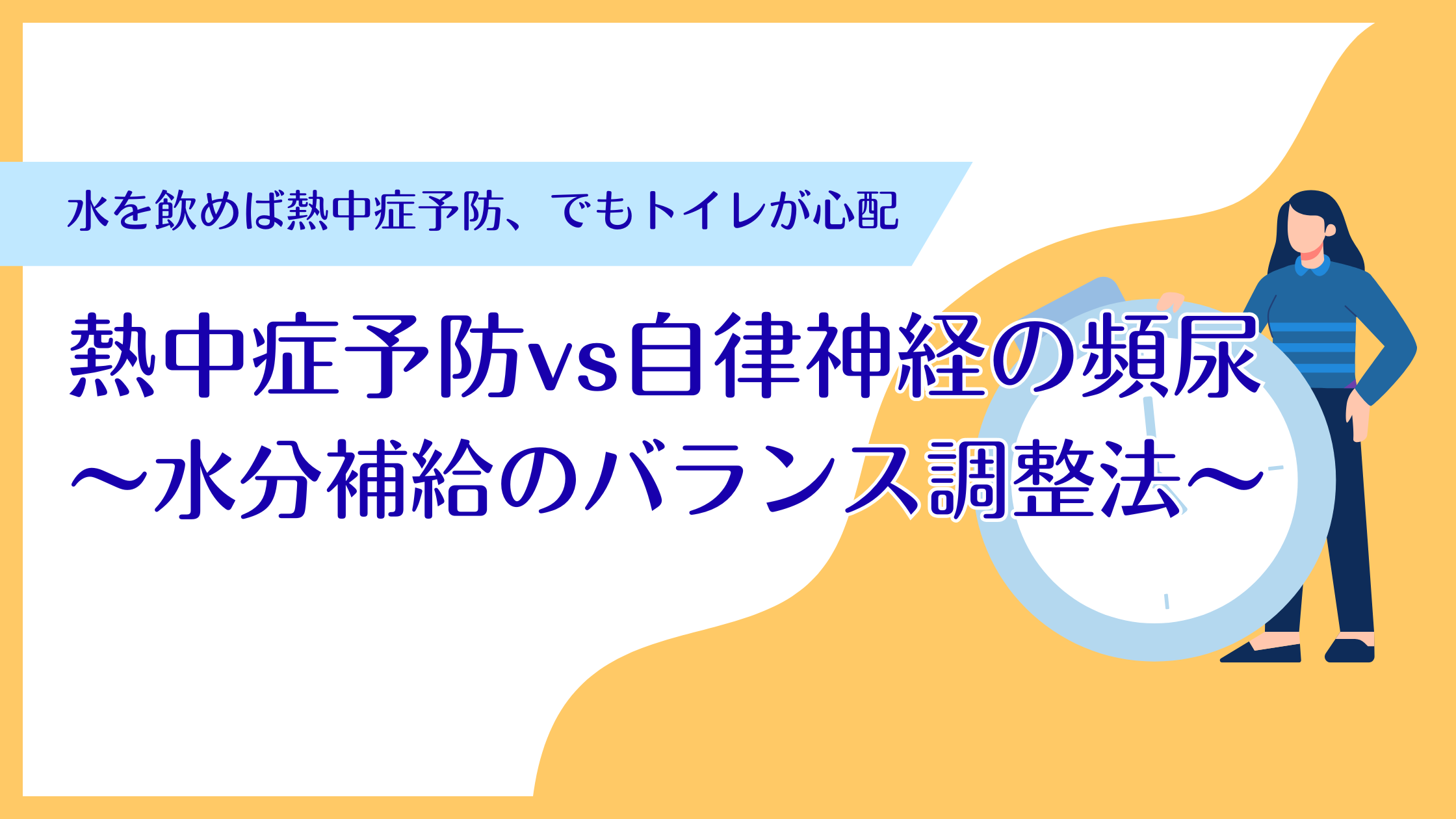令和時代の心身ケア|変化に適応するためのセルフケア術

平成から令和へ:春の空気と心と体の向き合い方を考えてみよう
昭和生まれ、集まれ~!
「困難な日も、こんなんな日も」の管理人、こんなんさんです。
よく、友人と話すのですが、子どもの頃の春と今の春って違いすぎません?
「桜が咲く頃はまだ肌寒くて、4月に入ってから徐々に暖かくなる」
そんな春の訪れ方が、いつの間にか変わりましたよね。
今回は、平成の春と令和の春の違い、その変化がわたしたち更年期世代の体調やメンタルにどう影響しているのか、どう向き合っていけばいいのかについて考えてみたいと思います。
記憶の中の春と現実の春のギャップ
いったい、何が変わったの?
子ども時代、春といえばどんな服装を思い浮かべますか?
わたしの記憶では、卒業式や入学式には必ずコートを着ていました。春の訪れはゆっくりで、桜の花が散った後にようやく暖かくなり始める…そんな穏やかな季節のうつろいがありました。そう、うつろいという言葉がしっくりきたんです。
ところが最近の春は、抒情的な思いから離れたところにいます。いつになったら衣替えをすべきかさっぱり。
気象庁のデータによると、この30年ほどで春の気温は平均で約1.5℃上昇しているそうです。数字にするとわずかですが、わたしの体感としては5℃は違うように感じています。
令和時代の「寒暖差春」の特徴
令和の春は:
- 急激な気温変化:一日の中での寒暖差が大きい
- 季節進行の不規則性:「三寒四温」ではなく「一暑一寒」のような不規則さ
- 花粉の飛散時期と強度の変化:スギ花粉の飛散が早まり、量も増加
- 春の嵐や集中豪雨の増加:安定しないお天気
- 桜の開花時期の前倒し:東京では平均で約10日早くなっているという報告も
わたしたちの体は、長年慣れ親しんだ季節のリズムに合わせて動くよう設計されているため、この急激な変化についていくのは正直むずかしい。
春の気候変動が更年期世代に与える影響
気温の乱高下と自律神経の混乱
更年期世代のわたしたちにとって、この気温の乱高下は特に厄介です。すでにホルモンバランスの変化で自律神経が不安定になっているところに、外気温の急激な変化がさらに負担をかけてるんですもの。
ホットフラッシュやのぼせを経験している人にとって、気温の急上昇は症状を悪化させることも。逆に、急に冷え込む日には、末端冷え性も悪化。この「暑い・寒い」の繰り返しが、自律神経の調整機能をさらに疲労困憊にさせているのです。
花粉症の変化と免疫系への影響
平成と比べて、花粉の飛散量は増加傾向にあります。とくに都市部では、気温上昇と二酸化炭素濃度の上昇により、植物の生育環境が変化し、より多くの花粉を生産するようになったとも言われています。今は、黄砂もありますよね。昔は、歌でしか聞かなかった黄砂が身近に。
更年期に入ると免疫系のバランスも変化するため、これまで軽度だった花粉症が突然重症化したり、初めて花粉症を発症したりすることも少なくありません。
わたし自身、40代に入ってから花粉症の症状が急に重くなりました。「昔はこんなにひどくなかったのに…」と思いながらティッシュを使い続ける日々。これも更年期と気候変動のダブルパンチなのかもしれません。今は絶賛、舌下免疫治療中です。
春の不安定な気圧と心身への影響
春は気圧の変動も大きい季節。低気圧が近づくと、気圧の低下に伴って体内の水分バランスや血流にも変化が生じます。これが頭痛やめまい、関節痛の原因になることも。
更年期特有の症状と、気圧変動による不調が重なると、「なんだか体がだるい」「頭が重い」「めまいがする」といった症状がより強く出ることも。
また、気圧の変動はセロトニンなどの脳内物質にも影響を与えるともいわれており、気分の落ち込みや不安感を強める可能性もあるそうです。うららかな春はどこに行ったのでしょう?
令和の春には新しい対策が必要だ
「気象痛」を理解する
「気象痛」という言葉を聞いたことはありますか?気象の変化(気温、気圧、湿度など)によって引き起こされる頭痛や関節痛、自律神経症状などを総称した言葉です。
更年期の症状だと思っていたものが、実は気象痛だったり、またはその両方が重なっていたりすることもあります。
気象痛の主な症状:
- 頭痛・偏頭痛
- 関節痛・筋肉痛
- めまい・ふらつき
- 疲労感・だるさ
- 不眠・睡眠障害
- イライラ・気分の落ち込み
これらの症状は更年期症状と非常に似ているため、「更年期だから仕方ない」と諦めてしまうこともあるかもしれません。でも、気象変化が原因の場合は、それに応じた対策を取ることで症状を和らげられる可能性があります。
「天気予報」を新たな味方に
昔は「明日の予定を決めるため」に天気予報を見ていましたが、今は「明日の体調管理のため」に天気予報をチェックする習慣をつけるのもいいかもしれません。
- 急な気温変化が予想される日は、重ね着で調節できる服装を準備
- 低気圧が接近する前日は、早めに休息を取り、水分補給を心がける
- 花粉の飛散量が多い日は、外出時の対策を徹底する
わたしは天気予報アプリをこまめに見るようにしています。気圧が大きく下がる日の前日には、なるべく予定を入れないようにしたり、軽めの運動で血行を良くしておくなどの工夫をしています。生きるってサバイバルですね。
「気候変動×更年期」対策キット
わたしが実践している、令和の春を乗り切るための「対策キット」をご紹介したいと思います:
《バッグの中の必需品》
- 折りたたみ傘(突然の雨対策)
- 薄手のストールやカーディガン(温度調節用)
- 保湿リップクリーム(乾燥対策)
- 花粉対策メガネとマスク
- モバイルバッテリー(災害時や体調不良時の備え)
《朝のルーティン》
- 起床後すぐに天気予報と気圧予報をチェック(前日夜にもチェック)
- その日の気象条件に合わせた服装を選ぶ
- 花粉の多い日は出かける前に対策(点鼻薬を行うなど)を行う
- 低気圧が近づく日は、頭痛薬を持ち歩く
《体調管理の工夫》
- 気圧の変化に備えて、こまめな水分補給を心がける
- 気温の変化が激しい日は、無理な予定は入れない
- 春特有の「眠気」に抗わず、短い昼寝を取り入れる
- 花粉症と更年期症状が重なる時期は、婦人科や耳鼻科と連携して薬の調整を行う
春特有のメンタルケア
「春うつ」と更年期うつの関係
「春うつ」という言葉を聞いたことはありますか?春になると気分が落ち込んだり、疲れやすくなったりする症状で、季節性情動障害の一種ともいわれています。
これが更年期うつと重なると、より複雑な心の状態になることがあるそうです。わたしたちって忙しいですね。
春うつの主な症状:
- 春先の強い倦怠感
- 集中力の低下
- 眠気の増加
- 気分の落ち込み
- 意欲の減退
これらの症状は、環境の変化(新生活や新年度のスタート)によるストレスや、日照時間の急激な変化、体内時計の乱れなどが原因と考えられています。
更年期世代のわたしたちは、ホルモンバランスの変化も加わるため、より慎重なメンタルケアが必要だとおもっています。
「無理しない」を意識的に選ぶ
令和の春は、気候の変化や社会環境の変化が激しく、体と心への負担が大きいもの。だからこそ、「無理をしない」という選択を意識的に行うことが大切です。
新年度が始まる4月は、「頑張らなきゃ」というプレッシャーを感じやすい時期。でも、更年期真っ只中のわたしたちは、昔と同じペースで頑張ることが難しいかもしれません。
そんなとき、わたしが実践しているのは「今日のMIT(Most Important Task)」を1つだけ決めること。「今日はこれだけはやる」と決めたタスクを達成できれば、その日は成功と考えるのです。
すべてを完璧にこなそうとするより、優先順位をつけて「できることから少しずつ」進む方が、心身への負担が少なく、結果的に長く続けられると実感しています。
「春の疲れ」と「更年期の疲れ」を区別する
春は誰でも疲れを感じやすい季節。環境の変化や気温の変動に体が適応するために、エネルギーを使っているからです。
でも、その疲れが「春特有の一時的なもの」なのか、「更年期に関連する継続的なもの」なのかを区別することも大切です。
《春特有の一時的な疲れの特徴》
- 午後になると回復する
- 週末の休息で改善する
- 環境の変化(新しい環境に慣れる)とともに徐々に改善する
《更年期関連の継続的な疲れの特徴》
- 十分な休息を取っても改善しない
- 数週間〜数か月継続する
- 他の更年期症状(ホットフラッシュ、不眠など)を伴うことが多い
この違いを意識することで、「春だから疲れるのは当たり前」と片付けず、必要に応じて婦人科や心療内科などの専門家に相談するきっかけにもなります。
令和の春の「新しい習慣」
季節の変化に合わせた食事の工夫
昔ながらの「春は苦味」という知恵は、実は理にかなってるんです。年齢を重ねるほど、苦味にうまさを感じるわたしたち、春に摂取すべき栄養素と食材を意識してみましょう:
- ビタミンB群:春の疲れに効果的(卵、乳製品、豆類、緑黄色野菜)
- ビタミンE:自律神経のバランスを整える(ナッツ類、植物油、うなぎ)
- マグネシウム:気圧変化による頭痛の予防に(海藻類、ナッツ類、豆類)
- 春の苦味野菜:肝機能を高める(ふきのとう、たらの芽、セリなど)
わたしの場合、更年期症状と春の疲れが重なると、特に「冷え」を感じやすくなります。そんなとき、温かいスープや具だくさんのみそ汁を意識的に取り入れるようにしています。
また、春は自律神経が乱れやすいので、カフェインやアルコールの摂取にも注意。夕方以降のカフェイン摂取は控え、睡眠の質を高める工夫も大切です。花見酒楽しいんですけどね。
春の光を味方につける
春の日差しには、メンタルヘルスを整える効果があるそう。朝の光を積極的に取り入れて、体内時計を整えていきましょう。
《朝の光を取り入れる工夫》
- 起床後すぐにカーテンを開ける
- 朝食は窓際で太陽の光を浴びながら食べる
- 可能なら朝の短い散歩を日課にする
ただし、花粉症がある方は外出時の対策を忘れずに。室内でも窓際で過ごす時間を増やすだけでも効果があるそうですよ。
「新しい体温調節習慣」を身につける
令和の春の特徴である「急激な気温変化」に対応するため、新たな体温調節習慣を取り入れてみましょう:
- 重ね着の工夫:薄手のアイテムを複数重ねる「ミルフィーユ戦法」で調整しやすく
- 「首元」の温度管理:首の後ろを温めることで全身の血行が良くなる
- 「温活」と「冷活」の使い分け:気温や体調に合わせて、温めたり冷やしたりする習慣を身につける
わたしがよく実践しているのは、「手首と足首の温度調節」。体温調節が苦手な更年期世代には、手首と足首の温度を調整することで、全身の温度バランスを取りやすくなるそうです。
暑いと感じたら手首を冷たい水で冷やし、寒いと感じたら足首を温める。このシンプルな方法が、ホットフラッシュと冷えの両方に悩まされる更年期世代の強い味方になります。
懐かしき平成の春の良さを「新しい形」で取り入れる
「季節を感じる」時間を意識的に作る
平成の春の良さといえば、「季節の移ろいをゆっくり感じられる」ことでした。気候変動の激しい令和の春でも、意識的に「季節を感じる時間」を作ることで、心と体のバランスを整えられるかもしれません。
- 週末には近所の公園や緑地で春の草花を観察する時間を作る
- 食事に旬の野菜や山菜を取り入れる。お惣菜を買いましょう
- 春の俳句や短歌を読んだり、自分でも詠んでみたりする
スマホやパソコンから離れて、自然に触れる時間を持つことは、自律神経のバランスを整えるのに効果的。わたしの場合、朝の散歩時間はスマホは触らない、意識的にオフラインの時間を作るようにしています。
「ゆるやかな季節の移行期間」を自分で作る
気候は急激に変化していても、わたしたちの体は急激な変化を好みません。だからこそ、意識的に「ゆるやかな季節の移行期間」を自分で作ることも大切かもしれません。
- 衣替えを一気に行わず、2〜3週間かけて少しずつ行う
- 生活リズムの変更も段階的に行う
- 冬から春へのスキンケアも、徐々に切り替える
わたしの場合、春の衣替えは3月下旬〜4月下旬の約1ヶ月間かけて少しずつ行っています。気温の変動に合わせて、冬服と春服を共存させながら、体に負担をかけないよう調整しています。
変わらない春の希望
気候は変化し、わたしたちの体も更年期という大きな変化を経験しています。でも、「新しい始まり」は、平成も令和も変わらないものだと思います。
若い頃と同じ無理はできなくても、経験を積んだからこそできる「賢い」体調管理や季節との向き合い方があるはず。
みなさんは、気候変動と更年期のダブルチャレンジにどのように向き合っていますか?あなたの工夫や体験を、ぜひコメント欄でシェアしてくださいね。
「困難な日も、こんなんな日も」
── こんなんさん
※この記事についてのご感想や、あなた自身の体験談などがありましたら、ぜひコメント欄でシェアしてください。みなさんの声が、次の記事の励みになります。
*「こんなんな日も」とは、「こんなん出た」、「こんなんいるー?」など、関西弁から取りました。ただ、管理人は関西人ではありません…。
⚠️ 免責事項 ⚠️
本記事の内容は、管理人の個人的な体験談であり、医学的なアドバイスや診断に代わるものではありません。更年期の症状や対処法には個人差があります。心配な症状がある場合は、必ず医療機関を受診し、医師にご相談ください。