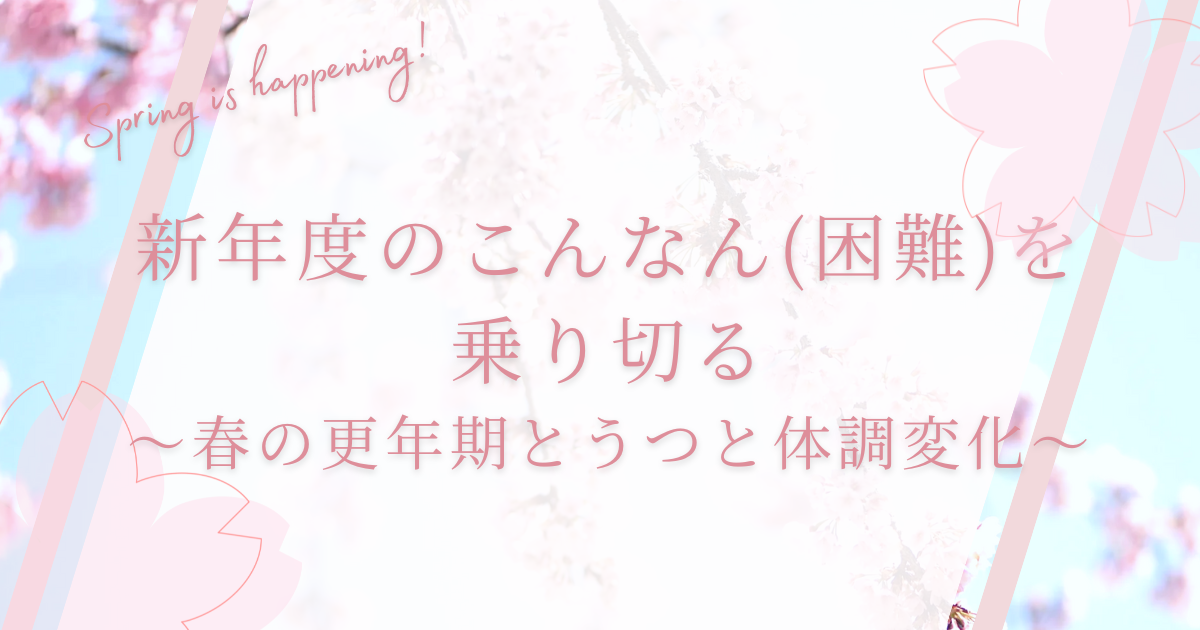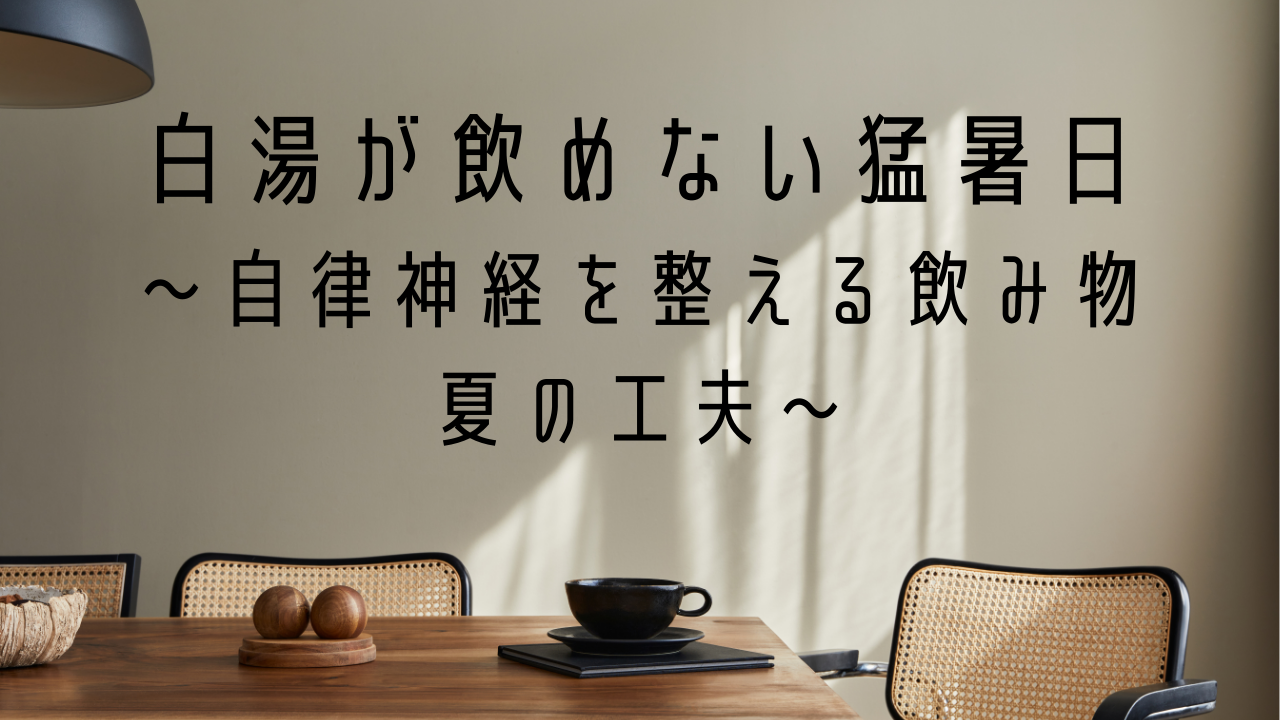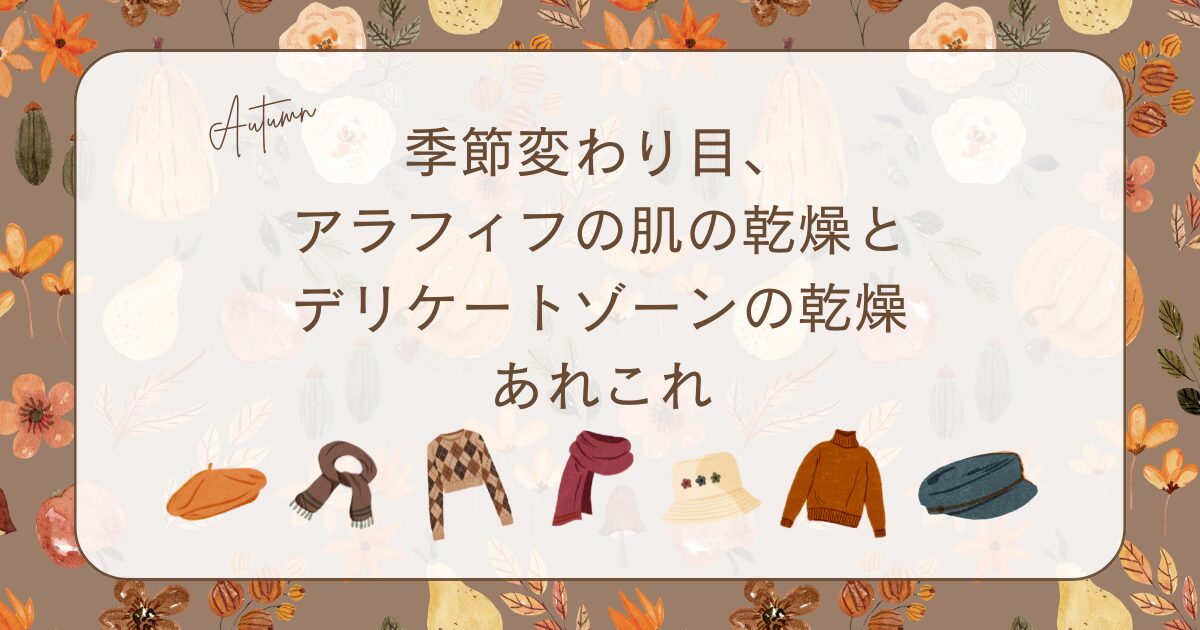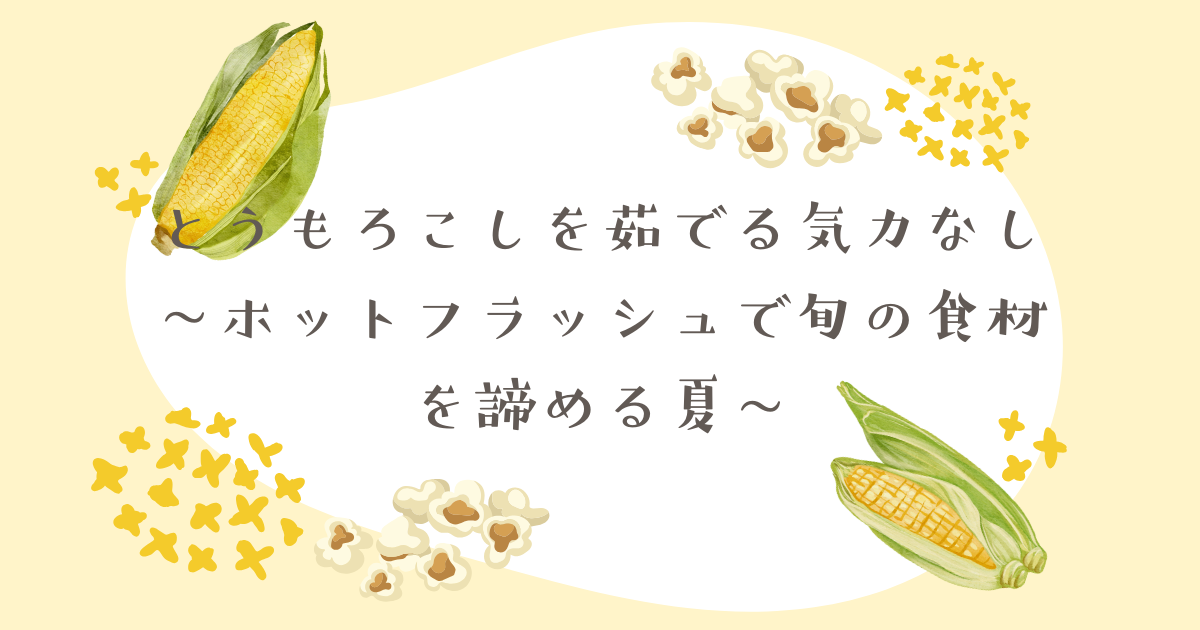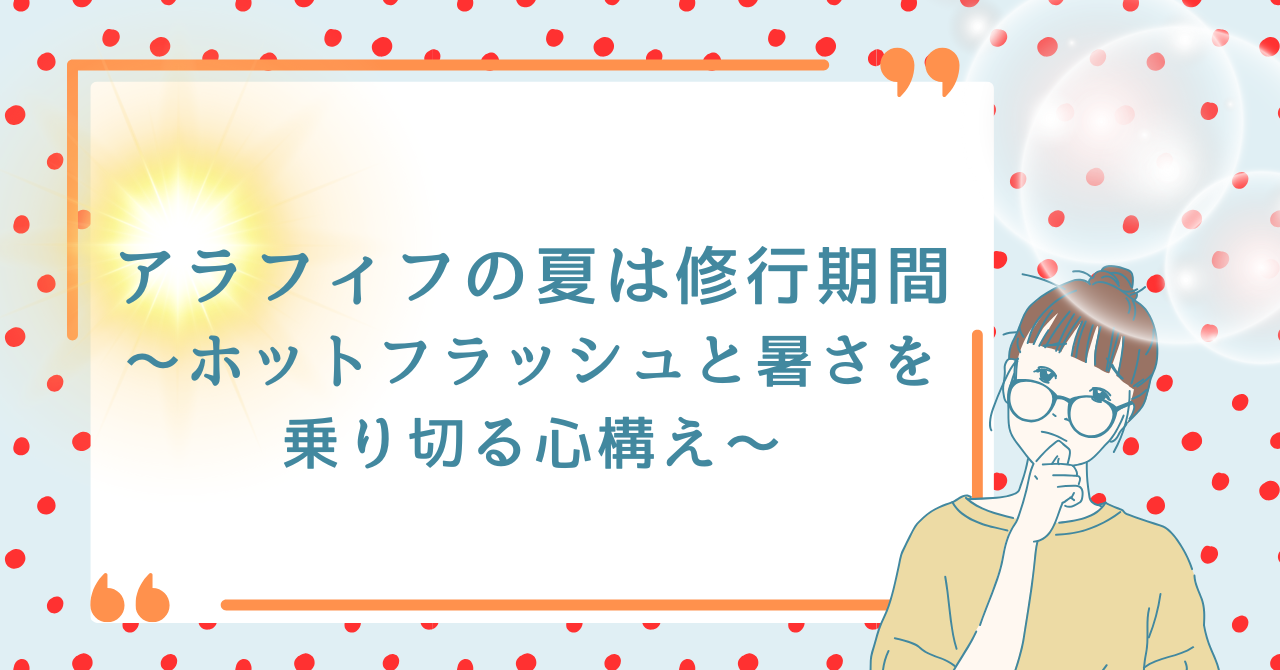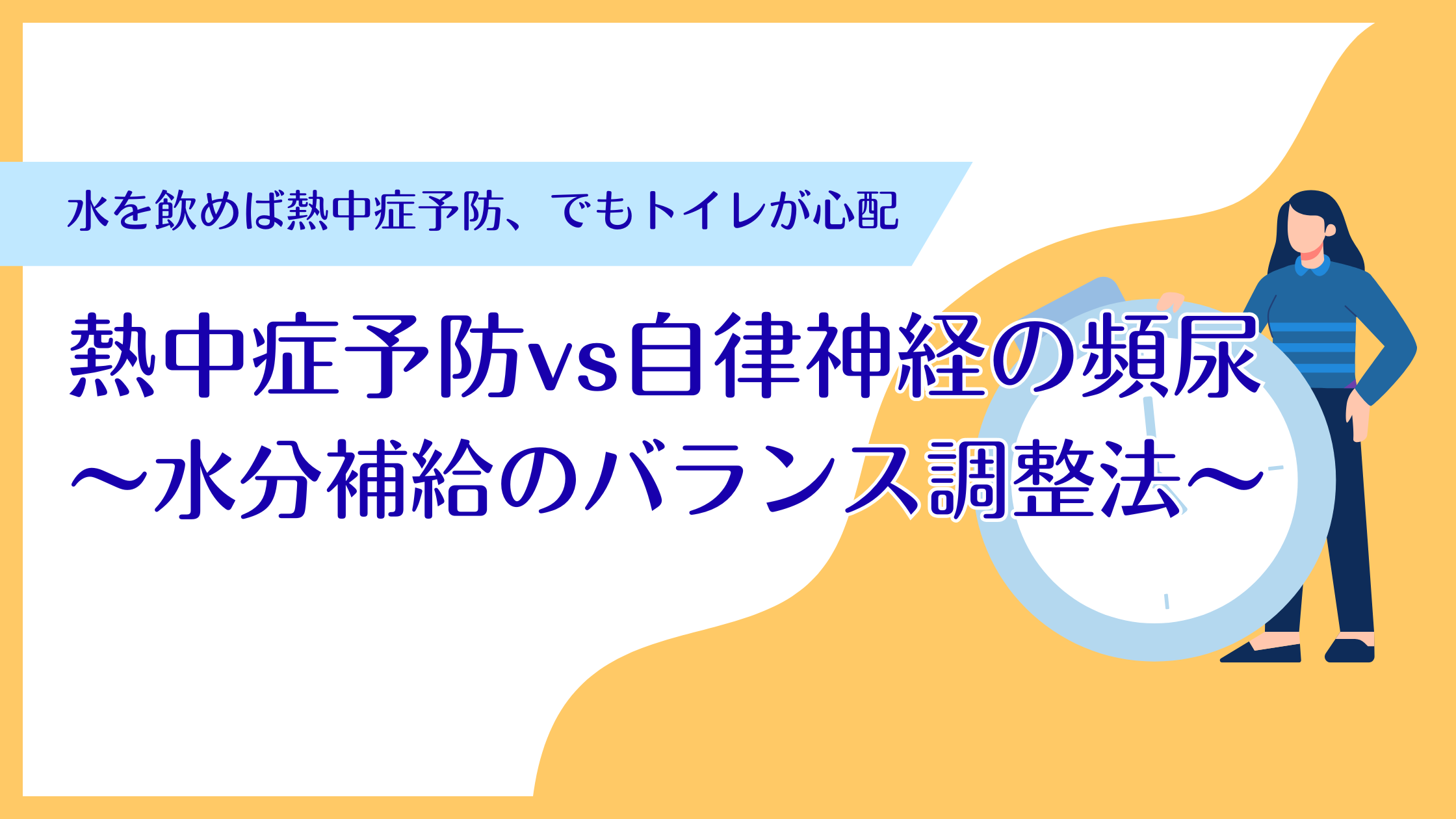「なんとなく調子悪い」の正体は?5月中旬の更年期×5月病が引き起こす体調不良の原因
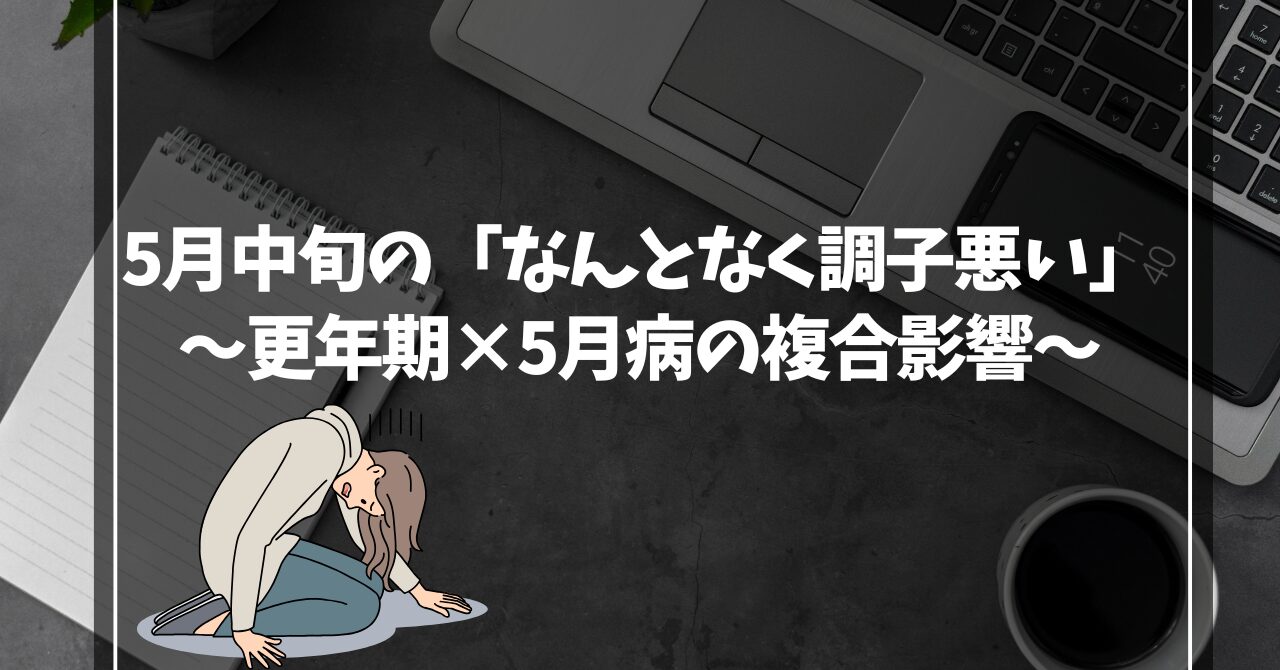
5月中旬の「なんとなく調子悪い」〜更年期×5月病の複合影響〜
病院に行くほどじゃないけど、モヤモヤする日々
「困難な日も、こんなんな日も」の管理人、こんなんです。
皆さん、5月も中旬に入りましたね。ゴールデンウィークが終わり、ちょっと疲れが出てくる時期。「なんだか体がだるい」「集中力が続かない」「イライラする」…そんな感覚、ありませんか?
わたし自身、ここ数日「病院に行くほどではないけど、なんとなく調子が悪い」状態が続いています。熱はないし、痛みもない。でもなんだか「本調子」ではない。更年期×5月の複合作用で起こるこの微妙な不調について、今日はお話ししたいと思います。
5月中旬の「なんとなく調子悪い」の正体
5月病と更年期の意外な関係
5月病というと、新入社員や新入生が環境の変化に適応できず、5月頃に心身の不調を訴える状態を指すことが多いですね。でも実は、わたしたちアラフィフ世代にも「5月病」的な症状が出ることがあるんです。
5月病の主な症状:
- 倦怠感や疲れが取れない感じ
- 集中力の低下
- 気分の落ち込み
- 食欲不振または過食
- 眠れないのに昼間は眠い
これって、更年期症状とかなり重なる部分があるんですよね。わたしの場合、「これって更年期?それとも季節の変わり目?」と区別がつかないことも多いです。答えは「両方」なのかもしれません。
5月の天気と自律神経の乱れ
5月の天気って、すごく変わりやすいですよね。晴れた日があれば、急に雨が降ったり。朝晩は冷えるのに、日中は暑かったり。この気温差や気圧の変化が、自律神経のバランスを崩す原因になっているんです。
特に更年期世代の私たちは、ホルモンバランスの変化で自律神経が不安定になりがち。そこに季節の変わり目が重なると、ダブルパンチのように影響を受けます。
今週は急に暑くなった日もあって、「あれ?もうホットフラッシュ?いや、単に暑いだけ?」と混乱することも。でも、そんな日に限って冷房の効いた部屋に入ると、今度は「寒い!」と感じる…。自律神経よ、どうかがんばって!と心の中で応援している日々です。
「なんとなく不調」と上手に付き合う方法
不調サインの「見える化」で自己理解を深める
「なんとなく調子悪い」という漠然とした感覚は、自分でも説明しづらいものです。わたしが実践しているのは、「不調の見える化」。
不調を見える化する方法:
- 朝起きたときの体調を10点満点で数値化(今日は6点、など)
- 気分の変化や身体感覚をごく簡単にメモ(「午後3時、頭がぼんやり」など)
- 天気や気圧など環境要因もチェック
これを続けると、「あ、この気圧パターンのときは頭が重くなりやすいな」「雨の前日は寝つきが悪くなるな」といった自分の傾向が見えてきます。自分のパターンを知ることで、「これは一時的な不調だから、無理しなくていい」と自分を許せるようになりました。
5月に摂りたい旬の食べ物で免疫力アップ
5月に旬を迎える食材には、この時期の不調を和らげてくれるものがたくさんあります。
5月の旬の食材とその効果:
- 新じゃがいも:カリウムが豊富で、むくみ解消に役立ちます
- グリーンアスパラガス:ビタミンB群が豊富で、疲労回復や自律神経のバランスに
- そら豆:良質なタンパク質とビタミンEが含まれ、女性ホルモンのバランスにも
- いちご:ビタミンCが豊富で、春の疲れを回復させる免疫力アップに
- 新玉ねぎ:辛みが少なく食べやすい上、抗酸化作用で血行促進効果も
わたしのお気に入りは、新玉ねぎのサラダです。細く切って水にさらし、さっと湯通しして冷やしたものに、塩麹とオリーブオイルをかけるだけの簡単レシピ。辛みが少ないので食べやすく、むくみが気になる日の夕食にぴったりです。
むくみ対策の簡単ケア法
5月病と更年期が重なると、なぜかむくみも気になりますよね。気圧の変化やホルモンバランスの乱れが影響しているのかもしれません。
むくみ対策の簡単ケア法:
- 足首回し:デスクワーク中も、10回ずつ時計回り・反時計回りに回す
- ハーブティー:むくみに効果的なルイボスティーやカモミールを日中に
- 半身浴:38〜40度のぬるめのお湯に20分ほど浸かる
- マッサージ:足首から太ももに向かって、優しく上向きにマッサージ
- 夕食の塩分控えめ:特に夕方以降の塩分摂取を控えめにする
わたしが最近ハマっているのは、肌触りのいいガーゼのパジャマに着替えて、小型マッサージ機に足をのせたままぼーっと目を閉じる時間。これが意外と効果的なんです。簡単な瞑想にもなるし、終わった後にはむくみもだいぶ解消されています。何もしてないようでちゃんとケアになっている、そんな「おきらくセルフケア」もたまには必要ですよね。
健康豆知識:更年期×5月病のためのセルフケア
自律神経を整える呼吸法
自律神経の乱れは、更年期×5月病の不調を悪化させる大きな要因。でも、呼吸を整えることで、自律神経のバランスを取り戻す手助けになります。
4-7-8呼吸法:
- 鼻から4秒かけて息を吸い込む
- 7秒間、息を止める
- 8秒かけて、口からゆっくりと息を吐き出す
- これを4回繰り返す
この呼吸法、いつでもどこでもできるのがいいところ。わたしはイライラしたとき、会議前の緊張したとき、夜寝つけないときなど、様々なシーンで実践しています。特に朝、目覚めてすぐにベッドで行うと、一日の始まりが違う気がします。
昼寝の効果的な取り方
5月病と更年期が重なると、昼間の眠気に悩まされることも。そんなときの昼寝は、取り方次第で味方にも敵にもなります。
効果的な昼寝のポイント:
- 時間は15〜20分を目安に:長すぎると逆に疲れる
- タイミングは午後1時〜3時の間:この時間帯は自然と眠くなりやすい
- 環境を整える:少し暗くして、静かな場所で
- 事前にカフェインを避ける:昼食後のコーヒーは控えめに
- 目覚まし機能を活用:うっかり寝過ごさないよう設定を
在宅勤務の日、わたしが実践しているのは「ランチ後の10分パワーナップ」。食後の睡魔に身を任せつつも、目覚ましをセットして短時間で切り上げる。これだけでも午後の頭の回転が全然違います。
「病院に行くほどじゃない」をどう判断する?
自分の「平常値」を知ることの大切さ
「これって病院に行くべき?」という判断が難しいときは多いですよね。特に「なんとなく調子悪い」という漠然とした状態だと、余計に迷います。
大切なのは、自分の「平常値」をしっかり把握しておくこと。平熱はどのくらいか、普段の血圧や脈拍はどのくらいか、生理周期はどうか…。こうした基礎データを持っていると、「いつもと違う」変化にも気づきやすくなります。
わたしの場合、スマホアプリで基礎体温や体調、症状をざっくり記録。これが医師に相談するときの重要な資料になっています。特に更年期は「何となく」の症状が多いので、こうした記録があると説明しやすいんです。
「様子見」と「受診」の境界線
では、具体的にどんな状態になったら「様子見」ではなく「受診」を考えるべきでしょうか?
受診を検討したほうがよいサイン:
- 睡眠障害が2週間以上続く:眠れない日が続くと、心身への負担が大きい
- 気分の落ち込みが日常生活に支障をきたす:家事や仕事に集中できないレベル
- 身体症状が特定の部位に集中:ただの疲れではなく、特定の部位の痛みやしびれ
- 基礎体温が平常値から大きく外れる:37.5度以上の熱が続くなど
- 周囲から「顔色が悪い」と言われる:自覚症状がなくても、客観的に変化がある場合
わたしの場合、「仕事への支障度」をひとつの基準にしています。「なんとなく調子悪いけど仕事はできる」なら様子見、「集中できないレベル」なら受診を検討。また、不調が1週間以上続くようなら、かかりつけ医に電話だけでも相談するようにしています。
おわりに:「なんとなく」を大切にする
5月の「なんとなく調子悪い」。病院に行くほどではないけれど、確かに感じる不調。これは、わたしたちの体が発するサインなのかもしれません。「無理しすぎていませんか?」「休む時間を取りましたか?」と、体が静かに問いかけているように感じます。
更年期とこの5月病が重なる時期は、特に自分を大切にする時間が必要です。「なんとなく」という感覚を無視せず、小さな変化にも耳を傾けてみましょう。
わたしは先日、雨上がりの夕方に綺麗な虹を見かけました。天気が変わりやすい5月だからこそ見られる光景。「天気も、わたしの体調も、気分も、変化して当然なんだ」と思いました。完璧でなくていい。調子のいい日も悪い日も、それがわたしたちの自然な姿なのだと。
みなさんは、5月のこの時期、どんな「なんとなく」と付き合っていますか?良かったら、コメント欄でシェアしてくださいね。
「困難な日も、こんなんな日も」
── こんなん
※この記事についてのご感想や、あなた自身の体験談などがありましたら、ぜひコメント欄でシェアしてください。みなさんの声が、次の記事の励みになります。
*「こんなんな日も」とは、「こんなん出た」、「こんなんいるー?」など、関西弁から取りました。ただ、管理人は関西人ではありません…。
⚠️ 免責事項 ⚠️
本記事の内容は、管理人の個人的な体験談であり、医学的なアドバイスや診断に代わるものではありません。更年期の症状や対処法には個人差があります。心配な症状がある場合は、必ず医療機関を受診し、医師にご相談ください。