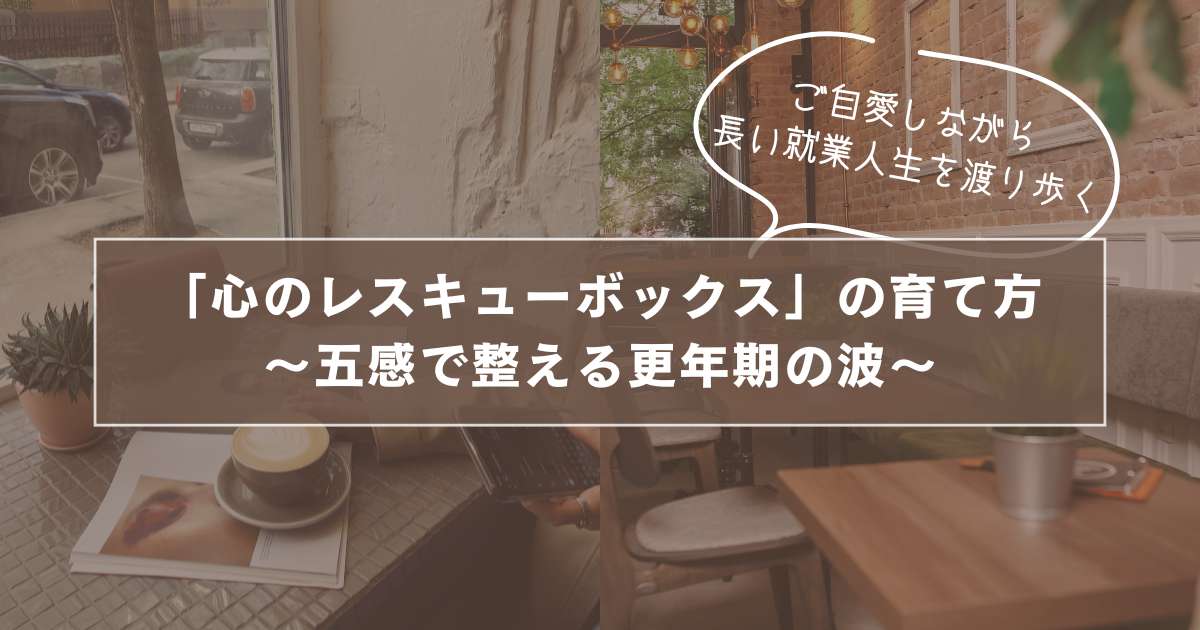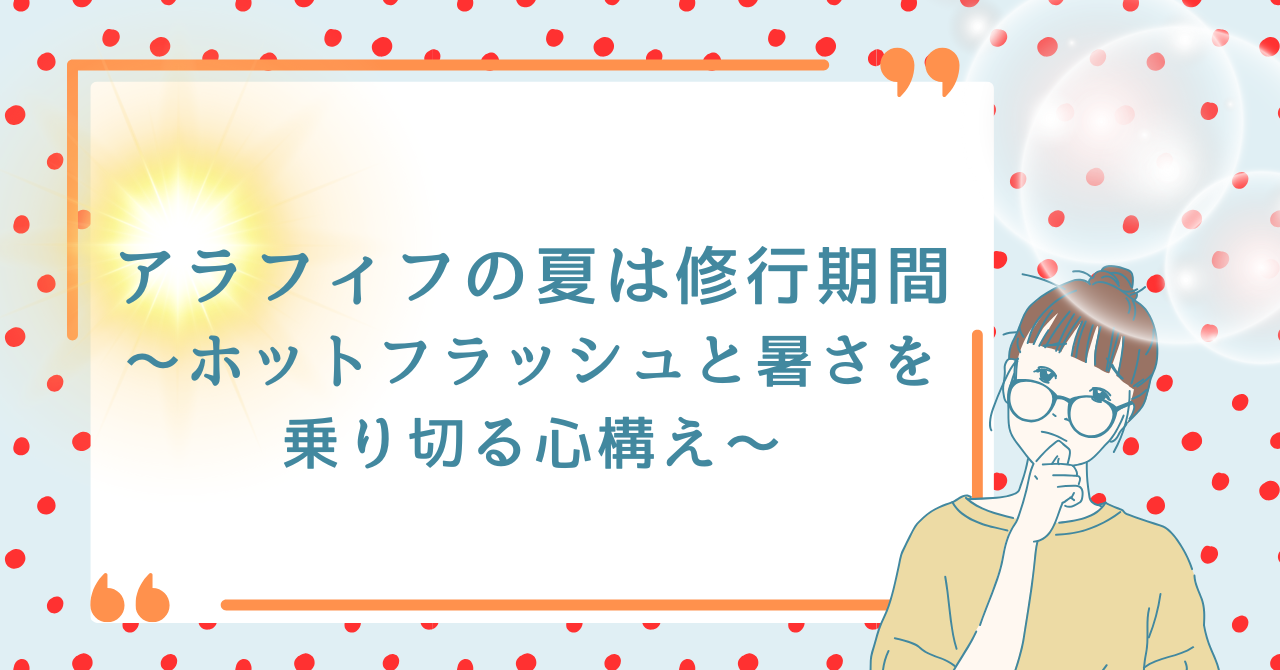GW疲れをスッキリリセット!5月後半を元気に乗り切る体調管理術とセルフケア方法
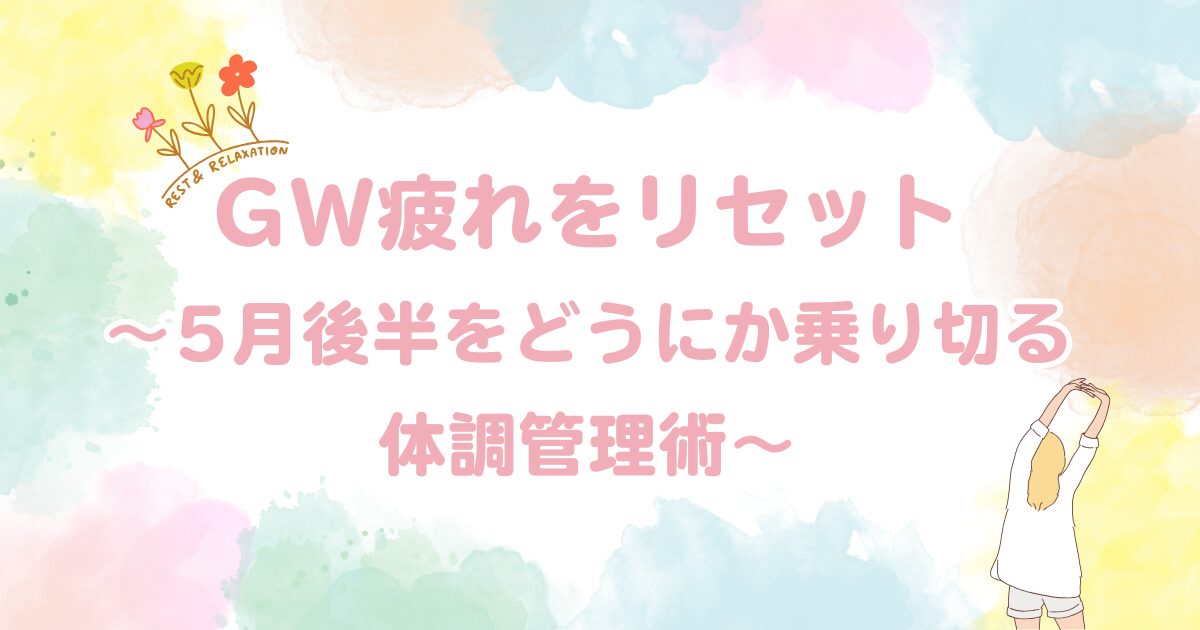
GW疲れをリセット~5月後半をどうにか乗り切る体調管理術~
GW明けの疲労回復と5月後半の体調管理に悩む更年期世代へ。休み明けの不調の正体と対策、エネルギー配分を考えた無理のない予定管理、職場での自己開示のコツまで。40〜50代の働く女性が心身の不調と向き合いながら、自分のペースを保つための実践的アドバイス。
〜更年期×うつ世代が実践する連休明けのリカバリー方法と無理のない予定管理のコツ〜
「困難な日も、こんなんな日も」の管理人、こんなんさんです。
GW明け、みなさまいかがお過ごしでしょうか?旅行に行かれた方、家族団らんを楽しまれた方、家の片付けに奮闘された方…さまざまだと思います。そして今、多くの方が感じているであろう「連休疲れ」。
「休みなのに、なぜかもっと疲れた…」 「カレンダーを見たら5月後半の予定がびっしり…」 「体力も気力も回復しないまま、また仕事が始まった…」
わたし自身、実家に帰省して母との語らい帰ってきたら「なぜか体が重い」「なんとなく気分が落ち込む」という状態に。日常のリズムが崩れると、特に更年期真っ只中のわたしたちは影響を受けやすいんですよね。
今日は、GWで疲れた心と体を立て直し、5月後半を元気に乗り切る方法について、お話ししたいと思います。一緒に「心と体のリカバリー作戦」を考えていきましょう!
GW疲れの正体~なぜ休みなのに疲れるの?~
「リズムの乱れ」が更年期の体に響く
連休明けの疲労感には、いくつかの理由があります:
- 生活リズムの変化:起床・就寝時間の変化、食事時間の不規則化(体内時計が「ん?何が起きてるの?」状態)
- 活動内容の変化:普段と違う活動(旅行、家事、家族サービスなど)による疲労の蓄積
- 環境の変化:旅先や実家など、いつもと違う環境での睡眠の質の低下
- 過剰な予定:「せっかくの休みだから」と詰め込みすぎた予定による心身の疲労
更年期世代のわたしたちは、このような変化に特に敏感です。ホルモンバランスが不安定な時期に生活リズムが乱れると、自律神経のバランスも崩れやすくなります。
日本睡眠学会の調査によると、休日と平日で2時間以上の睡眠時間のずれがある「ソーシャル・ジェットラグ」は、疲労感や集中力低下の原因になることが報告されています。
わたしの場合、実家では朝寝坊して、夜は母との語らいで遅くまで起きて…。そして帰宅後、急に元の生活リズムに戻ろうとしたら、体がついていかず。「ホットフラッシュ」の頻度も増えたように感じます。まるで体が「急に元に戻さないでよ!」と抗議しているかのよう。吹き出物も出てきました。
「社会的疲労」と「タスク復帰ストレス」
ふだんと違う社会的交流も、思いのほか疲れの原因になります:
- ふだん会わない家族や親戚との時間:楽しいけれど、気を遣う場面も(「おばちゃんって言われたショック」も)
- 「何してたの?」質問への対応:更年期やうつの症状は見えないため、理解されにくいストレス
- SNSでの他者の「楽しい連休」との比較:「みんな充実してるのに自分は…」という気持ち
そして連休が明けると、積み上がったメールや仕事のタスクに直面するストレスも。「休み前の自分」がセットした予定やタスクに、「休み明けの疲れた自分」が対応しなければならないというギャップ。
国立精神・神経医療研究センターの調査では、連休明けに「ブルーマンデー症候群」と呼ばれる気分の落ち込みを経験する人が増加することが示されています。
わたしは帰宅後、仕事メールを見て「うわぁ」と声が漏れました。休み前の自分が「連休明けにやろう」と思っていたタスクが、今の自分には「登山くらいのエネルギーが必要」に感じるんです。
心とからだのリカバリー作戦~5月後半に向けて~
生活リズムを少しずつ整える
まずは乱れた生活リズムを取り戻すことから始めましょう。ただし、急激な変化はかえって負担になるので、緩やかに調整を:
- 起床時間を固定する:休日も平日も、起きる時間はなるべく一定に(±30分程度)
- 朝日を浴びる習慣:起きたらカーテンを開けて、15分程度自然光を浴びる
- 夜の準備を早める:就寝1時間前にはスマホやPCから離れ、リラックスモードに
国立睡眠財団(National Sleep Foundation)によると、朝の光を浴びることで体内時計がリセットされ、夜の睡眠の質も向上するとされています。
わたしのやり方は「朝日セレモニー」です。休み中に崩れがちな生活リズムを取り戻すため、起きたら必ずカーテンを開けて、できれば窓も開けて深呼吸。「今日も始まるよ」と体に教えてあげるんです。
また、連休中に遅くなりがちな夕食の時間も、徐々に早めていくのがコツ。わたしは「19時夕食ルール」を作って、休み明けの生活リズム調整に役立てています。
「エネルギー回復」のための食事と水分
GW疲れからの回復には、栄養バランスも重要です:
- タンパク質をしっかり摂る:疲労回復や脳機能の維持に必要(卵、魚、鶏肉、豆腐など)
- 鉄分の意識的な摂取:疲労感の原因になりやすい鉄不足に注意(ひじき、レバー、ほうれん草など)
- ビタミンB群の多い食品:エネルギー代謝を助けるビタミン(豚肉、玄米、納豆など)
- 水分補給の習慣化:デスクに水筒を置き、こまめに水分補給(脱水は疲労感を悪化)
日本栄養士会によると、40〜50代女性は鉄分や良質なタンパク質が不足しがちで、疲労感や集中力低下の原因になることが指摘されています。
わたしの「連休明け回復食」は、「卵かけご飯+ひじきの煮物」。シンプルだけど、たんぱく質と鉄分が一緒に摂れる組み合わせです。ちょっと忙しいときでも5分で作れるので、疲れた日の夕食にぴったり。
食事の準備をする元気もないときは、タンパク質と野菜が入ったコンビニのお惣菜と卵1個を追加するという「最小限栄養確保作戦」も時々実行します。
「ブレインフォグ」対策と仕事の再開方法
GW明けは特に「頭がボーッとする」という症状が出やすいもの。更年期×うつ×連休疲れの「三重苦」でブレインフォグが悪化しがちです。
仕事復帰時のブレインフォグ対策:
- タスクの「見える化」:やるべきことをすべて書き出し、優先順位をつける
- 「小さく始める」原則:最初の1〜2日は難しい判断や大きな決断を避ける
- 25分集中×5分休憩:ポモドーロテクニックで集中力を管理
- 水分と深呼吸:デスクに温かい飲み物(カフェインレスがベター)を置き、こまめに休憩
日本産業衛生学会の研究では、短時間の集中と休憩を繰り返す「ポモドーロテクニック」が、特に更年期世代の女性の認知機能維持に効果的だと報告されています。
わたしの「仕事復帰の儀式」は、「連休前の自分へのご褒美タイム」から始めます。まず、机の上を整理して、可愛いポストイットでその日のToDoリストを作成。「これだけやればOK」と自分との約束を明確にします。それと同時に、「予定を入れない時間」も確保。真っ白な時間がないと、すぐに疲れてしまうんです。
5月後半の「無理しない予定の組み方」~疲れない工夫~
「エネルギー配分」を意識したスケジューリング
GW明けの5月後半、どうしても予定が詰まりがちです。エネルギー消費を意識したスケジュール管理が必要です:
- 「エネルギー消費量」でタスクを分類:対人業務、創造的業務、ルーティン作業など
- 一日の中でエネルギー消費の「山」を1〜2個に:大きな会議や重要な判断は同日に詰め込まない
- 回復の時間を意識的に設ける:昼休みはなるべく一人で過ごすなど
- 週の中でも「軽い日」を作る:金曜日は新しいことを始めないなど
米国心理学会(APA)の研究によると、「認知的負荷」の高いタスクを一日に詰め込みすぎると、意思決定能力が低下することが示されています。これは「決断疲れ」とも呼ばれる現象です。
わたしは手帳に「エネルギーマーク」を付けています。「⚡⚡⚡」は高消費タスク(重要会議、プレゼンなど)、「⚡⚡」は中程度(集中作業、長時間の対応など)、「⚡」は低消費タスク(ルーティン作業など)。この目安で、一日の「⚡」の数が5個を超えないようにスケジュールを調整しています。
「NO」と言える勇気と代替案の提示
更年期とうつの両方を抱えるわたしたちには、全てのリクエストに「YES」と言い続ける余裕はありません。適切に「NO」と言うスキルも大切です:
- 「いついつならできます」とキッパリ:曖昧な返事でかえって相手に迷惑をかけることも
- 代替案を提示する:「その代わりに〇〇ならできます」と建設的な対応
- 期待値のすり合わせ:「このクオリティでよければ」と予め伝えておく
女性の健康とワークライフバランスに関する研究では、とくに40代以降の女性が「自己主張」と「バウンダリー設定」のスキルを身につけることが、キャリア継続の鍵になると報告されています。
わたし自身、以前は「NOと言えない症候群」でしたが、無理して引き受けて結局体調を崩し、相手にも迷惑をかけた経験から学びました。今は「即答せず、一晩考える」ルールを自分に課しています。その間に本当に引き受けられるか、自分の体調とスケジュールと相談するんです。
「見えない体調不良」を周囲に伝える工夫
更年期やうつの症状は、外からは見えにくいもの。でも適切に伝えることで、周囲の理解や配慮を得ることができます:
- 具体的な影響を伝える:「集中できる時間が15分程度」など具体的に
- 数値化する:「今日の体調は10点満点で6点」など
- 必要な配慮を明確に:「会議は午前中が助かります」など具体的に
- 感謝も忘れずに:配慮してくれた相手への感謝を伝える
日本産業カウンセラー協会の調査によると、見えない症状を抱える従業員が職場で適切に自己開示することで、必要な配慮を得られるケースが増えていることが報告されています。
わたしの場合、上司には「更年期障害とうつの治療中」と伝えた上で、「朝一の会議は集中力があるので助かる」「午後3時以降は体調が落ちやすい」など、具体的な傾向を話しています。すると「じゃあこの重要な話は午前中にしよう」と配慮してもらえることも。すべての職場でこうした対応が可能とは限りませんが、少しずつ理解者を増やしていくことが大切です。
マイペースで乗り切る「5月の体調管理チェックリスト」
自分の体調を客観的に確認するチェックリストを作りました。これをもとに、自分の状態をモニタリングして、無理のない5月後半を過ごしましょう。
毎日チェックしたい項目:
- 睡眠の質:「よく眠れた」〜「全く眠れなかった」(5段階)
- 朝の目覚め:「すっきり」〜「全く起きられない」(5段階)
- ホルモン症状:ホットフラッシュ、頭痛、めまいなどの頻度
- 集中力の持続時間:集中できる時間の長さ(分単位)
- イライラ度:「穏やか」〜「非常にイライラ」(5段階)
- 身体の痛み:部位と強さ
- 水分摂取量:目安として1.5L〜2L/日
日本女性医学学会によると、更年期症状は日々変動することが多く、定期的な記録をつけることで、症状のパターンや対策の効果が見えやすくなると指摘しています。
このチェックリストを1週間続けると、自分の「調子が良い日」と「悪い日」のパターンが見えてきます。例えば「火曜日の午後は毎週調子が悪い」「天気の変化で頭痛が増える」といった傾向が分かれば、予定の調整もしやすくなります。
わたしはスマホのメモ機能に簡単なチェック項目を作って、毎朝と毎晩、30秒程度で記録しています。「体調が優れない」と感じる日が3日続いたら、予定を見直したり、休息を増やしたりする目安にしています。
おわりに:「自分ペース」で5月後半を乗り切る
GW疲れからの回復と5月後半の乗り切り方、いかがでしたか?
わたしたち更年期世代+うつは、「無理をして頑張る」時代は終わったのかもしれません。むしろ「自分のペースを守る」「必要な休息をとる」ことが、長期的に見て仕事のパフォーマンスも人間関係も良好に保つ秘訣なのかもしれません。
女性の健康推進に取り組む一般社団法人「女性の健康とエンパワメント」の調査によると、40代〜50代女性の約70%が「自分の体調に合わせた働き方」を希望している一方で、実際にできていると感じているのは30%程度に留まっています。
5月後半、すべての予定をこなそうとするのではなく、「優先順位」と「自分の体調」のバランスを大切に。「今日はここまで」と決めて、無理なく過ごしていきましょう。
「ならぬものはならぬ」。わたしの祖母がよく言っていた言葉です。すべてを完璧にこなそうとするのではなく、「できることとできないことを見極める」知恵。更年期とうつを抱えるわたしたちには、特に大切な心構えかもしれません。
みなさんは、GW明けの体調管理、どんな工夫をされていますか?良かったら、コメント欄でシェアしてくださいね。一人ひとりの小さな知恵が、誰かの大きな支えになるかもしれません。
「困難な日も、こんなんな日も」
── こんなんさん
参考資料・外部リンク
- 日本睡眠学会「睡眠障害対処12の指針」: https://www.jssr.jp/data/pdf/suiminyobou.pdf
- 国立精神・神経医療研究センター「ストレスとメンタルヘルス」: https://www.ncnp.go.jp/hospital/patient/stress.html
- Sleep Foundation「How Sunlight Affects Your Sleep」: https://www.sleepfoundation.org/circadian-rhythm/how-sunlight-affects-your-sleep
- 日本栄養士会「中年期女性の健康と栄養」: https://www.dietitian.or.jp/data/column/
- 日本産業衛生学会「働く女性の健康管理」: https://www.sanei.or.jp/
- American Psychological Association「Decision Fatigue」: https://www.apa.org/topics/stress/decision-fatigue
- 厚生労働省「女性の健康推進室ヘルスケアラボ」: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/sukoyaka/index.html
- 日本産業カウンセラー協会「職場のメンタルヘルス実態調査」: https://www.counselor.or.jp/tabid/223/Default.aspx
- 日本女性医学学会「更年期症状チェックリスト」: https://www.jmwh.jp/pdf/JMWH_healthcheck.pdf
- 女性の健康とエンパワメント「働く女性の健康調査2023」: https://womens-health.jp/
※この記事についてのご感想や、あなた自身の体験談などがありましたら、ぜひコメント欄でシェアしてください。みなさんの声が、次の記事の励みになります。
*「こんなんな日も」とは、「こんなん出た」、「こんなんいるー?」など、関西弁から取りました。ただ、管理人は関西人ではありません…。
⚠️ 免責事項 ⚠️
本記事の内容は、管理人の個人的な体験談であり、医学的なアドバイスや診断に代わるものではありません。更年期の症状や対処法には個人差があります。心配な症状がある場合は、必ず医療機関を受診し、医師にご相談ください。