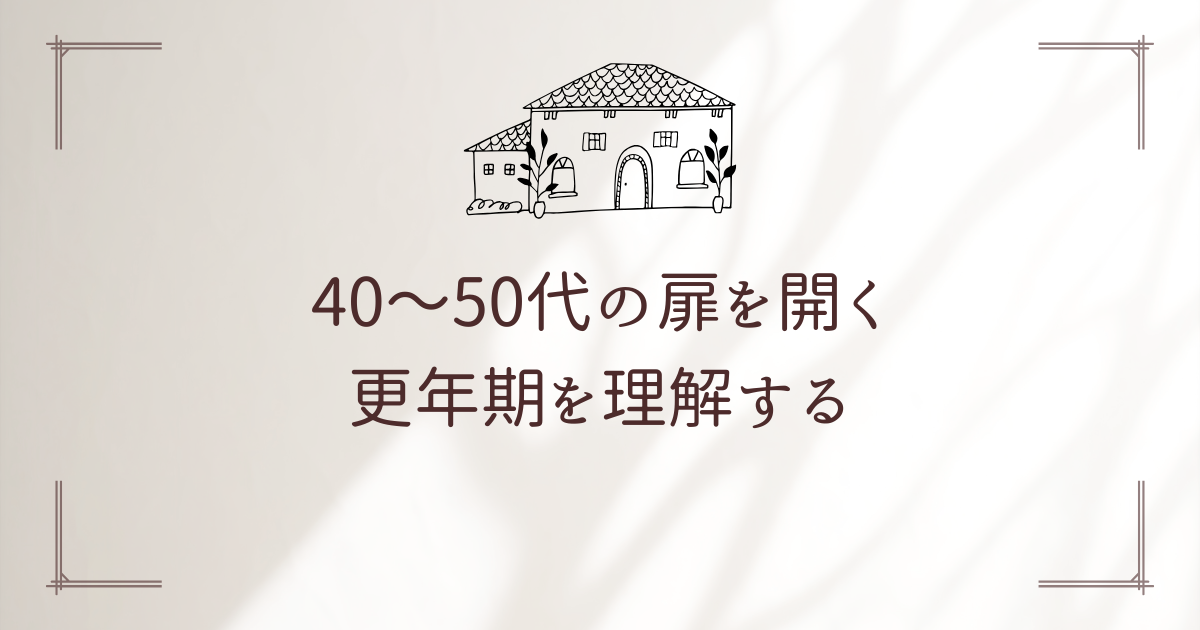更年期の自己管理とはなんだろう?

更年期の自己管理とはなんだろう?
〜年齢で変わっていくベーシック〜
「困難な日も、こんなんな日も」の管理人、こんなんさんです。
今回は、更年期×うつと上手に付き合いながら、定年までの長い就業人生を歩むための自己管理の基本フレームワークについてお話しします。
日々の小さな観察や工夫が、わたしたちの人生の質を大きく変えていく—そんな視点でいっしょに考えていきましょう。
■ バイタルサインと自己観察の基本
自分の「平常値」を知ることから始めよう
わたしたちは「おかしいな」と思ったときに医療につながるものです。でも「おかしいな」と思うには、まず自分の「ふだんの状態」を知っている必要があります。
基本的なバイタルサインの目安:
- 体温:36.0〜37.0度(個人差あり)
- 脈拍:安静時60〜80回/分(個人差あり)
- 血圧:収縮期血圧120mmHg未満、拡張期血圧80mmHg未満が理想
- 呼吸:安静時12〜20回/分
数字だけでなく、「今日の体調は10点満点で何点?」と自分に問いかけてみる習慣も役立ちます。ドラッグストアや調剤薬局にある血圧計。今までなんで必要なんだろうと思ってましたが大切だとわかりますね。
ホルモンの波を記録する
更年期世代のわたしたちは、ホルモンバランスの変動が大きいもの。その波を知ることで、少しずつ「波を読む力」が身につきます。
記録するとよい項目:
- 生理の周期や量の変化
- ホットフラッシュの頻度や強さ
- 寝汗の有無
- 疲労感・だるさの程度
- 頭痛やめまいの有無
- 気分の波(イライラ、憂うつなど)
この記録は、婦人科や心療内科を受診する際にもとても役立ちます。わたしの場合、毎日の症状をスマホのメモアプリに短く記録。あとから振り返ると「あ、この時期に症状が強くなる傾向があるな」と気づけて、心の準備ができるようになりました。
自律神経の乱れに気づく
更年期やうつ状態では、自律神経のバランスが崩れやすくなります。自律神経は「交感神経(活動モード)」と「副交感神経(休息モード)」のバランスで成り立っているもの。このバランスが崩れると、様々な不調につながります。
自律神経の乱れを示すサイン:
- 朝起きられない、または早朝に目が覚めてしまう
- 体温調節がうまくいかない(暑がり・寒がりの極端な変化)
- 動悸やめまいがある
- 消化器症状(下痢や便秘)が繰り返される
- 手足の冷えが強い
わたしは首の冷えが気になっているので、夏以外はネックウォーマーが手放せません。自分の体調の変化を細かく観察することで、「これは自律神経の乱れかも」と気づくことができるようになりました。
■ ストレスマネジメント概念とは
「ストレス反応」を味方にする考え方
ストレスは単に「悪いもの」ではなく、わたしたちの体を守る大切なシステム。このシステムの仕組みを知っていきましょう。
ストレス反応の基本的な仕組み:
- 脳がストレス(危険や課題)を感知
- 交感神経が活性化し、アドレナリンやコルチゾールなどのホルモンが分泌
- 心拍数上昇、血糖値上昇、筋肉の緊張などの「戦うか逃げるか」反応が起きる
- ストレス源が去ると、副交感神経が活性化し、体は徐々に元の状態に戻る
問題は、現代社会では慢性的なストレスにさらされることが多く、このサイクルがうまく完結せず、体がいつも「戦闘モード」になってしまうこと。更年期のホルモン変動はこの反応をより敏感にしてしまうことがあります。
ストレスサインを味方にする方法:
- 心身の変化(イライラ、疲れ、肩こりなど)を「休息が必要」というサインと受け止める
- そのサインを無視せず、早めに対処することでダメージを最小限に
- 「ストレスをゼロにする」より「ストレスと上手に付き合う」発想へ
わたし自身、以前は「できる自分」であることに価値を見出し、疲れのサインを無視していました。でも今は「疲れを感じたら休む」という単純なルールを大切にしています。これは「弱さ」なのかもしれません。でも弱いところがあってもいいのではないでしょうか。
「私のストレス対処レパートリー」を増やす
ストレス対処法は人それぞれ。自分に合ったレパートリーを持っていると心強いです。
短時間でできるストレス対処法:
- 呼吸法:4秒かけて吸い、7秒間息を止め、8秒かけて吐く「4-7-8呼吸法」
- リラックスヨガ:デスクに座ったまま、首や肩を優しくほぐすながらストレッチ
- 5-4-3-2-1法:周囲で見える5つのもの、聞こえる4つの音、触れる3つのもの、嗅げる2つのもの、味わえる1つのものを意識する方法
- 水分を摂る:ゆっくりと温かい飲み物(ノンカフェインが◎)を飲み、体を内側から温める。胃からじんわり温まる感じにほっこりします
- 温冷法:寒いところでホットフラッシュが起きたときは、首筋に冷たいタオルを当てる。冷えピタを持ち歩く
時間があるときのストレス対処法:
- 入浴剤を使ったゆっくりとした入浴:特にラベンダーやローズの香りは副交感神経を活性化
- 部屋着・パジャマに着替える:締め付けのない、肌触りの良い素材を選ぶことで体の緊張をほぐす
- インテリアを整える:心地よい空間を作ることで、視覚的にもリラックス効果
- ジャーナリングノートに気持ちを書き出す:言語化することで感情整理
「感情ハイジャック」から自分を守る
更年期症状とうつ状態が重なると、感情が自分の意志とは無関係に暴走する「感情ハイジャック」が起きやすくなります。
感情ハイジャックの対処法:
- 気づく:「今、感情にハイジャックされている」と認識する
- 一時停止:その場を離れるか、深呼吸など一時的な中断を入れる
- 言語化:「今、イライラしている/悲しい/怖い」と感情に名前をつける
- 受け入れる:その感情を否定せず「今はこう感じているんだな」と認める
- 対処する:反応する前にクールダウンの時間を取る
職場で動機が止まらなくなったとき、「トイレに行く」や「飲み物を取りに行く」という単純な行動が効果的だと気づきました。場所を変えることで、感情の流れを一時停止できるんです。「今、イライラしてるね」と自分に声をかける。この小さな対話が、感情を客観視する助けになります。
■ 睡眠衛生の基礎知識〜質の高い睡眠で体と心を守る
更年期×うつの睡眠問題を理解する
睡眠の質は、わたしたちの心と体の健康に直結します。とくに更年期とうつ状態では、睡眠障害が生じやすく、これが日中のパフォーマンスにも大きく影響します。
更年期×うつで起きやすい睡眠問題:
- 寝つきが悪い(入眠障害)
- 夜中に何度も目が覚める(中途覚醒)
- 早朝に目が覚めて眠れなくなる(早朝覚醒)
- 十分な時間寝ても疲れが取れない(熟睡感の欠如)
- 寝汗でパジャマや布団が濡れる
わたしの場合、更年期症状として最初に現れたのが「眠れない」という症状でした。入眠障害と中途覚醒の両方に悩まされ、そのせいで日中の集中力も低下。この悪循環を断ち切るため、睡眠環境を見直すことから始めました。
質の高い睡眠のための環境づくり
良質な睡眠を得るためには、環境整備が欠かせません。
睡眠環境の整え方:
- 温度:18〜23度が理想的(個人差あり)
- 湿度:50〜60%程度
- 光:できるだけ暗く(アイマスクの活用も)
- 音:静かな環境(耳栓や白色雑音も効果的)
- 寝具:体に合った枕とマットレス
- パジャマ:吸湿性・通気性の良い素材
わたしがしているのは寝汗対策として、吸水速乾性のあるパジャマに切り替えたことです。また、主治医に睡眠導入剤の処方もお願いしています。
朝起きたときに「よく眠れた!」と感じられるよう、自分に合った睡眠環境を少しずつ整えていきましょう。
睡眠の質を高める日中の習慣
良質な睡眠は、実は朝目覚めた瞬間から準備が始まっています。日中の過ごし方が夜の睡眠を左右するのです。
睡眠の質を高める日中の習慣:
- 朝日を浴びる:起床後30分以内に自然光を浴びる
- カフェイン摂取に注意:午後3時以降はなるべく控える
- 適度な運動:激しすぎない運動を日中に。階段を使うなど
- 食事のタイミング:就寝3時間前までに済ませる
- 入浴:就寝1〜2時間前の入浴でコアボディ温度を下げる(入浴剤で効果アップ)
- スマホ・PC:ブルーライトは睡眠ホルモン(メラトニン)の分泌を抑制するため、就寝1時間前には使用を減らす
わたしにとって有効だったのは「朝日を浴びる習慣」です。朝、カーテンを開けて日光を浴びることが気持ちいと感じます。開けるまでは面倒なので、そこは無条件に開けるのがコツです。
■ 栄養と運動の基本原則〜更年期×うつに効く食事と動き
更年期×うつをサポートする栄養素
体調不良やメンタルの波を感じるとき、実は栄養も大きく関わっています。
重要な栄養素:
- オメガ3脂肪酸:脳の健康を支え、炎症を抑制(青魚、亜麻仁油など)
- ビタミンD:ホルモンバランスの調整や骨の健康に関与(日光浴、きのこ類など)
- マグネシウム:神経や筋肉の機能を助け、睡眠の質を高める(ナッツ類、緑の葉野菜など)
- B群ビタミン:エネルギー代謝とメンタルヘルスに関与(豆類、レバー、玄米など)
- タンパク質:神経伝達物質の原料(大豆製品、肉、魚、卵など)
- 食物繊維:腸内環境を整え、メンタルヘルスにも影響(野菜、果物、全粒穀物など)
わたしの場合、忙しい朝は「アミノ酸入りホエイプロテイン」で済ませています。ホエイプロテインはすぐにエネルギーになりやすいと聞いたので朝に。夜は大豆由来のプロテインと使い分けています。
無理なく続けられる運動習慣
運動は体調管理の重要な柱ですが、更年期やうつ状態では「やりたいけどできない」というジレンマがありますよね。そんなときこそ、小さな運動から始めることが大切です。
更年期×うつ状態でも取り入れやすい運動:
- ウォーキング:10分から始めて徐々に延ばす
- ストレッチ:朝起きたときや就寝前にゆっくりと
- リラックスヨガ:呼吸と動きを連動させる気持ちよく伸ばす
- 階段を使う:エレベーターの代わりに階段を選ぶ
- デスクでのミニエクササイズ:座ったままでかかとを上げ下げ
■ 記録と振り返りの重要性〜自分の変化を可視化する
ジャーナリングの力
自分の状態を言葉にして記録する「ジャーナリング」は、更年期やうつと付き合う上で強力なツールとなります。
ジャーナリングの効果:
- 自分の感情や身体感覚を客観視できる
- パターンや傾向に気づきやすくなる
- 思考を整理し、混乱を減らせる
- 自己理解が深まる
- 医療機関での説明が的確にできるようになる
ジャーナリングのシンプルな始め方:
- 専用のジャーナリングノートを用意する
- 決まった形式にこだわらない
- 「今日の体調:点数」「気分:晴れ/曇り/雨」など簡単な記号も活用
- 毎日続けられなくてもOK
- 「答え」を出す必要なし、書くプロセスを楽しむ
わたしは寝る前に、その日の体調と気分を5段階で評価し、かんたんな一言とともに記録するようにしています。例えば「体調:3/5 気分:2/5 今日は会議が長くて疲れた」といった感じ。これだけでも、後から振り返ると「あ、この週はずっと体調が優れなかったな」など、パターンが見えてきます。気になった言葉も脈絡なく書くことも
体調・症状・活動のセルフモニタリング
日々の変化を数値化して記録する方法も効果的です。これによって、医療機関での説明がしやすくなり、自分でも変化に気づきやすくなります。
記録するとよい項目:
- 睡眠時間と質(例:7時間/5点)
- 体温(基礎体温のように毎朝測定)
- 症状の有無と強さ(ホットフラッシュ、頭痛など)
- 月経の状態(周期、量、随伴症状)
- 服用した薬やサプリメント
- 運動や活動の内容と時間
- 特別なストレス要因
- 食事内容(特に気になる場合)
これらの項目をすべて記録する必要はなく、自分にとって意味のある項目を選んで記録していきましょう。スマホのアプリや手帳など、自分にとって続けやすい方法で記録することが大切です。
「見えない痛み」を見える化するコツ
更年期症状やうつ状態の辛さは、周囲から「見えづらい」ものです。そのため、自分で状態を「見える化」するスキルが役立ちます。
見える化のコツ:
- 数値化する:「ふだんの自分を10として、今日は6」など
- 比喩を使う:「頭が霧の中にいるような感じ」など
- 具体的な影響を伝える:「集中して文章を読めるのは15分が限界」など
- 視覚的なスケールを活用:「痛みスケール」など医療でも使われる尺度
この「見える化」スキルは、医療機関でのコミュニケーションだけでなく、職場や家庭での理解を得るためにも役立ちます。わたしは職場の上司に「今日の集中力は5割ほどです」など、具体的に伝えることで、適切なサポートを得られるようになりました。
■ おわりに:自分を客観的に見てみる
更年期とうつ、この二つの波を同時に経験することは、確かに困難です。でも、この時期だからこそ得られる気づきや知恵もあります。
「自分を知り、自分を守る」。長い人生を生き抜くための賢明な戦略や知見です。
日々の小さな自己観察や工夫が、やがて大きな自己管理の力となります。「できることから少しずつ」を心がけて、自分のペースで健康管理のスキルを磨いていきましょう。
大切なのは「自分を優しく見守る目」です。「年相応の変化」も、「心の揺れ」も、すべて含めて自分自身。その全体を受け入れながら、より良い明日へと歩んでいきましょう。
みなさんの小さな気づきや工夫、ぜひコメント欄でシェアしてくださいね。
「困難な日も、こんなんな日も」
── こんなんさん
※この記事についてのご感想や、あなた自身の体験談などがありましたら、ぜひコメント欄でシェアしてください。みなさんの声が、次の記事の励みになります。
*「こんなんな日も」とは、「こんなん出た」、「こんなんいるー?」など、関西弁から取りました。ただ、管理人は関西人ではありません…。