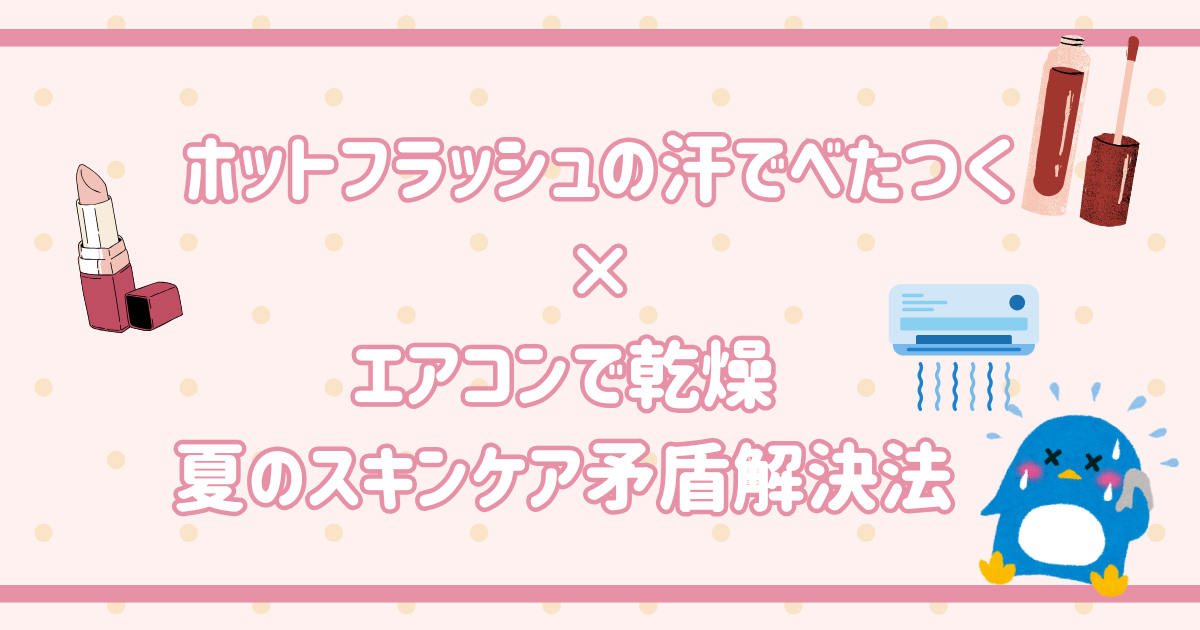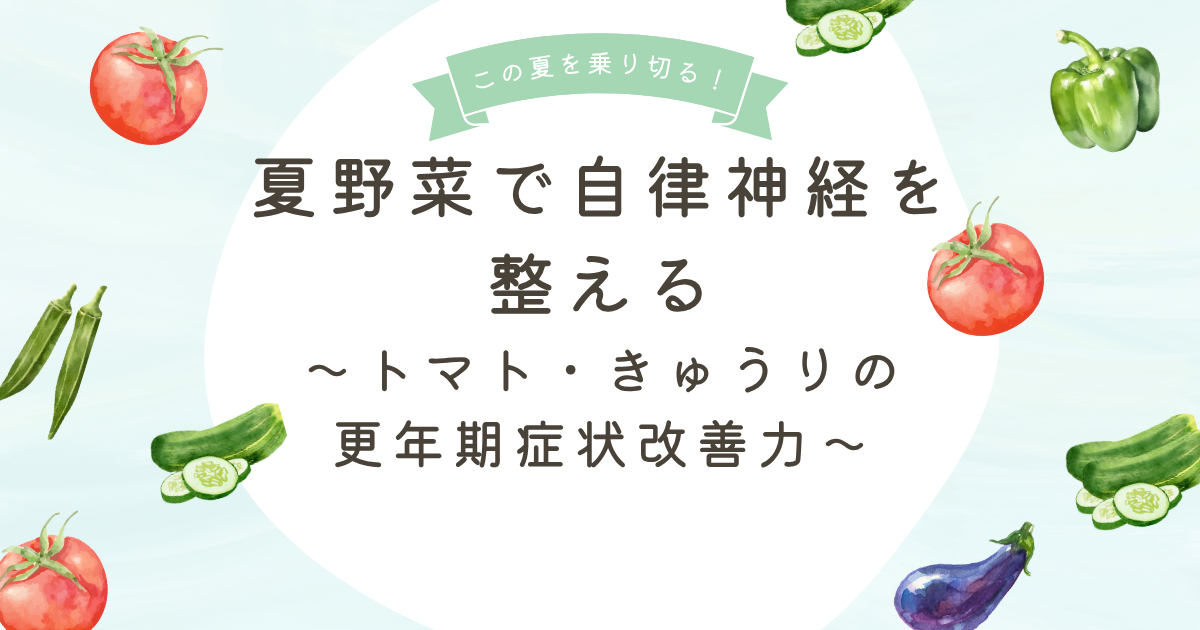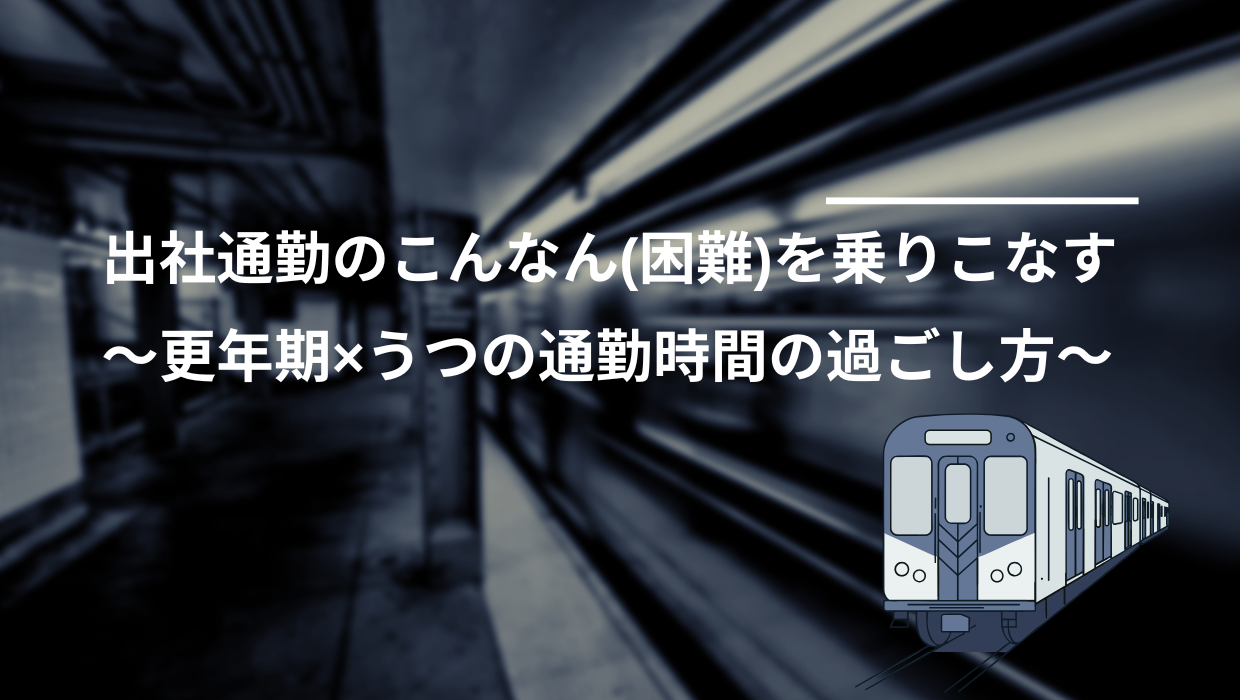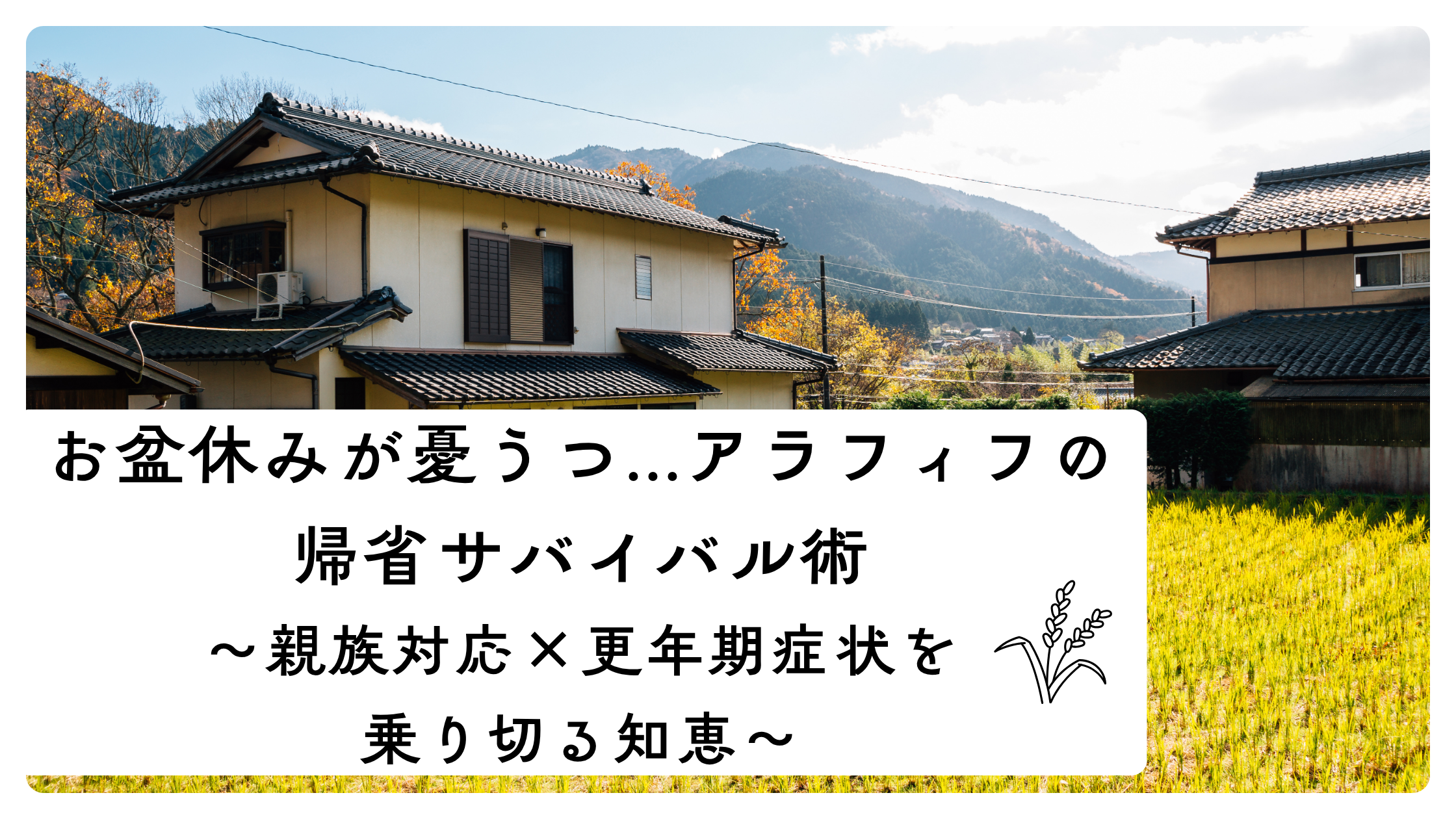朝のこんなん(困難)を乗り切る

朝のこんなん(困難)を乗り切る
〜更年期×うつの朝の過ごし方〜
おはようございます…というより、おはようってなかなか言えない日々を過ごしていませんか?
「困難な日も、こんなんな日も」の管理人、こんなんさんです。
今回は、更年期とうつを抱えるわたしたちの「朝」について、率直に向き合ってみたいと思います。
朝起きるのがつらい。
体が鉛のように重い。
目が覚めても心がついてこない…。
そんな朝の困難を少しでも和らげる方法を、経験を交えてお伝えします。
■ なにか背中に乗って寝起きを邪魔してる?
「5分だけ…」が30分になる目覚めの罠
目覚まし時計の音。そして、私の日課となったのが「あと5分だけ…」と言いながらスヌーズボタンを押すこと。この”あと5分”が気づけば30分、時には1時間に…。
そして最終的に「やばい、遅刻する!」と飛び起きて、バタバタと準備をする。
この焦りが、さらに心と体に負担をかけるスパイラルに陥っていることに気づいたのは、更年期治療を始めてからでした。
目覚めの悪さと朝のホットフラッシュの二重奏
起床時の「だるさ」は、更年期以前から経験していました。でも、46歳になってからの朝のだるさは、まるで違うレベル。
体が布団から離れてくれない。頭がぼんやりして、目が開けられない。そして、やっと起き上がったと思ったら、突然の「ホットフラッシュ」。
パジャマが汗でびっしょり。でも、汗が引くと今度は寒気が…。この温度調節の乱れが、朝の準備をさらに困難にしていました。
「今日も始まる…」という重圧感
そして何より辛いのは、目が覚めた瞬間から押し寄せる「今日も1日、乗り切れるだろうか」という不安と重圧感。
うつ症状が強い日は特に、朝、目を開けた瞬間から「今日も無事に終われるだろうか」という不安が胸に広がります。この感覚は、説明するのが難しいけれど、「朝からすでに力尽きている」感じです。
■ 朝のこんなん(困難)を乗り切るための私の工夫
布団の中でできるマイクロステップ
❶ 「起きなきゃ」から「今ここ」への意識転換
「早く起きなきゃ」「また朝が来てしまった」というネガティブな思考から、「今日の体調はどうだろう?」という観察に意識を向けるようにしています。
布団の中で、深呼吸を3回。それだけでOK。むしろ「今日はどんな1日になるだろう」とか「やるべきことがたくさんある」という未来の心配事がでてきたら、こんな日もあるよね~と口に出してみてます。
❷ 布団の中でできる”ゆるストレッチ”
完全に目が覚めていなくても、布団の中でできるストレッチがあります。私が毎朝実践しているのは:
- 手足の指をゆっくり開いて閉じる(気持ちがいいなと思えるだけ)
- 両腕を頭上に伸ばして、全身を大きく伸ばす(力が入らないときは両手を上げるだけでOK)
これは、起き上がる前の「準備」としてとっても効果的です。
❸ “ベッドジャーナリング”で心の準備
ベッドの横に小さなノートとペンを置いておき、起きてすぐに3行だけ書くようにしています。気分が乗れば、何ページでも。
「眠い」「のどが枯れている」「あんぱんたべたい」
たった3行でも、自分の状態を言語化することで、なんとなく目覚められるようになりました。とくにうつの日は、「くもり」「体重い」といった正直な気持ちを書くことで、自分を責めすぎない効果があります。書いたことに何もジャッジしないが大切です。
朝の体調に合わせた”起き方の選択肢”を持つ
❶ 体調最悪日のための「最小限プラン」
更年期とうつを持っている人には、「どうしても起きられない日」があることを認めましょう。そんな日のために、「最小限プラン」を用意しておくと安心です。
管理人こんなんさんの場合:
- 出社する場合:髪はドライシャンプーでさっと整える
- ふちのしっかりしたメガネをかける
- リモートワークの場合:カメラオフで参加できる会議は耳だけ参加。あとで録画をAIで要約
- 本当にダメな日:有給や半休を躊躇なく使う
「無理をしない」という選択肢も、自分に許可しちゃいましょう。
❷ 「寝たまま瞑想」5分法
どうしても体が重くて起きられない日は、「寝たまま瞑想」を試しています。
目を閉じたまま、自分の呼吸に意識を向けます。吸う息、吐く息をただ感じる。思考が浮かんできても、「あ、考えているな」と認識して、また呼吸に戻る。
最初は「瞑想なんて無理」と思っていましたが、寝たままできるこの方法は、朝の心の整理に役立っています。体調が悪くても、これなら「今日も何かできた」という小さな達成感を得られます。たまにそのまま寝てしまうときもあるので休日におすすめです。
❸ エネルギー温存のための「朝の準備シンプル化」
朝のエネルギーは有限です。特に更年期とうつがある私たちは、朝のエネルギーを「何に使うか」を選ぶ必要があります。
管理人こんなんさんが実践している朝の簡略化:
- 洋服は曜日ごとのコーデを決めておく
- 朝食は簡単に摂れるものを用意(プロテインなど)
- メイクアイテムを減らす(BBクリーム、眉毛はアートメイク、リップの3点だけの日も)メガネをかければわかりません
「カンペキな朝」などもう無く、「続けられる朝」にシフトしました。
■ 朝のエネルギーを確保するための夜の準備
就寝環境の整備
❶ 睡眠とホルモンバランスの微妙な関係
更年期になると、睡眠の質が落ちることが多いですよね。とくに、夜間の発汗やホットフラッシュは睡眠を妨げる大きな原因です。
管理人こんなんさんが整えているのは:
- 寝室の温度:18〜20度に設定
- 口テープで乾燥と口呼吸をふせぐ
- 枕の高さ:肩こりを防ぐため、通気性のいい低めの枕に変更
- サラッとしたパジャマで肌触りを楽しむ
❷ 「就寝1時間前」のルーティン
睡眠の質を高めるため、就寝1時間前からは「睡眠モード」に入るようにしています。
- 温かいハーブティー(カモミールやラベンダー)を飲む
- 足首と首元を温める(冷え対策に効果的)
温かい飲み物とストールで首を温めることは、自律神経を整えるのに役立っています。スマホを見ない方がいいとわかってはいるのですが、まだやめられません。
❸ サプリメントとの付き合い方
更年期とうつの症状緩和のため、いくつかのサプリメントを試してきました。朝のエネルギー確保のためにしてるのは:
- マグネシウム:お茶やレモン水に数滴入れて飲んでいます
- ビタミンD:冬場の気分の落ち込みに効果ありと聞いたので夜に摂っています
ただし、サプリメントは医師や薬剤師に相談しながら取り入れることをおすすめします。
休日のエネルギー回復法
❶ 「寝だめ」より「質の良い休息」
医学的には「寝だめ」は効果がないと言われていますが、現実的には「休日にたくさん寝たい」と思いますよね!
でも、単に長時間寝るより、質の良い休息を取るほうが効果的だと実感しています。
- 平日より1〜2時間程度長く寝る
- 午前中に20分程度の昼寝
- 横になって読書や瞑想、ジャーナリング
ふわふわとした気持ちの朝を迎えられたら最高って思ってます。
❷ 「休日の朝」を大切にする
平日の朝は時間との戦いになりがちですが、休日こそ「ていねいな朝」を過ごすようにしています。
- 目覚めたら、すぐに起きず、ゆっくり伸びをする、生きてることを実感する
- シートマスクで顔を洗顔とパックを同時に(ていねいではないかもです…)
- 時間をかけて朝食を楽しむ。お茶を飲んで胃を温める。あまいものを少し。30分後に朝食を食べるなど、コースを楽しむようにすると気持ちがいいものです。
「何もしない時間」をあえて作ることで、心と体が回復するのを感じます。
■ おわりに:「朝の自分」を責めない
わたしたち更年期世代が心に留めておきたいのは、「朝の自分を責めない」ということ。
「なぜ起きられないのか」「どうして朝からこんなに疲れているのか」と自分を責めるのではなく、「今日の体調に合わせた選択をした」と考えるだけで、心の負担は軽くなります。
更年期もうつも、決して「怠け」や「甘え」ではありません。ホルモンバランスの変化は、意思とは関係なく起こることです。それを理解した上で、自分なりの「朝のこんなん」対策を見つけていきましょう。
みなさんは、朝のこんなんに対してどんな工夫をされていますか?
「困難な日も、こんなんな日も」
── こんなんさん
※この記事についてのご感想や、あなた自身の体験談などがありましたら、ぜひコメント欄でシェアしてください。みなさんの声が、次の記事の励みになります。
*「こんなんな日も」とは、「こんなん出た」、「こんなんいるー?」など、関西弁から取りました。ただ、管理人は関西人ではありません…。