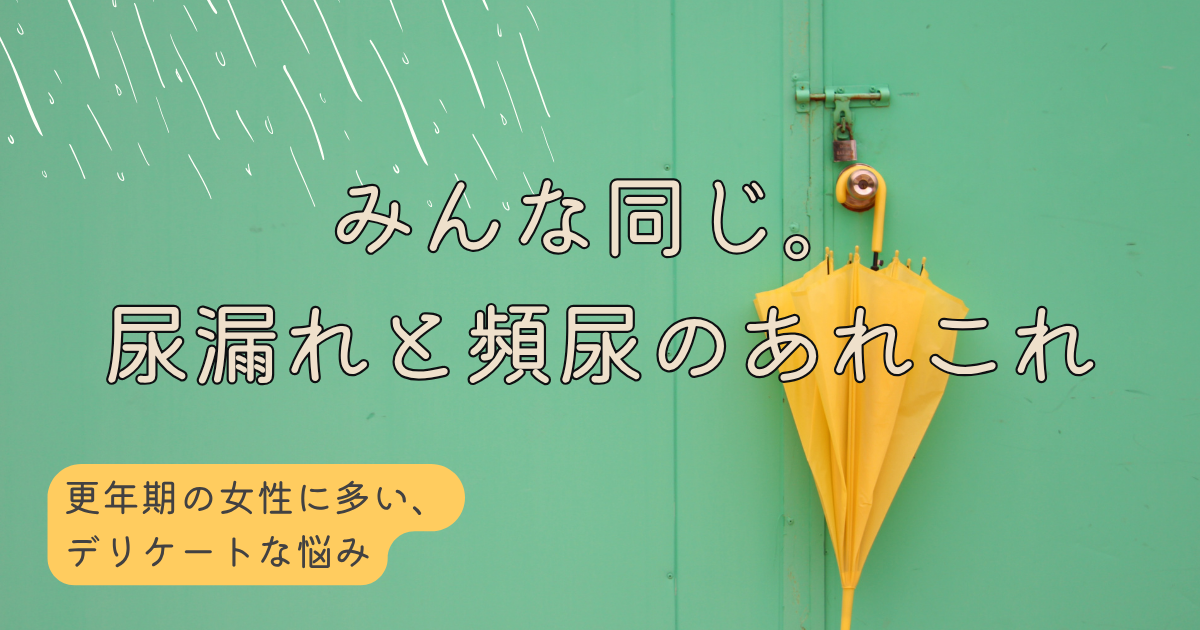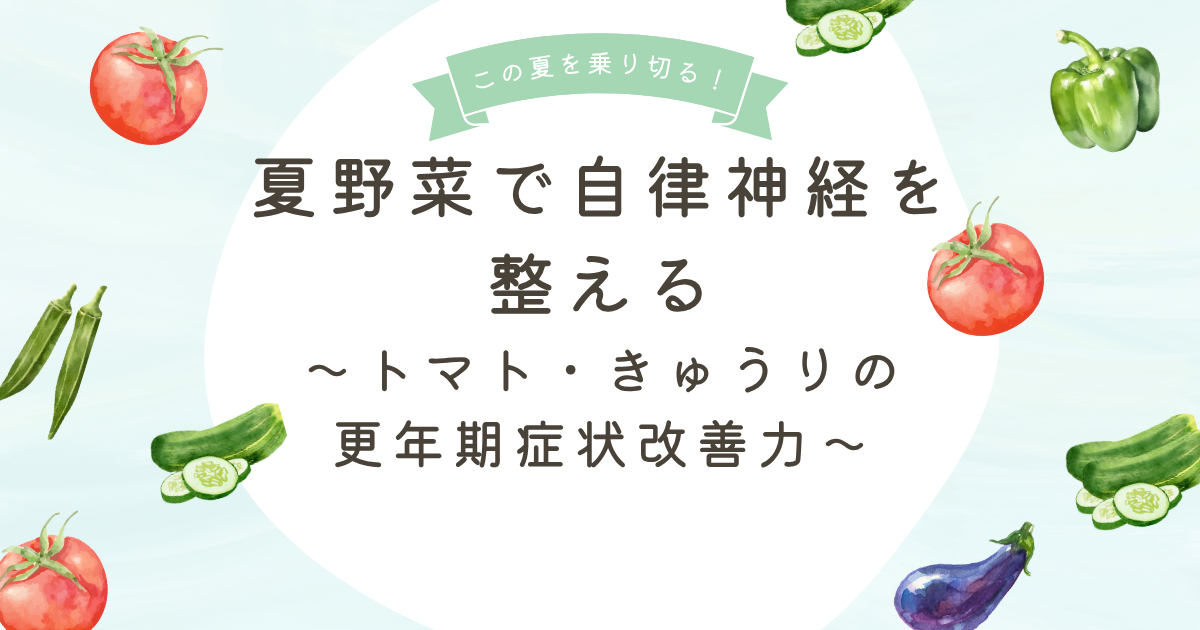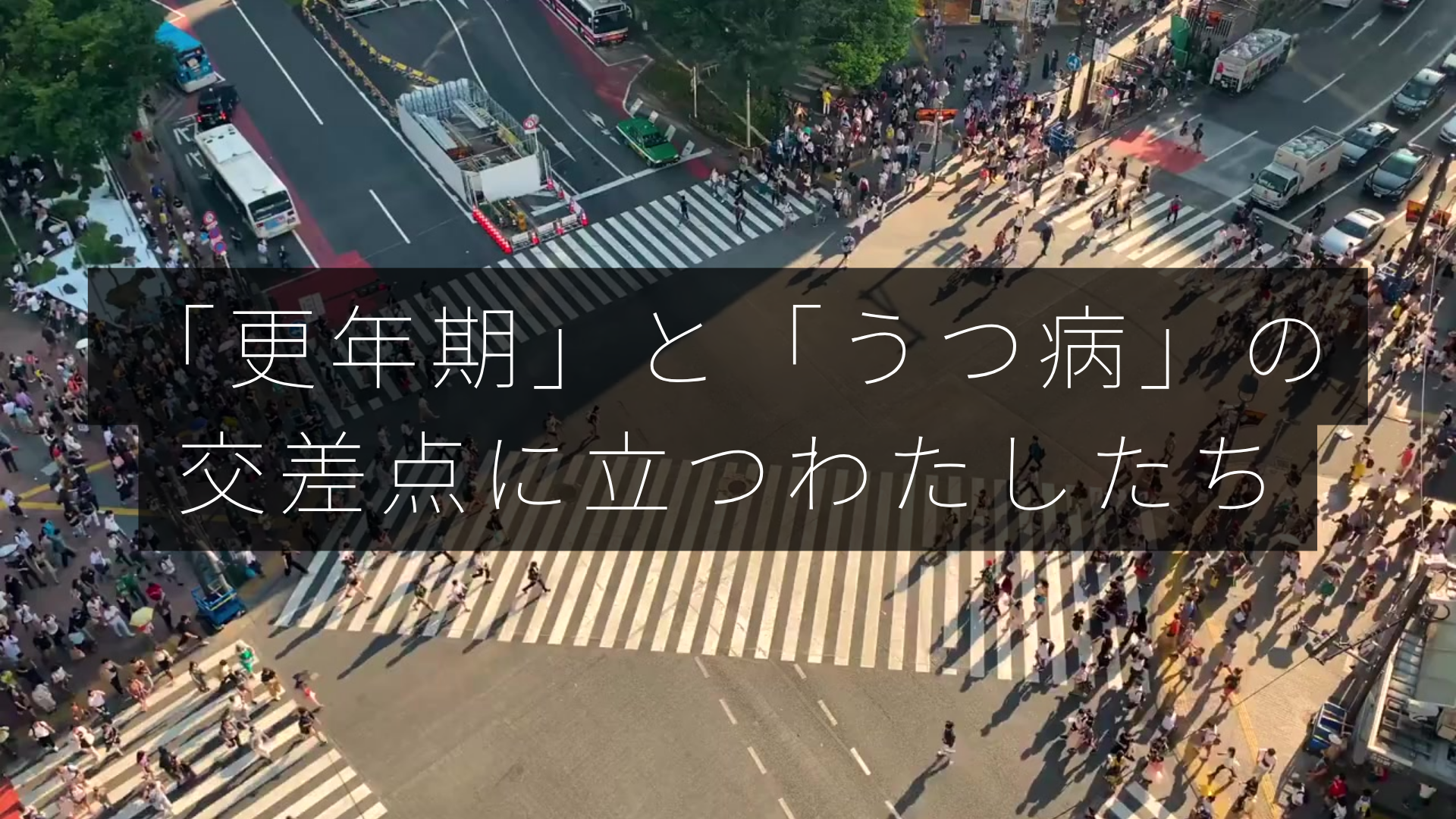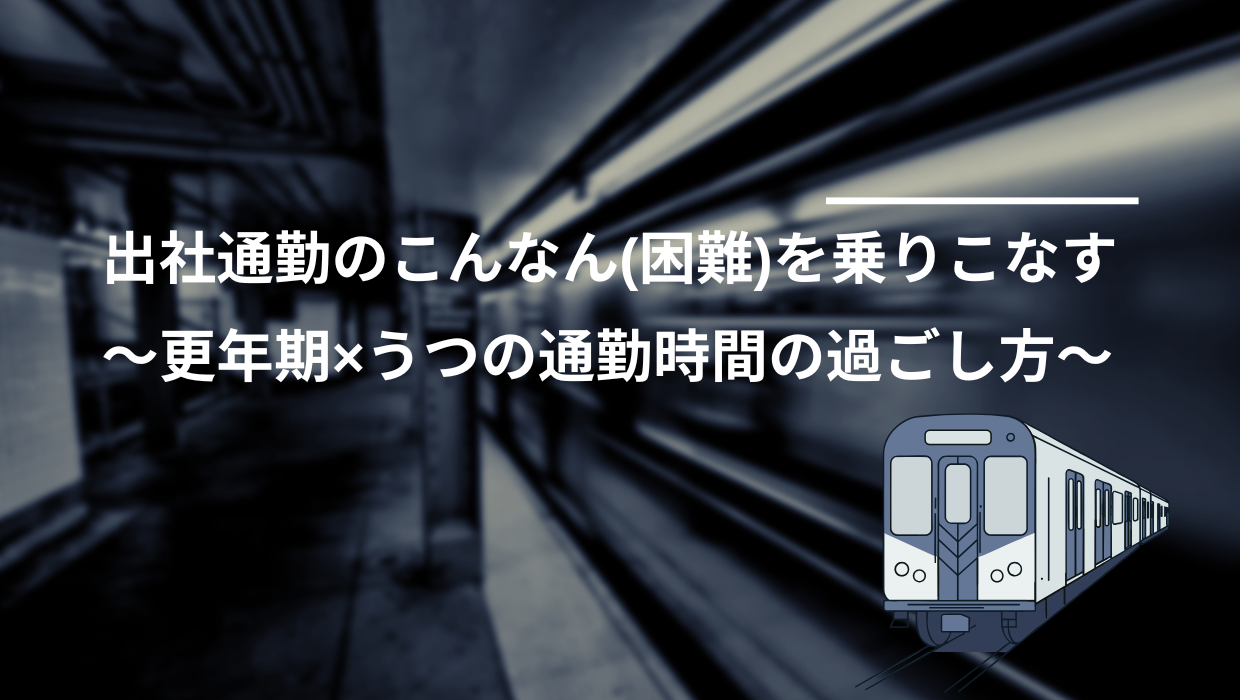がんばりすぎるアラフィフ女子の休息術〜自律神経と仲良くなるヒント〜
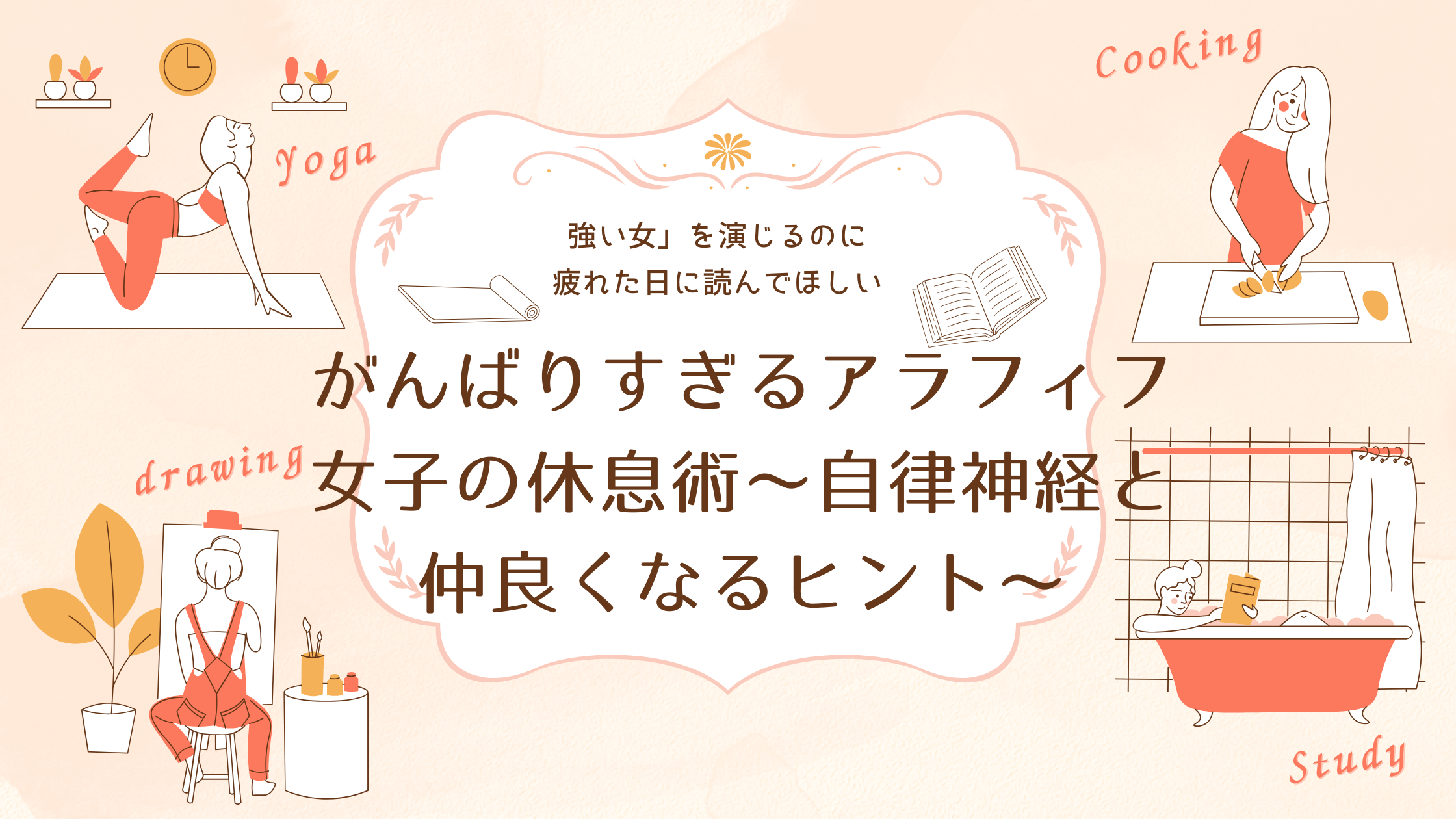
がんばりすぎるアラフィフ女子の休息術〜自律神経と仲良くなるヒント〜
〜「強い女」を演じるのに疲れた日に読んでほしい〜
「困難な日も、こんなんな日も」の管理人、こんなんさんです。
最近、こんな風景を目にしました。満員電車の中、40代後半と思われる女性が立ったまま資料に目を通し、スマホで何かを確認し、そして小さなため息。その横顔には、疲労と緊張が同居していて…「ああ、わかるなぁ」と思わず共感してしまいました。
振り返れば、わたしも長いことそうでした。「がんばる女性」「強い女性」であることを自分に課し、休むことさえ「怠け」のように感じる日々。
でも、もうそろそろ「がんばりすぎない選択」をしてもいいんじゃないでしょうか?
今日は、アラフィフ世代の私たちが無意識に背負っている「強くあるべき」という呪いと、更年期×疲れに効く「自律神経ケア」について、お話ししたいと思います。
■ 「がんばり女子」から身を引く時期—更年期×日本社会の期待値
「母のように強く」という刷り込み
わたしたちアラフィフ世代は、独特の価値観を植え付けられて育ちました。
お母さんたちは「良妻賢母」を理想とし、家事も育児も完璧にこなす姿を見せてくれました。その一方で、自分のことは後回し。「女は強くなければならない」という無言のメッセージを受け取りながら育ったんですよね。
そして、バブル崩壊後の氷河期に社会人となったわたしたち。就職難の中でも「なんとか仕事はしなければ」と歯を食いしばり、「男性と同じように働き、それでいて女性らしさも失わない」という矛盾した期待を背負いました。
でも今、そのがんばりすぎが限界を迎えようとしている気がします。がんばりすぎたツケが、更年期の症状として現れてくる。頑張りたい気持ちはあるのに体が付いてこない、そのもどかしさ…。それが、わたしたちアラフィフ世代の今の姿なのかもしれません。
「わたしは大丈夫」という呪文の危うさ
「大丈夫」—この言葉、何度言ったことでしょう。
朝から夕方まで仕事をし、帰宅後は家事をこなし、週末は実家の親の介護に行き…。そんな生活を「私は大丈夫」と言い聞かせながら続けてきました。
この「大丈夫」という言葉は、実は二つの危うさを含んでいます。一つは、本当は大丈夫ではないのに、自分に言い聞かせている場合。もう一つは、周囲に「助けて」と言えない状況に自分を追い込んでいる場合。
わたし自身、「大丈夫」と言いながら、実は夜中に目が覚めて動悸がしたり、急にイライラして職場で物を落としたり…。こういう経験、みなさんもありませんか?
これって、更年期の症状であると同時に、体からの「そろそろ休んで」というメッセージでもあるんです。
■ 体と心のもどかしさ—更年期×疲労の見えない連鎖
疲れが取れない理由—交感神経と副交感神経のバランス
「なんだか疲れが取れない」そんな日が続いていませんか?
これは単なる「年齢のせい」ではなく、自律神経のバランスが崩れているサインかもしれません。自律神経には「交感神経」(活動モード)と「副交感神経」(休息モード)があり、この二つが上手く切り替わることで、健康なリズムが保たれています。
更年期に入ると、エストロゲン(女性ホルモン)の減少により、この切り替えがスムーズにいかなくなることが。とくに「休息モード」へのシフトが難しくなり、体は休んでいるのに脳は休めない…そんな状態になりがちです。
例えば、こんな経験はありませんか?
- 夜寝る前までスマホをチェックし、頭はぼんやりしているのに眠れない
- 休日なのに仕事のことが頭から離れず、ゆっくりできない
- TVを見ていても内容が入ってこず、常に何か別のことを考えている
これらは全て、交感神経(活動モード)が優位になりすぎて、副交感神経(休息モード)に切り替わりづらくなっている状態なんです。
更年期独特のもどかしさ—やる気はあるのに体が動かない
更年期の疲れは、若い頃の疲れとは質が違います。「がんばりたい気持ちはあるのに体が思うように動かない」「頭ではわかっているけど実行できない」といった独特のもどかしさがあるんです。
これは、エストロゲンの減少が直接的・間接的に自律神経に影響を与えているから。エストロゲンには神経伝達物質の調整機能があるため、その減少は自律神経のバランスを崩しやすくします。
わたしの場合、42歳頃から「なんだか疲れが違う」と感じるようになりました。20代・30代の疲れは「寝れば回復する」単純なものでしたが、40代半ばからは「寝ても寝ても疲れが取れない」「眠れないのに昼間は眠い」という矛盾した状態に。
やる気と行動の間に大きな壁があるような、このもどかしさ。これこそが、更年期特有の症状なのかもしれませんね。
■ アラフィフ世代のための「自律神経ケア」実践法
副交感神経を上手に活性化する日常の工夫
「休息モード」である副交感神経を活性化するには、意識的な工夫が必要です。日常生活に取り入れやすい方法をいくつかご紹介します。
呼吸法:「4-7-8呼吸法」は特におすすめ。4秒かけて鼻から息を吸い、7秒間息を止め、8秒かけて口からゆっくり吐き出す。これを4回繰り返すだけで、副交感神経が活性化します。会議前、イライラしたとき、寝る前など、いつでもどこでも実践できるのが良いところ。
入浴法:38〜40度のぬるめのお湯に20分ほど浸かる「ぬる温浴」が、副交感神経の活性化に効果的。熱いお湯は交感神経を刺激してしまうので注意が必要です。わたしは入浴中に好きな香りのバスオイルを数滴たらし、目を閉じて深呼吸するのが日課になっています。
触れる安らぎ:肌触りの良いぬいぐるみを抱きしめることも、副交感神経を活性化させる効果があります。わたしは昔から大切にしている柔らかいクマのぬいぐるみを枕元に置いていて、眠れない夜や疲れがひどい日には抱きしめています。触り心地の良さが、不思議と心を落ち着かせてくれるんです。
「切り替えスイッチ」を持つことの大切さ
仕事モードから休息モードへの切り替えが上手くいかず、いつも脳が活性化している状態…。これが現代のアラフィフ女性の悩みの一つだと思います。
そこで役立つのが「切り替えスイッチ」の存在。仕事と私生活の境界線となる、ちょっとした儀式や習慣を持つことが大切です。
切り替えスイッチの例:
- 帰宅したらまず手洗い・うがい・着替えを一連の流れで行う
- オフィスとプライベートで使う香水やハンドクリームを変える
- 仕事終わりに「今日の仕事はここまで」と声に出して宣言する
- 通勤電車で聴く音楽と、帰宅時に聴く音楽を変える
わたしの場合は「帽子ルール」を設けています。仕事用のベレー帽をかぶって出勤し、帰宅時に玄関で取る。この小さな動作が、「仕事モード終了」の合図になっているんです。
このような「切り替えスイッチ」は、自律神経の切り替えを助け、心と体のメリハリをつけるのに役立ちます。
■ 「がんばらない」選択をする勇気—現実的な対処法
「完璧」という幻想から身を引く
わたしたちの世代は、「何でも完璧にこなすスーパーウーマン」という幻想に囚われてきました。でも、更年期を迎えたいま、その幻想から少し身を引くタイミングなのかもしれません。
「完璧」からの身の引き方:
- 「いい加減」を「良い加減」と捉え直す:「ほどよく」が一番健康的
- 「手抜き」を「効率化」と言い換える:省エネ家事は賢い選択
- 「自分基準」を見直す:他人の評価ではなく、自分の体調を優先
わたしは以前、休日も完璧に掃除した家でなければ気が済まなかったのですが、今は「見えるところだけ片付ける」ことにしました。結果、疲れも減り、家族との時間も増えて一石二鳥。「完璧な家事」より「ほどよい家事と充実した時間」を選ぶようになりました。
■ 「見えない疲れ」をどう伝えるか—家族との共有
家族との共有—「見えない症状」の見える化
更年期症状や疲れを家族に理解してもらうのは、一苦労ですよね。特に「なんとなく調子が悪い」という漠然とした状態は、伝わりにくいもの。
家族との共有のコツ:
- 具体的な例を挙げて説明する(「急に汗が出る」「夜中に何度も目が覚める」など)
- 状態を数値化する(「今日の体調は10点満点中6点」など)
- 医療情報や書籍の内容を共有する(客観的な情報として)
- 家族に協力してほしいことを明確に伝える(「疲れているときは静かな時間がほしい」など)
わたしは「体調メーター」という方法を取り入れています。リビングの見えるところに、自分の体調を1〜10の数字で示すマグネットを貼っておくんです。「今日は4だから、あまり話しかけないで」「今日は8だから、外出できるよ」というように。これで言葉で説明する手間が省け、家族も遠慮なく確認できるようになりました。
親世代への理解も深まる—母の苦労が今わかる
更年期を経験している今、初めて母の苦労がわかるようになりました。あの頃の母の急な感情の変化や疲れた様子、「なんでそんなに怒るの?」と思っていた反応—それが更年期症状だったのかと、今になって理解できます。
わたしが10代の頃、母は更年期真っ盛り。でも当時は「更年期」という言葉すら知らず、母の不調や感情の波を理解できませんでした。今自分が同じ立場になって、母がどれだけ頑張っていたのかが痛いほどわかります。
この「世代を超えた理解」が、家族との対話の糸口になることも。「お母さんも同じだったの?」という会話から、更年期についての理解を深めてもらえることもあります。過去と現在をつなぐ対話が、更年期を生きる知恵を紡いでいくのかもしれませんね。
■ 更年期を味方にする—今のわたしと向き合う時間
「今のわたし」と向き合う時期としての更年期
更年期は、単なる「我慢の時期」ではありません。むしろ、今まで周囲の期待に合わせて生きてきた自分を見つめ直し、「今のわたし」と向き合うチャンスなのかもしれません。
「今のわたし」と向き合うステップ:
- 自分の体調や気分の変化を丁寧に観察する習慣をつける
- 「してあげなければならない」ことと「したいこと」を区別してみる
- 小さな「自分のための時間」を日常に組み込む
- 「喜ばせる自分」から「本当の自分」への移行を意識する
わたしは、週に一度「自分時間ノート」という日記をつけるようにしました。「今週、自分が心から楽しいと感じたこと」「エネルギーを奪われたと感じたこと」を書き出すのです。これを続けるうちに、「実は〇〇が好きだった」「△△は期待に応えようとしているだけ」といった発見が増えてきました。
この自己観察が、少しずつ「今のわたし」と向き合うきっかけになっているように感じています。
自律神経の波に乗る生き方—「流れに逆らわない」智慧
更年期の体調変化や自律神経の乱れは、ある意味で「自然の流れ」。この流れに必死に逆らうより、上手に波に乗る生き方を模索してみませんか?
「流れに乗る」生き方のヒント:
- 朝の調子が良い日は仕事を進め、調子が悪い日はルーティンワークに切り替える
- ホットフラッシュが出やすい時間帯を把握し、重要な会議などを避ける
- 自分の体調リズムを記録し、パターンを見つける
- 「今だけの状態」と捉え、自分を責めない
わたしの場合、月の前半は比較的調子が良く、後半になると集中力が落ちる傾向があることに気づきました。そこで、重要なプレゼンや会議は月の前半に入れるよう調整。スケジュール調整できることは、積極的に「自分に合わせる」ようにしています。
こうした小さな調整の積み重ねが、自律神経の乱れと上手に付き合う道なのかもしれません。
■ おわりに:「できる」の定義を変える時
アラフィフを迎え、更年期の波を感じながら、わたしたちは「できる」の定義を変えるときなのかもしれません。
これまでの「できる」は「無理をしても成し遂げる」「弱音を吐かない」「完璧をめざす」ことでした。でも、これからの「できる」は「自分の限界を知る」「必要なときには助けを求める」「自分を大切にする」ことではないでしょうか。
やる気はあるのに体が言うことを聞かないもどかしさ、慢性的な疲れ、更年期の不調—これらは「弱さ」ではなく、自分を大切にするように促す体からのメッセージ。このメッセージに素直に耳を傾け、「がんばるべき」から「休むべき」へと選択を変える勇気を持ちたいと思います。
「無理をする私」から「自分を大切にする私」へ。その優しい移行を、わたしたちアラフィフ世代で一緒に実践していきませんか?
自律神経と更年期は、わたしたちに「もう、がんばりすぎなくていいよ」と教えてくれているのかもしれません。その小さな声に、耳を澄ませてみましょう。
みなさんは、どんな「がんばり癖」がありますか?どんな「自分を大切にする習慣」を始めましたか?良かったら、コメント欄でシェアしてくださいね。
「困難な日も、こんなんな日も」
── こんなんさん
※この記事についてのご感想や、あなた自身の体験談などがありましたら、ぜひコメント欄でシェアしてください。みなさんの声が、次の記事の励みになります。
*「こんなんな日も」とは、「こんなん出た」、「こんなんいるー?」など、関西弁から取りました。ただ、管理人は関西人ではありません…。
参考リンク
- https://www.jsog.or.jp/citizen/5717/
- 厚生労働省:女性の健康推進のための取組
- 日本心身医学会:ストレスと自律神経の関係