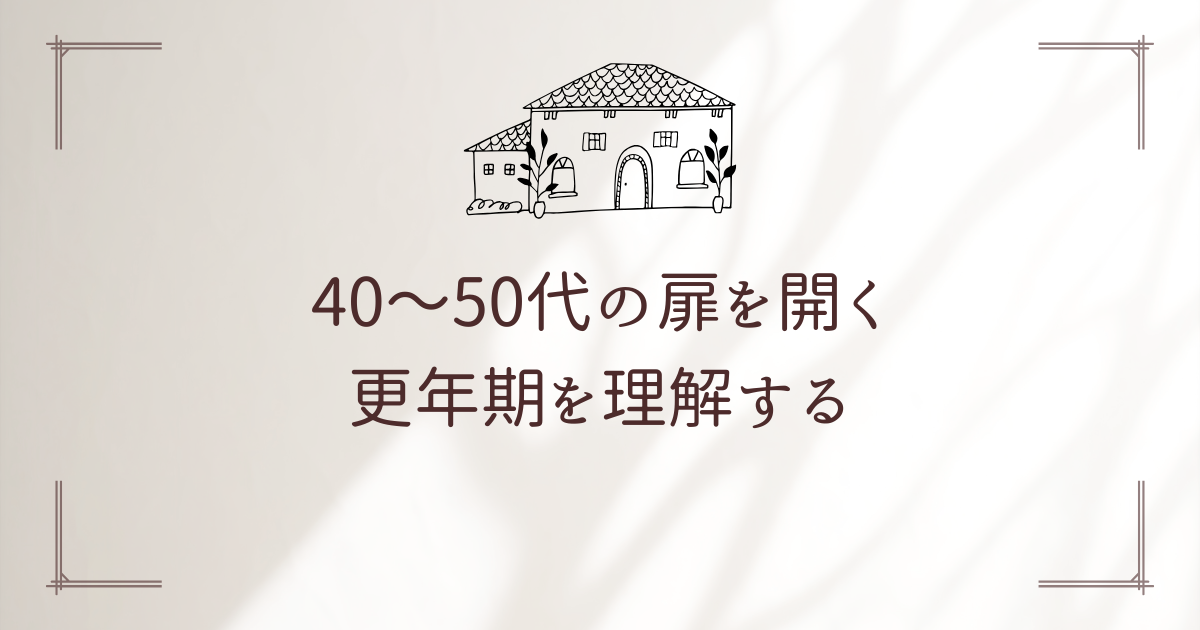心はうつろいゆくもの:メンタルヘルスを知っておこう

心はうつろいゆくもの:メンタルヘルスを知っておこう
〜更年期×メンタルヘルス、複雑な絡まりをほどく〜
「困難な日も、こんなんな日も」の管理人、こんなんさんです。
「最近、涙もろくなった」「何をしても楽しくない」「自己嫌悪が強くなった」…
このような気持ちの変化、感じたことはありませんか?
今回は、わたしたち40〜50代の女性が向き合いがちな「メンタルヘルス」について、基本的な知識をお伝えします。何より大切なのは、心の変化も体の変化と同じく「自然なこと」として理解すること。そして必要なときには専門家の力を借りること。
ひとりで抱え込まずに、いっしょに乗り越えていきましょう。
■ 「うつ」ってどんな状態?
うつ病の主な症状
わたしが46歳の4月26日に体験した急激な不安と絶望感。あの日を境に「うつ病」と診断され、その後の治療が始まりました。
うつ病の症状は、大きく「心の症状」と「体の症状」に分けられるといわれています。
〈心の症状〉
- 気分の落ち込みや悲しさが続く
- 何をしても楽しめない、興味が持てない
- 集中力や決断力の低下
- 自己評価の低下、自分を責める気持ち
- 過度の罪悪感
- 将来に対する悲観的な考え
- 死について考えることが増える
〈体の症状〉
- 疲れやすさ、だるさ
- 睡眠の問題(眠れない、または過眠)
- 食欲の変化(減退または増加)
- 体の動きが遅くなる、または落ち着きがなくなる
- 頭痛や消化器症状など、原因不明の身体症状
これらの症状が2週間以上続き、日常生活に支障をきたしている場合は、主治医もしくは病院の判断を得たほうがいいといわれています。
うつ病の診断基準
うつ病の診断は、国際的な基準に基づいて行われているそうです。:
「うつ病の診断には、気分の落ち込みや興味・喜びの喪失を中心とした症状が、一定期間継続して存在すること。また、これらの症状が社会生活や職業生活に支障をきたしていることも重要なポイントです」
つまり、「つらい」だけでなく「生活に支障がある」ということが診断の大きなポイントとのこと。
メンタルヘルス不調のスペクトラム
メンタルヘルスの状態は「健康」から「重度の障害」まで、連続的なスペクトラム(幅)を持っています。
軽度の不調:一時的な気分の落ち込みや不安を感じるが、日常生活はほぼ通常通り送れる状態。誰にでも起こりうる自然な反応です。
中等度の不調:気分の落ち込みや不安が強まり、日常生活や仕事に少し影響が出始める状態。集中力の低下や疲れやすさを感じることが増えます。
重度の不調:症状が強く、日常生活や仕事に明らかな支障をきたす状態。専門家の治療が必要です。
どの段階であっても、早めの気づきと対処が大切です。軽度の症状を放置すると、重度化することもありますので、ジャーナリングなど心の変化を書き留めておくことがおススメです。
■ 更年期とうつの不思議な関係
ホルモンと気分の密接な関係
更年期に入ると、エストロゲン(女性ホルモン)の分泌が減少・不安定になるといわれています。このエストロゲンは、単に生殖機能だけでなく、脳内の神経伝達物質にも大きな影響を与えているそうです。
エストロゲンは、セロトニンやドーパミンといった気分に関わる脳内物質の働きを調整する役割も持っているため、更年期のホルモン変動は、これらの物質のバランスを崩し、メンタルヘルスに影響を及ぼすことがあるそうです。
つまり、更年期とうつは単なる「同時期に起こる別々の問題」ではなく、生物学的にも密接に関連しているのです。
更年期うつの特徴
更年期に起こるうつ症状(更年期うつ)には、いくつかの特徴があります:
- ホットフラッシュや寝汗などの身体症状と同時に起こることが多い
- 気分の波が激しい(朝は落ち込むが、夕方は回復するなど)
- 不安感や焦燥感が強い
- 睡眠障害が顕著(とくに早朝覚醒)
- 集中力や記憶力の低下が目立つ
わたしの場合、42歳で更年期症状が始まり、46歳でうつ病を発症。振り返れば、この4年間、徐々に心と体の変化が進行していたのだと思います。最初の「眠れない」という症状から、「お風呂で泣けてくる」「仕事への意欲低下」と症状が進み、最終的に「強い不安と希死念慮」というピークを迎えました。
「わたしだけ?」じゃないことを知る
厚生労働省の調査によると、更年期障害を経験する女性の約30〜40%が、うつ症状を併発するといわれています。
つまり、あなたの「なんだか気持ちが沈む」「急に涙が出る」といった症状は、決して特別なものでも、あなたひとりの問題でもないのです。
更年期とうつの両方に悩む女性が多いからこそ、わたしはこのサイトを立ち上げました。ひとりで抱え込まず、「こんなん(困難)」を共有し、乗り越えるヒントを見つけていきましょう。
■ 脳内物質のふしぎな働き
幸せホルモン?セロトニンとドーパミン
わたしたちの気分や感情は、脳内の神経伝達物質によって大きく左右されています。とくに重要なのが「セロトニン」と「ドーパミン」です。
セロトニンは「心の安定剤」とも呼ばれ、気分の安定、幸福感、食欲、睡眠などをコントロールしています。セロトニンが不足すると、落ち込みや不安、睡眠障害などが起こりやすくなります。
ドーパミンは「やる気や快感のホルモン」で、動機づけや報酬系に関わっています。何かを達成したときの「やった!」という感覚は、ドーパミンの働きによるもの。ドーパミンが不足すると、喜びや意欲の低下につながります。
うつ病の発症には、セロトニンやドーパミンなどの神経伝達物質のバランスの乱れが関係しているといわれています。更年期の女性ホルモン変動は、これらの物質の産生や機能に影響を与えることがわかっています。
脳内物質のバランスは、ホルモン変動だけでなく、ストレス、睡眠、食事、運動、人間関係など、様々な要因によって影響を受けます。これらの要素を整えることが、メンタルヘルスを保つ上で重要なのです。
ストレス反応のメカニズム
「ストレス」という言葉、よく耳にしますよね。実は、ストレスへの反応はわたしたちの体を守るための大切な機能なのです。
ストレスを感じると、体内では「戦うか逃げるか(fight or flight)」反応が起こります:
- 脳の視床下部から指令が出て、副腎皮質刺激ホルモン放出因子(CRF)が分泌される
- それに反応して下垂体から副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)が分泌される
- さらに副腎からコルチゾール(ストレスホルモン)やアドレナリンが分泌される
- 心拍数増加、血糖値上昇、筋肉の緊張など、体が「非常事態」に備える
この反応は本来、わたしたちを危険から守るための重要なシステム。でも、長期間ストレスにさらされ続けると、このシステムが過剰に働き続けて疲弊してしまい、心身の不調を引き起こすことがあります。
更年期特有のホルモン変動は、このストレス反応システムの感受性を高めることがあるため、同じストレスでもより強く反応してしまうことがあるのです。
■ ストレスの波を乗りこなす
「敵」ではなく「味方」に変える発想
ストレス反応はもともと、わたしたちを守るための大切なシステム。このシステムを「敵」ではなく「味方」として活用する考え方が大切です。
「ストレス反応を味方にする」考え方:
- ストレス反応は「危険信号」と捉え、「何か対処が必要なサイン」と解釈する
- 心や体からのサインを無視せず、早めに休息や対処法を取り入れる
- 「完璧にこなせない自分」を責めるのではなく、「今の自分に合った対処」を考える
たとえば、仕事中に急に疲れを感じたら「サボりたい」という”罪悪感”ではなく、「体からの大切なサイン」と捉えて、短い休憩を取る。これがストレス反応を味方にする第一歩です。
セルフケアのための3つの柱
メンタルヘルスを整えるセルフケアには、主に3つの柱があるそう:
1. 身体的なセルフケア
- 適度な運動(ウォーキング、ヨガなど)
- バランスの良い食事
- 十分な睡眠と休息
- 過度の飲酒やカフェインの摂取を控える
2. 心理的なセルフケア
- 瞑想やマインドフルネス
- 趣味や楽しみの時間を作る
- 日記やジャーナリングで感情を整理する
- 「良いこと3つ」を毎日見つける習慣
3. 社会的なセルフケア
- 信頼できる人との交流を大切にする
- 孤立せず、必要なときに助けを求める
- 「No」をやんわり伝える(過剰な負担を避ける)
- 同じ経験を持つ人々とのつながりを作る
わたし自身、うつ病と診断された後は、「休息」を意識的に取り入れるようになりました。「一生懸命働く女性」ではなく、「休む時間も大切にする女性」へと自己イメージを変化させることで、少しずつ心と体のバランスを取り戻しています。
専門家の助けを借りるタイミング
セルフケアも大切ですが、ときには専門家(心療内科や精神科)の助けを借りることを強くおすすめします:
- 2週間以上、気分の落ち込みや意欲低下が続いている
- 日常生活や仕事に明らかな支障が出ている
- 自分を傷つけたり、死について考えることがある
- セルフケアを試みても改善が見られない
- 睡眠や食欲の乱れが著しい
わたしの経験ですが、早期発見、早期治療が重要だなと感じています。症状が軽いうちに相談することで、回復も早くなる気がしています。
■ 更年期×うつを乗り越えるポイント
「自分を許す」という勇気
更年期とうつの両方と闘っているとき、最も難しいのは「自分を許す」ことかもしれません。
かつての自分のパフォーマンスを基準にして、今の自分を責めてしまうことがあります。「前はこんなに疲れなかったのに」「昔はもっと集中力があったのに」…
そんなとき、こう考えてみてはいかがでしょうか:
「わたしの体と心は、大きな変化の途中にある。劣化ではなく変化。変容の途中で立ち止まることも、休むことも、必要な過程なのだ」
変化を受け入れ、自分を許すことは、一日でできることではないかもしれません。でも、少しずつその考え方を取り入れていくことで、心の負担は軽くなっていきます。
「見えない痛み」を言葉にする大切さ
更年期とうつ、どちらも「見えない痛み」を伴うものです。周囲からは理解されにくく、自分自身でも説明しづらい症状に悩まされることがあります。
自分の感じていることを言葉にし記録していくと、自分の状態を客観的に見つめる機会にもなりますし、同じ経験をしている人に共有することで、お互いの支えにもなります。
わたしがこのサイトで体験を語るのも、そのような思いからです。あなたの「見えない痛み」も、ぜひ言葉にしてくださるとうれしいです。
■ おわりに:心の波を受け入れる
更年期とうつに関する知識は、わたしたちが自分自身を責めず、必要な助けを求めるための武器となります。
心と体は、40代、50代に大きな変化を経験します。それは「悪いこと」ではなく、女性の一生における自然な変化のプロセス。その変化の途中で、不調を感じることも自然なことなのです。
いつか振り返ったとき、この時期が「大変だったけれど、自分自身を深く知るきっかけになった」と思えるように。
「困難な日も、こんなんな日も」
── こんなんさん
※この記事についてのご感想や、あなた自身の体験談などがありましたら、ぜひコメント欄でシェアしてください。みなさんの声が、次の記事の励みになります。
*「こんなんな日も」とは、「こんなん出た」、「こんなんいるー?」など、関西弁から取りました。ただ、管理人は関西人ではありません…。