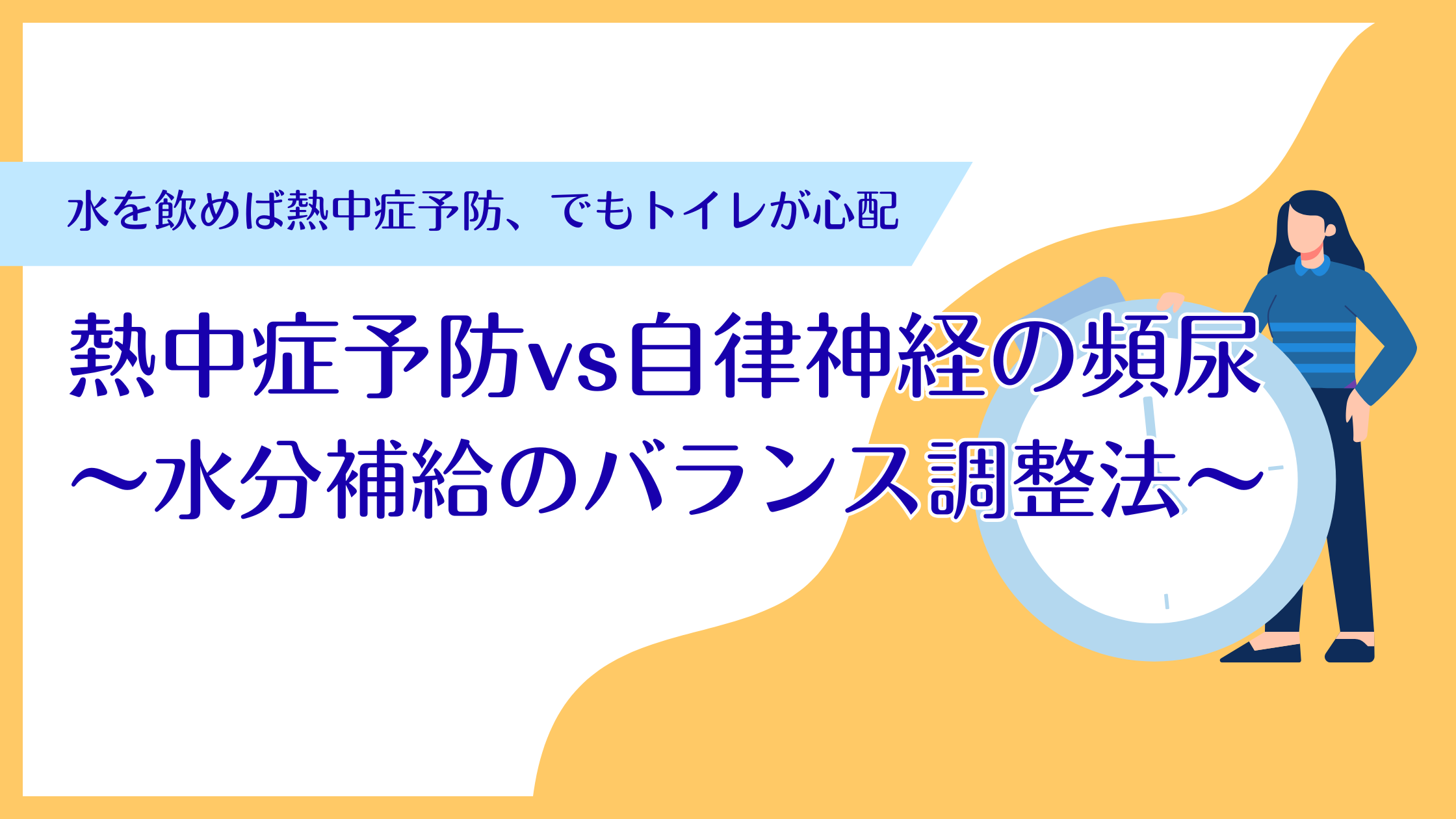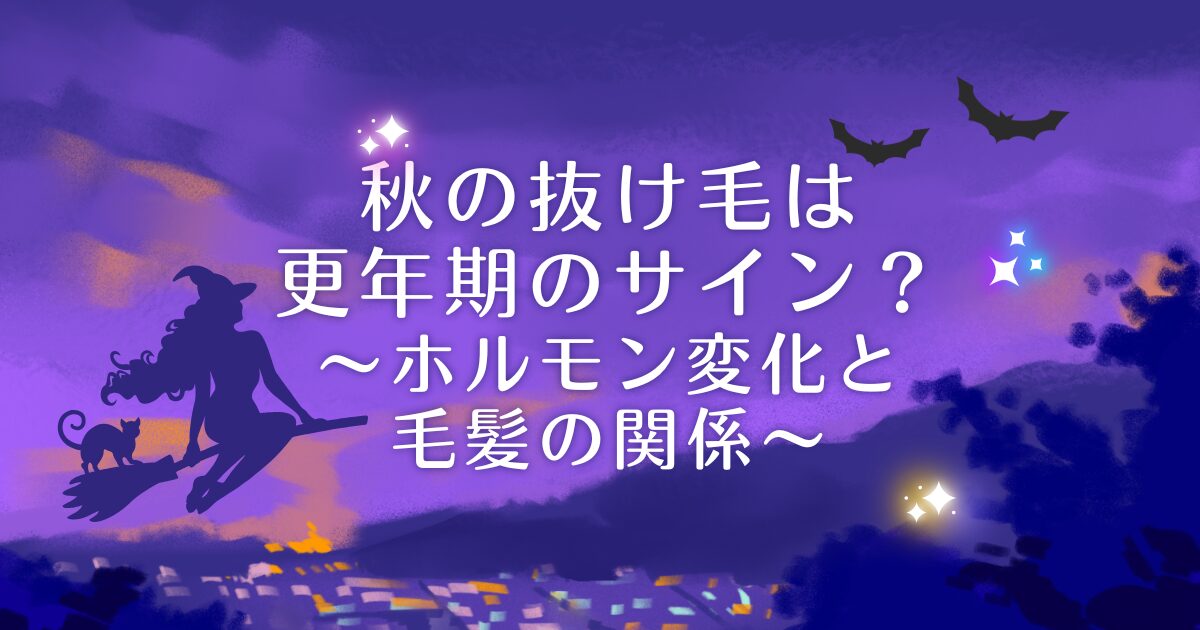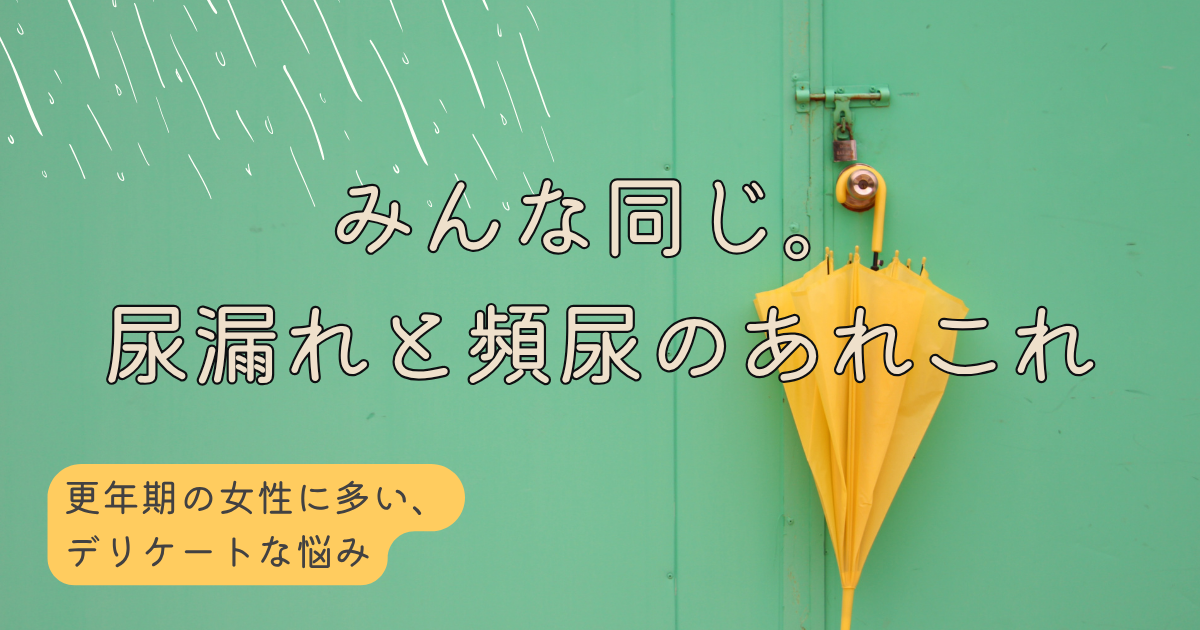更年期の朝が辛い|午前中の仕事を乗り切る対策とコツ

午前仕事のこんなん(困難)をウォームアップ!
〜更年期×うつの午前中の仕事時間(9:30-12:00)の過ごし方〜
「会議で言葉が出てこない」「ミスが増えた気がする」「トイレが近くて困る」…
「困難な日も、こんなんな日も」の管理人、こんなんさんです。
今回は、更年期とうつを抱えるわたしたちの「午前中の仕事時間(9:30-12:00)」について、率直に向き合ってみたいと思います。
かつては得意だった午前中の仕事時間。でも、40代半ばを過ぎたあたりから、午前中の「パフォーマンス」にばらつきがあるように感じませんか?
集中力の波が読めない、記憶力の低下、突然の焦燥感…「以前の自分ならできたのに」という自己不信。
そんな午前中の仕事時間の困難を少しでも和らげる方法を、経験を交えながら考えてみましょう。
「なんだっけ?」が口癖に?午前中の仕事のこんなんポイント
記憶力・集中力の低下と「ブレインフォグ」の正体
更年期に入ると、「ブレインフォグ」と呼ばれる症状を経験する方が増えます。まるで霧がかかったように、思考がぼんやりして集中できない状態です。
ある日の午前の会議のこと。上司から「先日の資料の件、どうなった?」と質問され、頭が真っ白に。「あの資料…あの…」と言葉に詰まり、内心パニックに。
資料のことは覚えているはずなのに、なぜか言葉が出てこない。頭の中でグルグル考えは回っているのに、それを言葉にする「変換機能」がうまく働かないような…。
こんな体験、一度や二度ではありません。とくに午前中は、なぜか脳が完全に起動していない感じがして、ちょっとした質問にも答えられないことがありました。
会議での言葉の出にくさと焦燥感
会議や打ち合わせで意見を求められたとき、「あれ?何を言おうとしていたんだっけ?」と思考が途切れる経験はありませんか?
とくに複数人がいる場面では、この「言葉が出てこない」症状が悪化します。みんなが自分を見ている中で言葉に詰まると、余計に焦りが生じて、さらに言葉が出なくなる…という悪循環に陥りがち。
「以前の自分なら、もっとスマートに答えられたのに…」 「なんでかんたんなことが言えないんだ…」
そんな自己不信が心に広がり、会議が終わった後も長く引きずってしまうことも。
午前中特有の身体的不調
午前中は、体内時計やホルモンバランスの影響で、身体的な不調が出やすい時間帯です。
気になるのがトイレの近さ。会議中に「あ、トイレに行きたい」と感じても、立ち上がるタイミングを逃してしまったり、「また?」と思われそうで言い出せなかったり…。
そして、ときに起こる「尿漏れ」への不安。こんな話、なかなか周囲には打ち明けられませんよね。でも、40〜50代の女性の3人に1人は経験しているとも言われています。けっして珍しいことではないのです。
午前中の仕事のこんなん(困難)を乗り切るための私の工夫
「脳のウォームアップ」で集中力アップ
❶ 出社後15分は「準備運動」の時間に
午前中のパフォーマンスを上げるために、出社後すぐの15分間を「脳の準備運動」の時間に設定するのはどうでしょう。
- 今日のタスクを紙に書き出す(デジタルよりアナログの方が記憶に定着します)
- 優先順位を1-2-3と振る
- 最も重要なタスク「今日のMIT(Most Important Task)」を決める
効果的なのは、「今日のMIT」を決めること。これを達成できれば、その日は成功と考えるタスクを1つだけ選びます。集中力が落ちてきても、このMITだけは完了させる意識を持つことで、成功体験が積み重なります。
「すべてをこなそう」とすると挫折しがちですが、「これだけはやる」と決めたものに集中すると、不思議と達成できることが増えました。
❷ 「午前中の黄金時間」を見極める
更年期とうつがあっても、午前中のどこかに「脳がクリアに動く時間帯」が存在することに気づきました。この「黄金時間」は人それぞれ異なります。
私の場合、10:15〜11:00の間が最も頭がクリアになる時間。この時間帯を見つけるには、1週間ほど「調子がいい時間」をメモするだけ。
この黄金時間には:
- 最も頭を使う仕事
- 創造的な作業
- 重要な意思決定
を集中して行うようにしています。逆に、資料の整理や単純作業は、集中力が落ちる時間帯に回すようにしました。
❸ メモを「躊躇なく」取る習慣をつける
記憶力低下を自覚しているからこそ、メモ取りを「当たり前の行動」として堂々と行うようにしています。
- 小さなメモ帳を常に持ち歩く
- 会議前に日付と参加者を先に書いておく
- 聞きながら箇条書きでキーワードだけメモする
効果的だったのは、「手帳タイプ」ではなく「上から開くフリップタイプ」のメモ帳を使うこと。さっと取り出してメモできるので、自分も負担に感じません。
また、会議の内容を録音させてもらえる場合は、録音も活用。「後で確認したいので録音させてください」と事前に伝えると、大抵の場合は了承してもらえます。
会議での「言葉詰まり」対策
❶ 「準備」と「テンプレート」で安心感を作る
会議での言葉詰まりを防ぐため、事前準備とテンプレート化を習慣にしています。
- 予想される質問に対する答えを3行でメモしておく
- 「~についてですが、まず第一に…第二に…最後に…」という型を作っておく
- 「少し整理させてください」というフレーズを用意しておく
大切だなと思うのは、「少し整理させてください」というフレーズ。言葉が詰まったとき、このフレーズを使えば、考える時間を合法的に確保できます。焦らず、メモを見る時間ができるのです。
❷ チーム内で「バディシステム」を構築する
信頼できる同僚と「バディシステム」を作れると心強いです。
- お互いの調子が悪い日をさりげなくカバーする約束をする
- 言葉に詰まったとき、さりげなくフォローしてもらう
- 「〇〇さんはどう思いますか?」と振ってもらえるよう頼んでおく
私の場合、同世代の女性同僚と「今日はちょっとしんどいから、フォローして」と伝え合える関係を築きました。これがあるだけで、会議への不安が大幅に軽減します。
❸ 「言えなかった」を引きずらない技術
会議で言葉に詰まったとき、その後も自己嫌悪でへこむときも。そんなときの対処法として:
- 「3分間だけ」完全に落ち込む時間を作り、その後は意識的に切り替える
- 「完璧な自分」を求めないことを日々言い聞かせる
- 「私だけじゃない」と思い出す(実際、多くの人が同じ経験をしています)
完璧主義を手放すことは、更年期とうつを乗り越える大きなカギ。「今日の自分」を受け入れることで、少しずつ心を軽くしていきましょう。
身体の不調を和らげる「見えない対策」
トイレの近さと尿漏れ対策
❶ 「躊躇なく」行くことを自分に許可する
トイレに行くことへの罪悪感や躊躇いがある方は多いと思います。でも、身体のサインを無視するほうがリスクは高いです。
- 会議前に必ず行く習慣をつける
- 1時間に1回は行く計画を立てる
- 長時間の会議では休憩時間を確保してもらうよう調整役に事前に伝える
もし「また?」と思われそうで不安なら、水分を多く摂っていることや、「健康のため」と前向きに考えると気が楽になります。トイレはむしろ、短い「リフレッシュタイム」と考えましょう。
❷ 「備えあれば憂いなし」の安心アイテム
尿漏れの不安がある場合、備えておくと安心なアイテムがあります。
- 吸水ショーツを活用する(通常の下着のように見えて、尿を吸収。消臭効果もあります)
- 薄手の尿漏れパッドを使用する(かぶれに注意。こまめな交換が大事です)
- フェムケアスプレーで清潔感を保つ
「吸水ショーツ」は近年品質が向上し、見た目も普通の下着と変わらないものが増えています。「もしも」の安心感があるだけで、集中力もぐんと上がります。
❸ 骨盤底筋トレーニングをこっそり実践
尿漏れ予防に効果的な「骨盤底筋トレーニング」は、デスクに座ったままでもできます。
- 会議中でも、お尻の穴を5秒間締めて、5秒間緩める運動を繰り返す
- エレベーター待ちの間に骨盤底筋を上に引き上げるイメージで力を入れる
この「見えないトレーニング」は、継続することで少しずつ効果が出てきます。何より、「対策している」という安心感が、心の余裕につながりますよね。
突然の発汗や体温調節の乱れへの対策
❶ オフィスでの「冷え対策グッズ」
オフィスでの突然の冷えや熱さに対応するため、デスク周りに以下のアイテムを常備しています。
- 薄手のストールやカーディガン(温度調節用)
- 保冷剤やクールタオル(ホットフラッシュ対策)
- 保温効果のあるスリッパ(足元の冷え対策)
ストールは必需品。首元を温めるだけでなく、汗をかいたときのカバーにもなります。
❷ アロマスプレーで気分転換
気分の落ち込みや集中力低下を感じたとき、アロマの力を借りるのも効果的です。
- レモン、ペパーミント、ローズマリーなどの香りは集中力アップに
- ラベンダー、イランイランなどはリラックス効果に
- ハンカチに1滴垂らしたり、マスクの外側に軽くスプレーするだけでOK
私の実感としては、レモンの香りが午前中の「頭のモヤモヤ」を晴らすのに最も効果的でした。もちろん、周囲の方に配慮して、強すぎない香りを選ぶことが大切です。ちょっとした香りあわせも楽しめるから気分転換になります。
事前に「備える」ことで安心感を作る
午前中を乗り切るための「前日の準備」
❶ 「翌日の服」を決めておく
朝の判断力低下を考慮して、仕事着は前日のうちに細部まで決めておくことをおすすめします。
- 服だけでなく、アクセサリーや靴までセットしておく
- 天気予報をチェックして、羽織りものも準備しておく
- 「これで合ってる?」と悩む時間を減らす
特に効果的なのは、「洋服の定番化」。よく似合うコーディネートを5〜6パターン決めておき、迷わず選べるようにしています。判断の数を減らすことで、朝のエネルギー消費を抑えられます。
❷ 「明日のタスク」を3つだけリストアップ
前日の終業時に、翌日取り組むタスクを3つだけリストアップする習慣をつけると効果的です。
- 最重要タスク1つ
- 重要タスク1つ
- できればやりたいタスク1つ
「3つ以上はリストに入れない」というルールを自分に課すことで、タスクの洪水に溺れることなく、集中力を維持できます。
❸ 「朝のエネルギー」を温存するための準備
朝の限られたエネルギーを温存するため、以下の準備も効果的です。
- 通勤バッグの中身を前日に確認する
- 朝食の準備をしておく(ヨーグルトに果物を切っておくなど)
- 無駄な動きも愛嬌と受け止める
「認知機能」をサポートするための工夫
❶ サプリメントと食事の活用
午前中の認知機能をサポートするため、以下の栄養素を意識して摂取しています。
- オメガ3脂肪酸(青魚やサプリメントで)
- ビタミンDとマグネシウム
- 抗酸化物質(ベリー類や緑茶など)
オメガ3系サプリメント。継続して摂取することで、少しずつ「頭の霧」が晴れてきた感覚があります。もちろん、サプリメントは医師や薬剤師に相談の上、自分に合ったものを選ぶことが大切ですし、あくまで食事の補助的な存在として考えましょう。
❷ 「もしも」のバックアップ体制を整える
記憶力や判断力の低下に備えて、バックアップ体制を整えておくと安心です。
- スマホのリマインダー機能を活用する
- 同僚に共有しておく
- クラウドツールで資料を管理し、どこからでもアクセスできるようにする
効果的なのは、「予定の二重化」。紙の手帳とデジタルカレンダー、両方に予定を記入することで、片方を見落としても大丈夫な体制を作っています。めんどくさいより心配を減らすことを大事にしています。
完璧主義と「失敗の恐怖」から解放される
「以前のわたし」という幻想との決別
わたしは昔から「だらしがない」と思い込んでいました。その割には、ミスは許されない、常に成果を出すことがミッション——そんな裏腹な自分への厳しい要求が、長年の習慣となっていました。
しかし更年期に入り、うつの症状も重なると、この完璧主義が大きな重荷に。かつてはできていた「ミスの少なさ」が、いまや達成できない目標となり、自己評価を下げる要因になってしまったのです。
ある日の午前中、重要な資料作成中に単純なミスをしてしまいました。以前なら簡単に修正して前に進めたはずなのに、その日はなぜか頭が真っ白に。「またミスした」という思いが頭を占領し、修正方法すら思い浮かばなくなりました。
ミスによる「フリーズ」状態—これが新たな困難として現れてきたのです。
ミスをした時に「動けなくなる」対処法
ミスがトリガーとなって、突然頭が真っ白になる「フリーズ状態」。この状態から抜け出すために、いくつかの対処法を見つけました。
- 「5-4-3-2-1」感覚リセット法:目で見えるもの5つ、聴こえる音4つ、触れるもの3つ、嗅ぐことができるもの2つ、味わえるもの1つを意識的に探す。この方法で、「今ここ」に意識を戻します。
- 「失敗ノート」の活用:小さなノートに「今日の失敗と教訓」を記録する習慣をつける。「記録することで客観視する」という行為が、失敗への過剰反応を和らげてくれます。
- 「停止・呼吸・進む」の3ステップ:ミスをしたと気づいたら、まず作業を停止し、深呼吸を3回。そして「次に何をすべきか」だけを考える。過去のミスを掘り返さない。
最後の「停止・呼吸・進む」は、日々の仕事の中で実践しやすく効果的です。この3ステップによって、「完璧にできなかった自分」を責める時間を最小限にし、次のアクションに移る力を取り戻せるのです。
「失敗の公開」で恐怖感を減らす
完璧主義から抜け出す過程で大きな転機となったのは、信頼できる同僚に「わたし、最近ミスが増えてて…」と正直に打ち明けたことでした。
すると驚くべき反応が。「えっ、こんなんさんがミスするなんて思ってなかった!わたしなんて毎日してるよ」と。
わたしの中の「みんな完璧にこなしている」という思い込みが、実は幻想だったことに気づかされました。他の人も同じように苦労していたのに、私だけがそれを隠し、自分だけが特別にダメなのだと思い込んでいたのです。
以来、ミスをした時は、適切な範囲で「あ、ごめん、ここミスしちゃった」と素直に言えるようになりました。この「失敗の公開」が、不思議と恥ずかしさや恐怖感を減らしてくれたのです。
完璧主義の殻を少しずつ脱ぎ捨てる過程は、決して簡単ではありません。でも、「ミスをしない人」から「ミスをしても前に進める人」へと自己イメージを変化させることで、心の余裕を生むようにしています。
おわりに:「以前のわたし」との比較をやめる
更年期とうつを抱えながら仕事を続けるわたしたちが心に留めておきたいのは、「以前の自分」と比較しないこと。
「前はこんなミスしなかったのに」 「昔はもっと頭の回転が速かったのに」
そんな思いが浮かんできても、それは自分を責める材料ではなく、「今は違う状況にある」という事実を受け入れるきっかけにしましょう。
更年期とうつによる変化は、「劣化」ではなく、「変化」です。そして、その変化に合わせた新しい工夫や習慣を取り入れることで、十分に仕事は続けられます。
むしろ、これまでの経験や知恵が、若い頃にはない強みになることも。午前中の調子の波を認識し、それに合わせた働き方を模索することで、新たな自分の強みを発見できるかもしれません。
みなさんは、午前中の仕事のこんなんに対してどんな工夫をされていますか?
「困難な日も、こんなんな日も」
── こんなんさん
⚠️ 免責事項 ⚠️
本記事の内容は、管理人の個人的な体験談であり、医学的なアドバイスや診断に代わるものではありません。更年期の症状や対処法には個人差があります。心配な症状がある場合は、必ず医療機関を受診し、医師にご相談ください。
※この記事についてのご感想や、あなた自身の体験談などがありましたら、ぜひコメント欄でシェアしてください。みなさんの声が、次の記事の励みになります。
*「こんなんな日も」とは、「こんなん出た」、「こんなんいるー?」など、関西弁から取りました。ただ、管理人は関西人ではありません…。