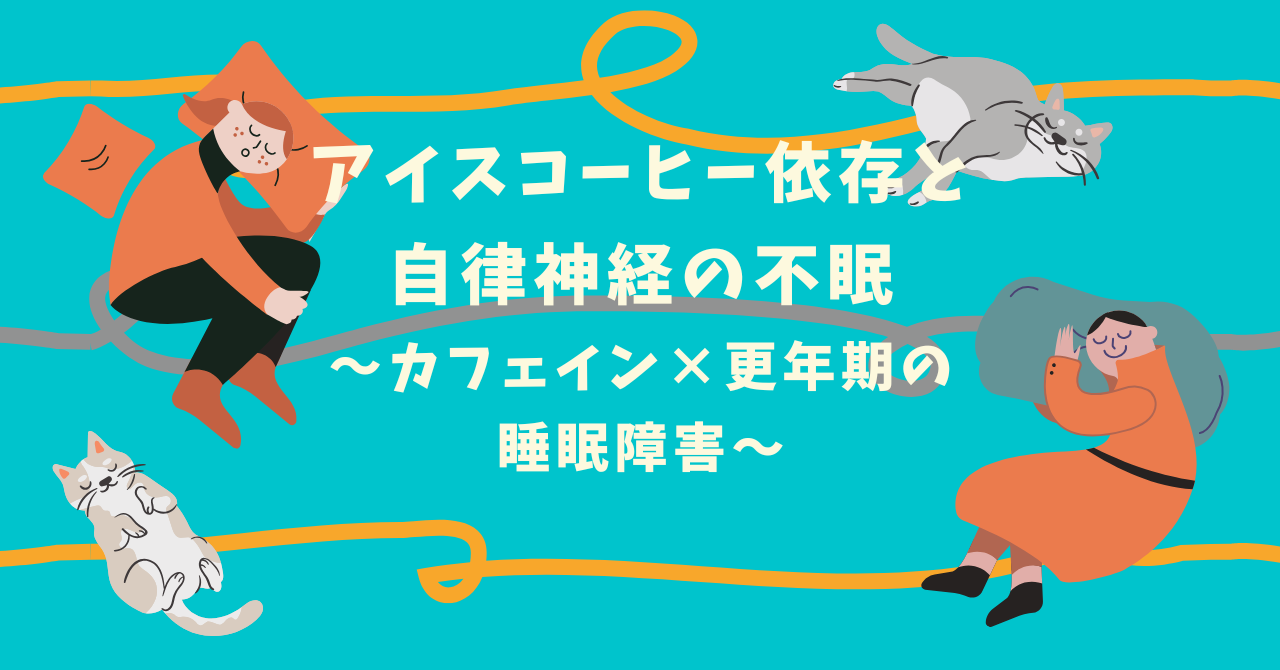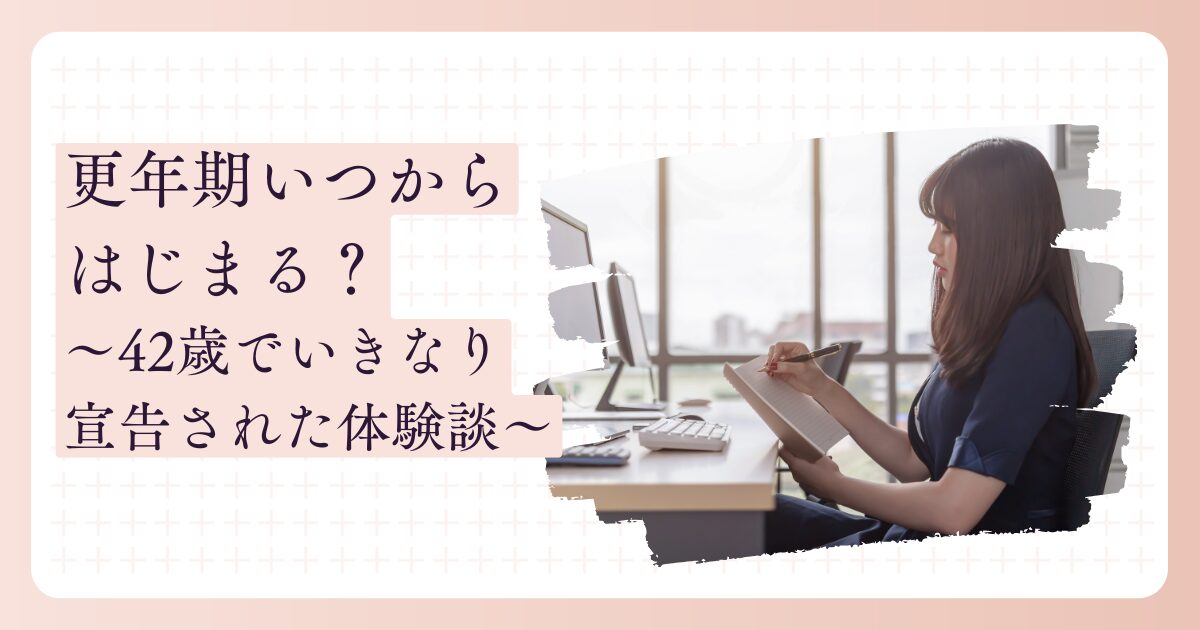更年期で眠れない秋の夜|睡眠障害の原因とは
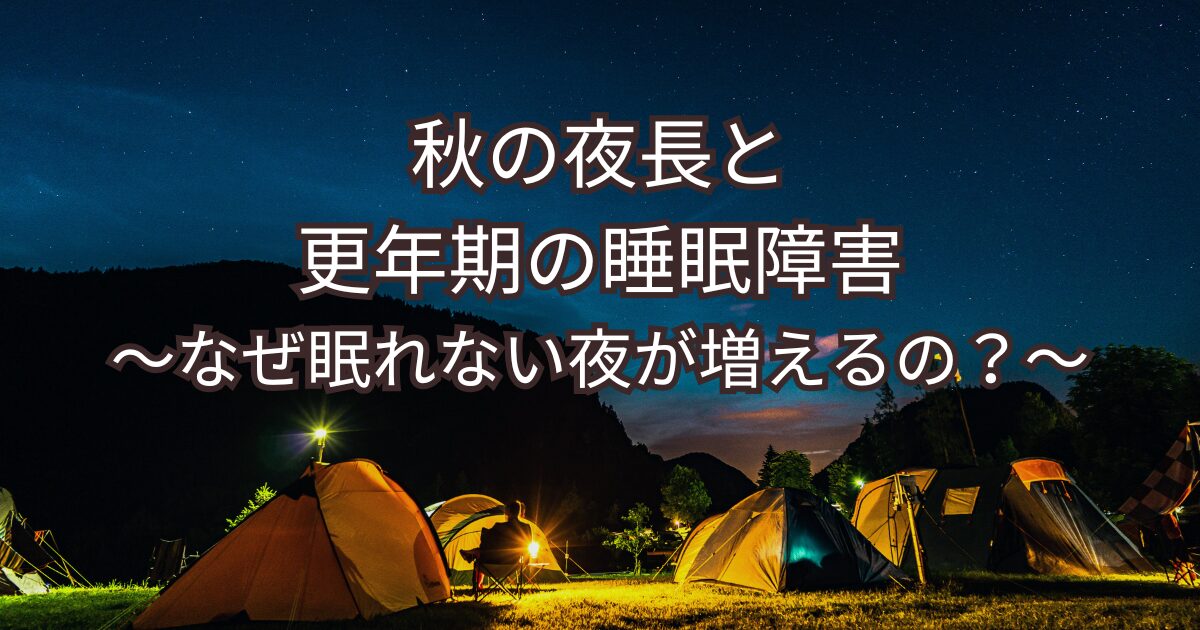
秋の夜長と更年期の睡眠障害〜なぜ眠れない夜が増えるの?
〜秋の訪れとともに深まる不眠の謎〜
「困難な日も、こんなんな日も」の管理人、こんなんさんです。
最近、夜がすっかり長くなってきましたね。秋の虫の声を聞きながら、「読書の秋」「芸術の秋」なんて素敵な響きにワクワクしていたのですが…気づけば、眠れない夜が増えていませんか?
わたしも47歳になってから、特に秋になると睡眠の質が落ちる気がしていました。「夜が長いはずなのに、なぜ眠れないんだろう?」と不思議に思っていたんです。ベッドに入っても目が冴えてしまったり、夜中に何度も目が覚めたり…。更年期だから仕方ないと思っていたけど、実は秋という季節そのものも大きく関係していることを最近知りました。
今日は、秋の夜長と更年期の睡眠障害について、日照時間の変化やメラトニンとの関係をひも解きながら、お話ししたいと思います。
秋になると眠れなくなる理由〜日照時間の変化が体に与える影響
日が短くなることの意味
秋分の日を過ぎると、日に日に日照時間が短くなっていきます。9月下旬には約12時間だった日照時間が、11月には10時間を切るほどに。たった2時間程度の変化と思われるかもしれませんが、この変化が私たちの体内時計に大きな影響を与えているんです。
人間の体は、太陽の光を浴びることで「今は昼間だ、活動する時間だ」と認識し、暗くなることで「夜だ、休息の時間だ」と判断します。この体内リズムを整えているのが「概日リズム(サーカディアンリズム)」と呼ばれる、約24時間周期の生体リズムです。
秋になって急激に日照時間が短くなると、この体内時計が混乱しやすくなります。特に更年期世代の私たちは、ホルモンバランスの変化でただでさえ体内リズムが乱れがち。そこに季節の変化が重なると、睡眠障害がより深刻になってしまうんですね。
朝の光を浴びられない生活習慣の落とし穴
現代の生活では、朝起きてすぐに太陽の光を浴びる機会が減っています。カーテンを閉めたまま朝を迎え、そのまま家事をしたり、すぐに通勤電車に乗ったり…。特にリモートワークが増えてからは、一日中室内で過ごすことも珍しくありません。
わたし自身、在宅ワークの日は朝起きてもカーテンを開けずにパソコンに向かってしまうことがありました。気づけば午前中が終わっていて、「あれ、今日一度も外の光を見てないかも」なんてことも。これが体内時計をさらに狂わせる原因になっていたんですね。
朝の光を浴びることは、体内時計をリセットし、夜の睡眠の質を高めるために欠かせません。特に秋は日の出も遅くなるので、意識的に朝日を浴びる習慣をつけることが大切だと気づきました。
メラトニンと睡眠の深い関係〜更年期が与える影響
メラトニンってなに?「睡眠ホルモン」の正体
メラトニンは、脳の松果体という部分から分泌されるホルモンで、「睡眠ホルモン」とも呼ばれています。このメラトニンが、私たちの眠りを誘導してくれる重要な役割を果たしているんです。
メラトニンの分泌は光に大きく影響されます。明るい光を浴びると分泌が抑制され、暗くなると分泌が増えて眠気を感じるようになります。通常、夕方から夜にかけて徐々に分泌量が増え、深夜にピークを迎え、朝方には減少していきます。
このメラトニンのリズムが正常に働くことで、私たちは自然に眠くなり、朝にはすっきりと目覚めることができるわけです。でも、このリズムが乱れると…眠れない夜が続くことになってしまうんですね。
秋の日照時間短縮がメラトニン分泌に与える影響
秋になって日照時間が短くなると、日中に十分な光を浴びられなくなります。すると、体は「今は昼間なのか夜なのか」の判断が曖昧になり、メラトニンの分泌タイミングがずれてしまうことがあります。
また、早く暗くなることで、本来ならまだ活動している時間帯にメラトニンの分泌が始まってしまい、夕方に眠気を感じることも。そして夕方に少し眠ってしまうと、夜になっても眠れない…という悪循環に陥りやすいんです。
わたしも経験があります。秋の夕方5時頃、まだ夕食の準備もしていないのに急に眠気に襲われて、「ちょっとだけ」と思ってソファで横になったら1時間も寝てしまって。そのせいで夜11時になっても目が冴えてしまい、結局夜中の2時まで眠れなかった…なんてことが。
更年期がメラトニン分泌をさらに乱す理由
ここに更年期という要素が加わると、さらに複雑になります。更年期になると、女性ホルモン(エストロゲン)の分泌が急激に減少します。実はこのエストロゲン、メラトニンの分泌にも関わっているんです。
エストロゲンが減少すると、メラトニンの分泌量も減少しやすくなります。つまり、更年期世代の私たちは、もともとメラトニンが出にくい体質になっているところに、秋の日照時間短縮というダブルパンチを受けているわけです。
さらに、更年期には自律神経のバランスも乱れがち。自律神経は睡眠と覚醒のスイッチを切り替える役割を持っているので、このバランスが崩れると「眠りたいのに眠れない」「眠いのに目が覚める」という状態になりやすいんです。
わたしの場合、ホットフラッシュで夜中に目が覚めることもよくあります。秋になって涼しくなったから少しはマシになるかと思いきや、今度は「寒い?暑い?」と体温調節がうまくいかず、結局何度も目が覚めてしまう…。更年期と秋の組み合わせ、本当に手強いです。
秋の夜長を味方につける〜更年期世代の睡眠改善策
朝のルーティンで体内時計をリセット
秋の睡眠障害を改善する第一歩は、朝の過ごし方から。特に起床後すぐの行動が、その日の睡眠を左右します。
朝のおすすめルーティン:
- 起床後30分以内に朝日を浴びる:カーテンを開けて窓際で5〜10分過ごす
- 朝食をしっかり食べる:体内時計のリセットに食事のタイミングも重要
- 軽いストレッチや散歩:血行を良くして覚醒モードに切り替える
- 朝のコーヒーは起床後1時間以内に:早めのカフェイン摂取で体内時計を整える
わたしが最近始めたのは、起きたらすぐにカーテンを全開にして、窓際でコーヒーを飲むこと。ベランダに出て5分ほどぼーっと空を見上げるだけでも、「ああ、朝だな」と体が認識してくれる感じがします。曇りの日でも、室内よりは明るい光を浴びられますよ。
夕方以降の過ごし方を見直す
秋は日が落ちるのが早いので、夕方の過ごし方も重要です。
夕方から夜にかけての工夫:
- 夕方の仮眠は避ける:どうしても眠い時は15分以内に
- 夕食は就寝3時間前までに:消化に時間がかかる食事は早めに
- 夕方以降はカフェインを控える:コーヒー、紅茶、緑茶は午後3時まで
- 夜の照明を暗めに:オレンジ系の間接照明で体を休息モードに
- 寝る1時間前からブルーライトを減らす:スマホやパソコンの使用を控える
わたしは夜8時以降、部屋の照明を暗めのオレンジ色に切り替えるようにしています。最初は「ちょっと暗くて不便かな」と思ったけど、慣れてくると不思議と落ち着く感じがして。この時間からは、なるべくスマホも見ないようにして、本を読んだり音楽を聴いたりするようにしています。
睡眠環境を整える〜秋ならではの工夫
秋は気温の変化も激しい季節。寝室の環境づくりも重要です。
秋の睡眠環境づくりのポイント:
- 寝室の温度は18〜20度が理想:秋は気温差が大きいので調整を
- 湿度は50〜60%に保つ:乾燥しやすい季節なので加湿も意識
- 寝具の調整:暑すぎず寒すぎない、調整しやすい掛け布団を
- パジャマは吸湿性の良い素材を:更年期の寝汗対策にも
- 遮光カーテンの活用:朝日は浴びたいけど、早朝に目覚めすぎないように
わたしの場合、ホットフラッシュで夜中に汗をかくことがあるので、吸湿速乾性のパジャマに変えました。また、掛け布団は薄めのものを2枚重ねにして、暑ければ1枚はずせるようにしています。ちょっとした工夫ですが、夜中の「暑い!寒い!」で目が覚める回数が減りました。
メラトニンを増やす食事の工夫
実は、食事からもメラトニンの分泌をサポートできるんです。
メラトニン分泌を助ける栄養素と食材:
- トリプトファン:メラトニンの原料(バナナ、ナッツ類、大豆製品、乳製品)
- ビタミンB6:トリプトファンの代謝に必要(魚、鶏肉、バナナ)
- マグネシウム:睡眠の質を高める(ほうれん草、アーモンド、海藻類)
- カルシウム:神経の安定に(牛乳、小魚、豆腐)
朝食にバナナとヨーグルト、夕食に魚料理と納豆を取り入れるなど、少しずつ意識するだけでも違ってきます。わたしは最近、寝る2時間前にホットミルクにはちみつを入れて飲むのがお気に入り。体も温まるし、気持ちもほっこりして、自然と眠気が訪れる感じがします。
それでも眠れないときは〜医療の力も借りよう
「我慢しない」という選択
ここまでいろいろな工夫をお話ししてきましたが、それでも眠れない日が続くときは、無理に我慢する必要はありません。更年期の睡眠障害は、婦人科や心療内科で相談できます。
医療機関を受診するタイミング:
- 2週間以上、寝つきが悪い日が続く
- 夜中に何度も目が覚めて、再入眠できない
- 早朝覚醒が続き、疲れが取れない
- 日中の眠気や集中力低下が仕事に影響する
- 不眠のせいで気分が落ち込む
わたし自身、睡眠障害がひどかったとき、婦人科で相談しました。医師から「更年期の睡眠障害は、ホルモンの変化が原因のことも多いから、適切な治療で改善できますよ」と言われて、少し救われた気持ちになりました。現在は睡眠導入剤の力も借りながら、少しずつ睡眠の質を取り戻しているところです。
「薬に頼るのは抵抗がある」という気持ち、わたしもありました。でも、眠れない日々が続いて心身ともに疲弊するより、適切な治療を受けて元気を取り戻す方が、自分にも周りにも優しいのではないでしょうか。
おわりに:秋の夜長を楽しめる日を目指して
秋の夜長と更年期の睡眠障害—この二つが重なると、確かに辛い日々が続きます。「秋の夜長を読書で楽しむ」なんて、今の自分には遠い世界のように感じることもありますよね。
でも、日照時間とメラトニンの関係、更年期との相関性を知ることで、「あ、これは自分のせいじゃなくて、体の自然な反応なんだ」と思えるようになりました。眠れないことを自分のせいにして責めるのではなく、「今、体が大きな変化の中にいるんだな」と受け止めることが、第一歩なのかもしれません。
朝の光を浴びる、夕方以降の過ごし方を工夫する、食事に気をつける—小さなことから始めて、自分に合った睡眠のリズムを見つけていきましょう。そして、どうしても辛いときは、医療の力を借りることも大切な選択肢です。
いつか、秋の夜長を心から楽しめる日が来ますように。それまでは、焦らず、自分のペースで、一晩ずつ向き合っていきましょう。
みなさんは、秋の睡眠障害にどんな工夫をしていますか?「これは効果があった」という方法があれば、ぜひコメント欄で教えてください。一人ひとりの体験が、同じ悩みを持つ誰かの支えになるはずです。
「困難な日も、こんなんな日も」
── こんなんさん
*「こんなんな日も」とは、「こんなん出た」、「こんなんいるー?」など、関西弁から取りました。ただ、管理人は関西人ではありません…。
参考文献・出典
- メラトニンについて – e-ヘルスネット(厚生労働省)
- 更年期障害 – 日本産科婦人科学会
- 睡眠と生体リズム – e-ヘルスネット(厚生労働省)
- 更年期と睡眠障害 – 日本女性心身医学会
- 体内時計と睡眠のしくみ – 睡眠健康推進機構
⚠️ 免責事項 ⚠️
本記事の内容は、管理人の個人的な体験談であり、医学的なアドバイスや診断に代わるものではありません。更年期の症状や対処法には個人差があります。心配な症状がある場合は、必ず医療機関を受診し、医師にご相談ください。